
『フリーダ・カーロの遺品−石内都、織るように』小谷忠典監督インタビュー
~「私は過去を撮っているのではなく、今を撮っている」
フリーダ・カーロと写真家石井都の魂が共鳴する瞬間~

メキシコを代表する女性画家、フリーダ・カーロ。独特の色遣いとシュールレアリズムを体現するだけでなく、不自由な身体で最後まで画家として、また愛を求めて力強く生き抜いた女性として、死後50年経った今でもメキシコだけでなく、世界のファンを魅了している。そんなフリーダ・カーロの遺品を撮影するプロジェクトがメキシコで立ち上がり、日本を代表する写真家、石内都さんがその依頼を受けたのだ。
石内さんといえば、ドキュメンタリー『ひろしま〜石内都・遺されたものたち』で広島被爆者の遺品を撮影する様子や展示での反響が映し出され、今までとは違う「被爆者の遺品」の捉え方にハッとさせられたことは、記憶に新しい。本作では、かつてから石内さんの熱烈なファンだったという小谷忠典監督が、石内さんのメキシコ撮影旅行に完全密着。さらに別途メキシコ取材を敢行し、遺品を通じて感じ取るフリーダ・カーロの真実や石内さんとの魂の交流、フリーダ・カーロのアイデンティティを支えた民族衣装の作り手たちへのインタビュー、さらに死者と共に過ごす祭りを盛大に行い続けているメキシコという国の死生観にも触れている。
陽光降り注ぐメキシコのフリーダ・カーロ博物館の一室で、特別な照明は一切使わず、自然光だけで撮影する石内さん。多くの遺品を選びながら、かかとの高さの違う靴や薬瓶の数々も美しく撮りあげる。フリーダがお気に入りだったという民族衣装のテワナドレスを、彼女が身に着けているかのように、ひだまで綺麗に再現し、丁寧にディスプレイする。そういった作業を通じて、フリーダと会話をしているかのような石内さんの表情がとても魅力的だ。また全編を通じて、メキシコならではの鮮やかな色合いが映し出され、太陽の国メキシコを旅しているような感覚を与えてくれるのだ。
本作の小谷監督に、石内さんの撮影に同行することになったいきさつや、実際に撮影現場に密着して感じたこと、またメキシコのアイデンティティを象徴する死生観や民族衣装についてお話を伺った。
■石内さんは今まで思い続けてきた人、このチャンスを逃してはいけない。

―――小谷監督は、長年石内都さんのファンだそうですが、どれぐらい前から石内さんの写真に触れていたのですか?
十数年前、僕の学生時代に、写真に文章が添えられた石内さんの写真集『キズアト』があったのですが、それが一番印象的ですね。僕が『LINE』という映画を作ったときは、石内さんへのラブレターのような作品でした。絶対に石内さんに観ていただきたいと思い、パンフ用のコメントをいただけないかとお願いし、トークショーにも登壇していただきました。
―――石内さんの『LINE』に対する感想は?
コザ吉原に入って、ああいう形で撮ったのは非常に貴重だし、傷へのアプローチも好感を持ったとおっしゃっていました。コメントでも「沖縄の女達の純仕事の磁力を表出させた」と書いていただきました。
―――石内さんを映画のテーマにしようと思ったきっかけは?
『LINE』で石内さんにお会いしたとき、とてもすてきな女性だったので、彼女を撮りたいとそのときに思いました。ちょうど『百万回生きたねこ』を撮っていたので、それが落ち着いた2012年12月にお電話したのです。
―――電話でお話をしてからほんの2週間後にメキシコ行きというハードルの高い状況ながら、撮影を決断した一番の動機は?
石内さんのプロジェクトは最近NHKや他の映像作家が密着することが多いのですが、偶然にもメキシコのプロジェクトは誰も撮影として同行しないということも大きかったです。ただ、今まで思い続けてきた人ですから、このチャンスは逃してはいけないという気持ちが一番ですね。
■このプロジェクトを通じて、石内さんは写真表現、僕は映像表現で対峙したい。

―――フリーダ・カーロの作品を撮影するプロジェクトですが、監督ご自身はフリーダ・カーロに対してどのような印象を持っていたのですか?
僕は、ビジュアル・アーツ専門学校に通う前に奈良芸術短期大学で油絵を専攻していたので、フリーダ・カーロの情報は知っていましたし、石内さんが彼女の遺品を撮ると聞き、ぴったりだと思いました。僕も『LINE』で娼婦の方の体の傷を撮っています。フリーダ・カーロも傷だらけの作家ですし、僕も含めて三者がつながったというイメージがありました。
―――憧れていた石内さんを密着する撮影は、どんな気持ちで挑みましたか?
よく石内さんに「僕はファンです」と言っていたら、「そんな安っぽいことは言うな」と。石内さんは十数年ファンで、僕自身の制作にも大きな影響を与えていた方です。影響が大きすぎて撮影できないのではないかと思うぐらいでしたが、このプロジェクトのどこかで石内さんは写真表現、僕は映像表現で対峙したいという思いがありました。緊張感をもって撮影しました。
―――石内さんの仕事ぶりを間近で見た感想は?
3週間、遺品撮影に密着させてもらいましたが、フリーダ・カーロはメキシコでは英雄ですし、石内さんも偉人としてのフリーダの大きさをよく分かっていて、最初は緊張されていました。フリーダ・カーロをしっかり撮ろうと思われていたのでしょう。ただ、フリーダ自身が針と糸でストッキングを修繕した痕跡を発見されたときぐらいから、石内さんがフリーダに対して親しみを持つようになった風に見受けられました。
■遺品をモノというより、フリーダと対話したり接しているように撮影。

―――撮影するものを選ぶときや、洋服をフリーダが着用していたように整えているときの石内さんの表情がイキイキとしていました。最初はあまりフリーダに興味を持っていなかったとおっしゃっていた石内さんですが、撮影を通じて、フリーダとどのような関係を築いたように映りましたか?
フリーダが身につけていたものや、普段生活で使っていた遺品を300点ぐらいの中から選んで撮影していましたが、重たいフリーダのイメージがどんどん剥がれていって、一人の女性として、フリーダを洗い流しているようなイメージがありました。石内さんの撮影の一つの形でもあるのでしょう。モノというより、フリーダと対話したり、接しているような感じでした。時代も、国も越えてフリーダ・カーロと出会い、コラボレーションすることによって全く違う新たなフリーダ像を二人で一緒に作っているように見えました。最後は二人が仲良くなっている、とけあっているような印象を受けましたね。
―――撮影中に親友の訃報に接するなど、プライベートな面での石内さんにも触れたのでは?
石内さんは、遺品の撮影だけではなく、メキシコの文化遺産やご主人のディーゴ・リベラさんの壁画も撮影されていました。それはフリーダの遺品だけではなく、スペインの歴史や文化に触れ、フリーダの背景にあるものを写真でも掬い取っていたのだと思います。カメラで遺品を撮っても、目に見えない部分が映っているように感じましたし、石内さんの親友が亡くなられた後は、遺品の撮影に変化が生まれたと感じました。目に見えない石内さんのまなざしをきちんと映像化、可視化するのが、僕が映像で入った役目だなと思いましたので、3週間の撮影が終わってから1年後に撮影クルーだけでメキシコに行き、目に見えないまなざしを可視化する取材をしました。具体的には、死者の祭りや刺繍家の方たちの取材ですね。
■目の前にある遺品と対峙するからこそ、新しいイメージが出てくる。

―――石内さんと一緒に行動した中で、印象的だったことは?
「私は過去を撮っているのではなく、今を撮っている」という言葉が印象的ですね。過去を撮っていると定着したイメージでしか捉えられないものが、目の前にある遺品と対峙するからこそ、新しいイメージが出てくるのだと思います。『ヒロシマ』という写真集もそうですが、僕たちが原爆で被災された方の遺品と考えると、暗くて、重くて、辛いというイメージで捉えてしまいますが、石内さんはそれを「かわいい」と思ったからキレイに撮ったとおっしゃっていました。それは過去ではなく、今を撮る力だと思います。フリーダも遺品が見つかったときに、最初はメキシコの男性写真家が何人か撮ったそうなのですが、僕も見せてもらいましたが、暗い中でエロチックに撮られている写真でした。フリーダ・カーロ博物館はほとんどが女性スタッフなのですが、彼女たちがフリーダに抱くイメージとそれらの写真とは違ったので、写真を撮ってくれる方を探して、石内さんに辿りついたそうです。実際にできた写真もすごく気に入っておられました。
50年間ずっとしまい込まれていたものが、メキシコのフリーダ・カーロ博物館の庭に出されて、天日干しのようにされていて、フリーダがとても気持ちよさそうにしている気がしました。
■服は地域や国も反映。縫う、染める、織るという服を作る行為が持つ生命感を一番感じた。

―――メキシコの追加取材では、彼女のルーツでもあるテワナドレス発祥の地、オワハカを訪れ、なぜフリーダがこのドレスを愛したのか、その背景が見えてきますね。
石内さんのご友人に象徴される個人の死から、メキシコのもっと大きな死生感につなげるために、死者の祭りを撮りたい。そして、フリーダ・カーロの背景にあるものとして、民族衣装を捉えようと思っていました。海外ジャーナリストの記事も含めて、夫ディーゴ・リベラは土着的嗜好が強かったためフリーダにテワナドレスを着せていたと、よく言われています。ただ、遺品の中でもテワナドレスの数が圧倒的に多かったですし、フリーダの母親がテワナドレス発祥の地、オワハカ出身なのです。僕の解釈では、フリーダは多分母の故郷に来て、自分のアイデンティティとしてテワナドレスを着ていたのだと思います。フリーダは混血児なので、ヨーロッパの衣装なども着ていたのですが、晩年テワナドレスを多く着ていたというのは、このドレスを着ることによってフリーダが安らげ、ぼろぼろの身体をこのドレスが守っていたのではないかと思います。訪れてみると、実際にフリーダがオワハカを訪れたと証言してくださる方もいました。
―――テワナドレスの刺繍家たちを多数取材されたことで、作品がメキシコの伝統や魂にまで通じるものになったのでは?
僕は既製品ばかり着ていて、親から譲り受けた服など一枚も持っていませんが、村に行って、実際にドレスを触ってみると、民族衣装が外界世界と内面世界の狭間にあるような存在だと感じました。映画の中でもオワハカのダンサーが「第二の肌」と表現していますが、まさにそう感じたのです。その人が着ていたときの感情や記憶が、服にすごく内包されていると思います。
服は地域や国も反映させていますし、縫う、染める、織るという服を作る行為が持つ生命感を一番感じました。映像に出てくる刺繍家たちの先祖は奴隷で、貴族のために作っていたのですが、それでもただ作らされていたわけではなく、自分たちの好きな花を取り入れることで楽しみを見出していらっしゃったそうです。
■メキシコは陽気で明るい反面、影もあるコントラストのある国。過去の制圧を受け入れたからアイデンティティを守れた。
―――冒頭でも登場する、3000年前から続いている死者の祭りは、日本の慎ましやかな死者に対する迎え方と違い、かなり賑やかですね。
死者を迎える概念が全く違いますね。沖縄もそうですが、悲しい歴史を持っている場所は逆にすごく明るい面があります。メキシコも、あれだけ制圧や闘争の歴史がある中で、笑い飛ばさなければやっていけないという状況下で、あの明るさがある気がします。陽気で明るくて、本当に愛想がいいのですが、仮面の国とも言われており、仮面の裏では泣いている。陽気で明るい反面、影もあるコントラストのある国だと感じました。
―――死生観の他に、メキシコでの取材で興味深かったことはありましたか?
歴史上混血の国で、血も混ざりあっているのがすごく面白く、あのミックス感は他では味わえません。現地の人がおっしゃっていましたが、「メキシコは、アメリカやスペインなど他の国の人が制圧しにきたが、それを受け入れたから自分たちのアイデンティティを守れた。それを拒否していたら、全てなくなっていたかもしれない」と。
(江口由美)
<作品情報>
『フリーダ・カーロの遺品−石内都、織るように』
(2015年 日本 1時間29分)
監督:小谷忠典
出演:石内都
2015年9月12日(土)~シネ・リーブル梅田、9月26日(土)~神戸アートビレッジセンター、今秋~京都シネマ他全国順次公開
(C) ノンデライコ 2015
 メインキャスト声優が大阪に登場!
メインキャスト声優が大阪に登場! 映画の上映終了後、満員のお客さんの前に大きな拍手で迎えられ、登壇したお二人。
映画の上映終了後、満員のお客さんの前に大きな拍手で迎えられ、登壇したお二人。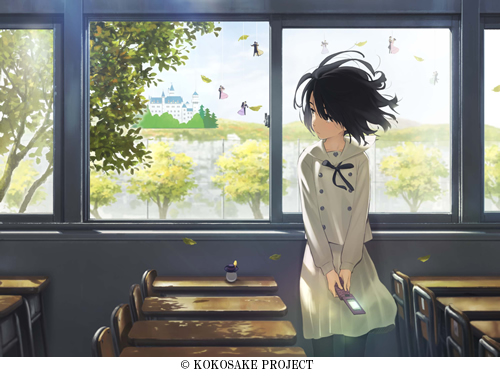 【STORY】
【STORY】




 『高野聖』中村獅童舞台挨拶
『高野聖』中村獅童舞台挨拶

 ――― 泉鏡花の『高野聖』は博多座での公演だそうで?
――― 泉鏡花の『高野聖』は博多座での公演だそうで?
 NHKの絵本の読み聞かせの番組で声だけの語り部のお仕事に出会いました。今は亡き母も動物たちの友情物語が大好きで、この世界観が歌舞伎にも通じるものがあると言っていました。それを10年越しに歌舞伎の舞台で演じることができて本当に嬉しく思っております。また、母が育った京都の地で座頭として公演できて、感慨深いものがあります。
NHKの絵本の読み聞かせの番組で声だけの語り部のお仕事に出会いました。今は亡き母も動物たちの友情物語が大好きで、この世界観が歌舞伎にも通じるものがあると言っていました。それを10年越しに歌舞伎の舞台で演じることができて本当に嬉しく思っております。また、母が育った京都の地で座頭として公演できて、感慨深いものがあります。 『ポプラの秋』中村玉緒記者会見
『ポプラの秋』中村玉緒記者会見 9月19日公開の映画『ポプラの秋』(大森研一監督)に“不思議なおばあさん”役で出演した中村玉緒(76)が18日、来阪。主役を務めた子役の本田望結ちゃんと65歳差の共演を「ホントに楽しかった。これで望結ちゃんも映画好きになってくれるでしょう」と充実の笑顔を見せた。
9月19日公開の映画『ポプラの秋』(大森研一監督)に“不思議なおばあさん”役で出演した中村玉緒(76)が18日、来阪。主役を務めた子役の本田望結ちゃんと65歳差の共演を「ホントに楽しかった。これで望結ちゃんも映画好きになってくれるでしょう」と充実の笑顔を見せた。 ―――気難しいおばあさん役は普段のイメージとは違いますが、役作りの苦労は?
―――気難しいおばあさん役は普段のイメージとは違いますが、役作りの苦労は? ―――勝新太郎さんが亡くなって20年近くたちます。様々な思いがあると思いますが、一番の思い出は?
―――勝新太郎さんが亡くなって20年近くたちます。様々な思いがあると思いますが、一番の思い出は? ―――映画では「手紙を天国に届けるおばあさん」ですが、私生活で手紙は?
―――映画では「手紙を天国に届けるおばあさん」ですが、私生活で手紙は?
 大好きだった父を突然亡くした8歳の千秋(本田望結)は母(大塚寧々)と2人でポプラの木のあるポプラ荘に引っ越す。そこで会った大家のおばあさん(中村玉緒)は“天国に手紙を届ける”不思議な配達人だった。千秋は死んだ父に伝えたかった溢れる思いを手紙に綴っていく。父に届く、と信じて…。
大好きだった父を突然亡くした8歳の千秋(本田望結)は母(大塚寧々)と2人でポプラの木のあるポプラ荘に引っ越す。そこで会った大家のおばあさん(中村玉緒)は“天国に手紙を届ける”不思議な配達人だった。千秋は死んだ父に伝えたかった溢れる思いを手紙に綴っていく。父に届く、と信じて…。
 高橋伴明監督が『愛の新世界』以来、20年ぶりにエロスに挑んだ野心作。人生の半分を過ぎようとする男たちが経験する、「老い」が「性」に追いつく時間と葛藤を、現実と妄想の狭間で描く。主人公の映画監督・時田に奥田瑛二。時田の人生を狂わせる女子高生・律子にオーディションで選ばれた新人・村上由規乃のほか柄本佑。製作に名を連ねている高橋恵子も特別出演している。
高橋伴明監督が『愛の新世界』以来、20年ぶりにエロスに挑んだ野心作。人生の半分を過ぎようとする男たちが経験する、「老い」が「性」に追いつく時間と葛藤を、現実と妄想の狭間で描く。主人公の映画監督・時田に奥田瑛二。時田の人生を狂わせる女子高生・律子にオーディションで選ばれた新人・村上由規乃のほか柄本佑。製作に名を連ねている高橋恵子も特別出演している。
 ―――この映画は、最近監督が足場にしていた京都造形芸術大学の“北白川派”の作品ではないが、監督の立場は変わったのか?
―――この映画は、最近監督が足場にしていた京都造形芸術大学の“北白川派”の作品ではないが、監督の立場は変わったのか? 『MADE IN JAPAN こらッ』の大西礼芳(あやか)や、山田洋次監督『小さなおうち』の黒木華(はる)。この映画でも、新人・村上由規乃が頑張ってくれた。彼女は入学式の時から注目していた。度胸がよく、テレるということがなかった。奥田瑛二もすっぽんぽんだったからね。
『MADE IN JAPAN こらッ』の大西礼芳(あやか)や、山田洋次監督『小さなおうち』の黒木華(はる)。この映画でも、新人・村上由規乃が頑張ってくれた。彼女は入学式の時から注目していた。度胸がよく、テレるということがなかった。奥田瑛二もすっぽんぽんだったからね。

















 江口:
江口: 本木:
本木: 本木:
本木:







