
~「聞いて下さい」母の訴えが背中を押した、核を選んだ人類の今を辿る旅~




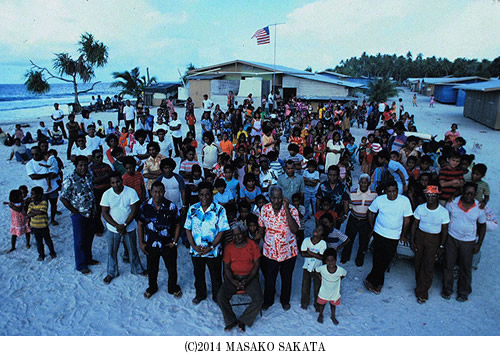





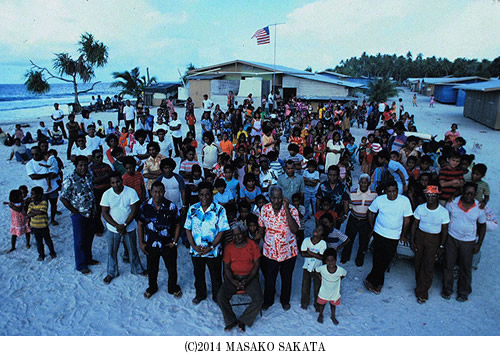






 しっかり者の大島優子主演映画『ロマンス』監督&サプライズゲスト記者会見
しっかり者の大島優子主演映画『ロマンス』監督&サプライズゲスト記者会見
ゲスト:タナダユキ監督、大倉孝二(桜庭洋一役)
・(2015年 日本 1時間37分)
・監督・脚本:タナダユキ
・出演:大島優子、大倉孝二、野嵜好美、窪田正孝、西牟田恵
・2015年8月29日(土)~ヒューマントラストシネマ渋谷、シネ・リーブル梅田、京都シネマ、9月5日(土)~シネ・リーブル神戸 ほか全国順次公開
・公式サイト⇒ http://movie-romance.com/
・コピーライト: (C)2015 東映ビデオ

元AKB48メンバーの大島優子主演映画は、新宿と箱根を往復する特急ロマンスカーに乗務するアテンダント女性の成長物語。ひょんなことから怪しい映画プロデューサーと名乗る男と箱根の名所を巡りながら、それまでの生き方を見つめ直して、前向きな気持ちになっていく。怪しい映画プロデューサー・桜庭を演じた大倉孝二と、母親との関係に悩む実年齢と同じ26歳の鉢子を演じた大島優子との掛け合いが、これまた絶妙で笑える! 大人の男性としてリードしようとする桜庭を全く信頼しない鉢子。ボケとツッコミ漫才の“箱根湯けむり珍道中”を見ているようだが、そこに人生をやり直そうとするふたりの心境の変化を感じとることができる。
【STORY】
 特急ロマンスカーでアテンダントをしている26歳の鉢子(大島優子)は、今日も同棲している彼(窪田正孝)にお小遣いを渡して出勤。ドジな後輩(野嵜好美)の失敗もさり気なくフォローし、テキパキと車内販売の仕事をこなすしっかり者。そんな鉢子が万引をした男・桜庭(大倉孝二)を捕まえたことから、変なオッサンと箱根をめぐる羽目になる。鉢子は、男にだらしない母親と高校卒業以来疎遠になっていた。一方、桜庭は、度重なる資金繰りの不調で妻子にも去られ、借金取りに追われる“人生崖っぷち”状態の映画プロデューサーだった。二人が晩秋の箱根を巡る内に、幼い頃の思い出が甦る鉢子と、不甲斐ない自分と向き合う桜庭。二人とも過去を振り返りながら、それまでの自分と決別して前へ進もうとする。
特急ロマンスカーでアテンダントをしている26歳の鉢子(大島優子)は、今日も同棲している彼(窪田正孝)にお小遣いを渡して出勤。ドジな後輩(野嵜好美)の失敗もさり気なくフォローし、テキパキと車内販売の仕事をこなすしっかり者。そんな鉢子が万引をした男・桜庭(大倉孝二)を捕まえたことから、変なオッサンと箱根をめぐる羽目になる。鉢子は、男にだらしない母親と高校卒業以来疎遠になっていた。一方、桜庭は、度重なる資金繰りの不調で妻子にも去られ、借金取りに追われる“人生崖っぷち”状態の映画プロデューサーだった。二人が晩秋の箱根を巡る内に、幼い頃の思い出が甦る鉢子と、不甲斐ない自分と向き合う桜庭。二人とも過去を振り返りながら、それまでの自分と決別して前へ進もうとする。
8月29日の公開を前に来阪したタナダユキ監督の合同記者会見が行われた。そこに、急遽東京から駆け付けた大倉孝二が飛び入り参加。鉢子の前に突然現れた怪しい男とは違い、ナイーブさを感じさせる色白のスレンダーボディ。思わぬ嬉しいゲストに取材陣も湧き立った。箱根のガイドブックを見ながら脚本を書いたというタナダユキ監督と、大島優子との共演がとても楽しみだったという大倉孝二。作品に込めた思いや撮影秘話などについて、それぞれに語ってもらった。
【大島優子について】
――― 大島優子さんに対するそれまでのイメージや、当て書の部分は?
 監督:子供の頃に憧れていたアイドルのお姉さんという感じでした。とても明るくてキラキラしているけど、どこか憂えを感じさせる。何でもできるけど何でもやらされる、本人にしか分からない大変さもあるんだろうなと思っていました。
監督:子供の頃に憧れていたアイドルのお姉さんという感じでした。とても明るくてキラキラしているけど、どこか憂えを感じさせる。何でもできるけど何でもやらされる、本人にしか分からない大変さもあるんだろうなと思っていました。
当て書の部分は、何でもテキパキとできるところや、足が速いところ、他は想像して書いていました。
大倉:大島さんは、足、マジで速いんで、大変でしたよ、逃げ切るの(笑)
――― 大倉さんは大島優子さんに対して?
大倉:僕は、失礼ながらアイドルということしか知りませんでした。「AKB48」もたまにテレビで見るくらいで、真ん中でとても綺麗な娘が踊っているなという印象しかなかったですね。それが、会ってすぐに「前から知ってる!」みたいな雰囲気になって、普通にダベってました。
監督:ここに大島さんがいたら、多分一番しっかりしていると思います(笑)。
大倉:どこでもそうなのか知らないけど、“アイドル大島優子”を演じているというところは見たことなかったですね。
監督:一番若いスタッフにでも誰に対しても変わらない態度で接していました。
 ――― 最初、大島さんとの共演を聞いた時の感想は?
――― 最初、大島さんとの共演を聞いた時の感想は?
大倉:なんか面白くなりそう!と思いました。
――― 体格も性格も対称的なふたりでしたが、撮影する際に工夫したことは?
監督:工夫というより、限られた時間の中でどれほど自由に動いてもらえるかなと考えました。自由に好き勝手にやってもらえればと。
大倉:本読みでも、10分くらいで「もう終わりです」と監督が言われたので、スタッフが慌てて「いやいやいや」と止めたほどです。「もういいです。後は本番でやって下さい」とね。
――― 車の中の二人の会話が面白かったのですが、緊張した?
大倉:まったく無かったすね。打ち合わせも練習もなかったです。
――― 絶妙な掛け合いに笑わされましたが?
大倉:たまたまですね(笑)。
【脚本と演出について】
――― 「脚本協力」とクレジットされている向井康介さんは、どんな協力だったのですか?
監督:鉢子と映画プロデューサーの二人が箱根へ行って帰ってくるという、大まかなプロットの部分です。それに私が肉付けしていったのです。
――― 映画プロデューサーのモデルはいるの?
監督:特にいないです。私自身がプロデューサーを胡散臭いと思っているので(笑)、未だにどんな仕事をしているのかよく分かっていないのです。いろんな人たちをミックスさせて桜庭という人物像を創り上げました。本当に、監督より個性的な人が多く、そんな人たちといると、自分が常識人だと思えてくるほどです。
 ――― 鉢子と桜庭との出会いのシーンについて?
――― 鉢子と桜庭との出会いのシーンについて?
監督:桜庭にとっては逃げる日だったので、鉢子が捨てた手紙を利用して、映画のプロデューサーらしく自分でストーリーをこしらえて、一緒に「母を探す」行動に出たのです。
大倉:そんな説明初めて聞いた!(笑)
監督:何も考えていない訳ではないんです。説明するのがイヤなんです、野暮に思えるから。
――― 細かな演出はしないんですか?
監督:一切しません。脚本を渡して好きにやってもらった方がいい。
――― 役者としてはやりにくいのでは?
大倉:いろんな監督さんがいらっしゃるので、その人の船に乗ったら従うだけです。説明がなくてもあんまり不安にはならなかったです。監督は言葉にしなくても「それでいいんだ」という顔をしていたので。
――― ラブホテルでのシーンについて?
監督:最初からそういう感じで撮ろうと思っていました。桜庭の中の男性としての欲望とは別に、若い女の子に泣かれてしまい、抱きしめてからの展開は、桜庭の中ではかなり混乱していたであろうと(笑)。
――― 監督からの説明もなく、脚本通りされたのですか?
大倉:理解しようとしても難しいですからね。
監督:あんまり言い過ぎると固まってしまうので、何も言わずに自由にやってもらった方が、新しい発見があるからいいんです。
――― ラストシーンにちょっと疑問を感じたのですが?
監督:最初からそういう構成でした。たまたま出会った鉢子と桜庭ですが、一緒に過ごすうちに、鉢子の母親へのわだかまりを落ち着いて考えられるようになり、最後は鉢子の笑顔で終わらせたいと思っていました。でも、母親を見掛けてすぐに母親を許す気にはなれないと思うので、ちょっと間を置いてからあのようなラストにしました。
――― それが鉢子が成長した姿だったんですね?
監督:そうです。
【鉢子と親子関係について】
――― オリジナル脚本ということですが、主人公・鉢子の26歳という年齢は、タナダ監督にとって曖昧さや不安定感というものがありましたか?
監督:あったと思います。それまで“若い”というだけで許されていたことが段々と許されなくなる。今の年齢から見ればまだまだ若いと思えますが、当時は“若い”とは感じられませんでした。あまりにも一般常識もなく、できないことが多過ぎたり、また母が姉を産んだ年齢なのに自分が母親になるなんて無理だわ、「やばい!」と思ってました。
――― 26歳という年齢的なリミットを感じていたのですか?
監督:リミットは感じていませんでしたが、とても母親になる自信がないという焦りを感じていました。
 ――― 大倉さんは鉢子のような20代半ばの曖昧さとかありましたか?
――― 大倉さんは鉢子のような20代半ばの曖昧さとかありましたか?
大倉:個人的にはフラれたりバイトがダメになったり、周りの人たちが少しずつ映像に出だして「俺はもう諦めなければいけないのかな?」と思ったり、かなり腐った状態でした。でも、26歳~27歳の時が一番大きな転換期だったように思います。野田秀樹さんや三谷幸喜さんの舞台に出させて頂いたり、映画『ピンポン』に出演したりとね。
――― 親と子の関係や子供をうまく育てられなかったという思いが作品の中にあるが、監督もそんな難しさを感じているのですか?
監督:意識している訳ではないけど、「家族ってやっかいだな」と思っている部分はあります。どんなにひどい親でも捨てきれないとか、逆の立場では、私自身親の望み通りの人間に育ってないので、何だか面倒くさいなとかね。
――― 「親だから」といって許してしまうところもあるが?
監督:今回、私は桜庭の年齢に近いのですが、鉢子に対しては、まだ子供ですが親のことが理解できる立場でもあるので、子供だからといって親を責めていい年齢ではないよね、と気付き始めた時の苦しさがあります。桜庭に関しては、親としての不甲斐なさや、子供を嫌いになれないという親の感情を、今の年齢だから入れられたのかなと思います。
【箱根について】
――― 関西の人にはあまりなじみのない箱根ですが、ロケ地について?
 監督:実は私も箱根は初めてだったんです(笑)。都心から1時間ちょっとで行けるので、いつでも行けると思って全然行ったことがなかったんですよ。今回は時間がなかったので、脚本はガイドブック見て書きました(笑)。行ったことのあるプロデューサーに、ここは1日で移動できる距離なのかと聞いてみたり、後はロケハンで決めればいいやというふうに思ったり、自分で脚本書いている強みですね。
監督:実は私も箱根は初めてだったんです(笑)。都心から1時間ちょっとで行けるので、いつでも行けると思って全然行ったことがなかったんですよ。今回は時間がなかったので、脚本はガイドブック見て書きました(笑)。行ったことのあるプロデューサーに、ここは1日で移動できる距離なのかと聞いてみたり、後はロケハンで決めればいいやというふうに思ったり、自分で脚本書いている強みですね。
大倉:ホント、ベタですからね。ガイドブックに載っている所しか出て来ないですからね(笑)。
――― 小田急電鉄からのオファーなのかと思いましたよ?
監督:いえいえ、こちらからお願いしたのです。最初小田急電鉄へ電話した時、たまたま受けて下さった広報の鈴木さんという方の奥様がロマンス号のアテンダントをされていて、「アテンダントに光を当てて下さって嬉しいです」と仰って下さり、撮影が実現しました。小田急さんに断られていたら、今ここで取材を受けることもなかったでしょう。
大倉:箱根はとてもいい所ですよ。
――― 今、火山活動の影響で観光客も減っているようですが?
監督:早く収束してほしいですね。でも、箱根へ行けない間は、この映画で見て箱根を楽しんで頂きたいです。
(河田 真喜子)







 シリーズ最高傑作を引っ提げ、トム・クルーズ来日!
シリーズ最高傑作を引っ提げ、トム・クルーズ来日!
「日本に戻って来られてうれしい!」 ファン700人の熱い歓迎に、トム感激!!
映画史上最高のスパイ、<不可能を可能にする>伝説のスパイ:イーサン・ハントに、史上最難関のミッションが発令される!
全世界で累計21億ドル(約2520億円)を超えるパラマウントピクチャーズの超人気シリーズ『ミッション:インポッシブル』の最新作『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』(日本公開:8月7日(金)。公開に先駆け、トム・クルーズとクリストファー・マッカリー監督が7月31日(金)、プロモーションのため来日致しました。
『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』トム・クルーズ来日空港取材
2015年7月31日(金) 17:50頃 羽田空港 国際線到着ロビーにて
トム・クルーズが、監督のクリストファー・マッカリーとともに、本作のプロモーションのために来日した。トム・クルーズの来日は昨年6月の「オール・ユー・ニード・イズ・キル」以来約1年1か月ぶり、21回目。クリストファー・マッカリー監督はトムと初タッグを組んだ『アウトロー』のプロモーション(2013年1月)以来2度目の来日となる。
羽田空港の到着ロビーでは、多くの報道陣と、女性ファンやファミリーのほか、夏休みということもあり小学生や制服姿の女子高生など幅広い層のファン約700人が到着をいまかいまかと待ちわびた様子だった。「Welcom to Japan」と書かれたお手製のボードを持ったファンやお手製のトム写真入りうちわを持ったファンの姿も。そしてロビーにトムが姿を現した瞬間、あちこちから「トムー!トムー!」の歓声があふれ、まさにトムコール一色に!!トムは真っ先に5歳くらいの女の子のもとへ駆け寄りサインに応じたり、中には「I Love You!! Hug Me!!」と熱烈なラブコールを送る女性ファンもおり、トムも熱いハグで応じるなど感無量の様子だった。そのあとも一人ひとり丁寧にサインや握手、写真撮影に応じたり、時にはファンと会話を交わす場面もあり、黄色い声援が収まらない中、ファンサービスは1時間弱にも及んだ。
ようやくマスコミの前にも姿を現したトムは「日本に戻って来られてうれしい!」とコメント。「サングラスを外してくれる?」とのマスコミからのリクエストには「明日ね!」と笑顔で応えた。
先日ウィーンのオペラハウスで行われたワールドプレミアでは、詰めかけた5,000人以上のファンに向けて約4時間にわたるファンサービスをたっぷりと行ったトム。日本でのキャンペーンはクリストファー・マッカリー監督、製作のブライアン・バークとともに2日の記者会見、3日のプレミアレッドカーペットに出席する予定だ。なお、全米批評家ランキングサイトRotten Tomatoesで97%の高評価(2015年7月28日現在)をたたき出しており、ワールドプレミアでもトムは「シリーズ最高傑作だと自信を持って言える出来だから、きっと皆さんにも楽しんでもらえるはずさ」とコメントしており、自信作を引っ提げてのプロモーションにあたる。親日家のトムだけに、日本のファンに向けて丁寧なファンサービスが期待され、この夏一番熱い1日になることは間違いなさそうだ。
◆『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』ストーリー
 超敏腕スパイ:イーサン・ハント率いるIMFは無国籍スパイ「シンジケート」の暗躍により、またしても解体の窮地に追い込まれてしまう。イーサンはこの最強の敵にどう立ち向かうのか?誰が敵か味方かわからない中、究極の諜報バトルが繰り広げられる。史上最難関のミッションをコンプリートできるのか!?イーサンの究極の「作戦」とは?
超敏腕スパイ:イーサン・ハント率いるIMFは無国籍スパイ「シンジケート」の暗躍により、またしても解体の窮地に追い込まれてしまう。イーサンはこの最強の敵にどう立ち向かうのか?誰が敵か味方かわからない中、究極の諜報バトルが繰り広げられる。史上最難関のミッションをコンプリートできるのか!?イーサンの究極の「作戦」とは?
・公式HP:http://missionimpossiblejp.jp/
・公式Facebook:https://www.facebook.com/missionimpossibleJPN
・公式ツイッター:Twitter:https://twitter.com/MImovie_jp (#mijp)
2015年8月7日(金)より全国ロードショー!
(C)2015 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
(プレスリリースより)
 『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』来日記者会見
『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』来日記者会見
飛行機にぶらさがるのはお勧めしないよ(笑)
トム・クルーズ史上&M:Iシリーズ史上
全米&世界オープニング興収No.1を引っ提げ日本で記者会見
~ノースタントアクション秘話を語る~
日本で語る トム史上もっとも危険な超絶アクション。その舞台裏とは?
全世界で累計約21億ドル(約2,520億円)を超えるパラマウントピクチャーズの大人気シリーズ『ミッション:インポッシブル』の最新作『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』 日本公開:8月7日(金)に先駆けて、7月31日(金)に公開された全米では、初日興収がシリーズ最高の2030万ドル(24億4000万円)で大ヒットスタートを切った! 初日単日としては、『ミッション:インポッシブル』シリーズ史上最高の興収で「M:I-2」(2000年)が記録した1660万ドル(19億9000万円、最終興収2億1500ド万ドル=258億円)の興収を大幅に更新した。一方、海外では20ヶ国以上で公開され、すでに2630万ドル(31億6000万円)大ヒットスタートを切っており、週末の興収は6000万ドル(72億円)と予測され、シリーズのみならず、トム・クルーズ出演作品史上、最大のオープニングとなった国もあり、全世界ではこの週末に約1億1200万ドル(134億4000万円)が見込まれている。
また、公開前には全米批評家サイト「ロッテン・トマト」で驚異の97%、「シネマスコア」でもAの高評価を獲得している。シリーズ最高傑作との呼び声も高い。
そんな世界中で話題沸騰の本作を引っさげ、7月31日におよそ1年1か月ぶりに来日したトム・クルーズの「来日記者会見」の様子を下記にて紹介いたします。
【来日記者会見】
・2015年8月2日(日) ザ・ペニンシュラ東京にて
◆出席者:トム・クルーズ(イーサン・ハント役兼プロデューサー)、クリストファー・マッカリー(監督)

2日(日)、映画『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』の記者会見が東京で行われ、製作・主演のトム・クルーズ、監督のクリストファー・マッカリーが出席した。4000人ものファンが集まったロケ地でもあるオーストリア・ウィーンでのワールドプレミア、1000人のファンでごった返したNYでプレミア、そんな世界中で話題沸騰の本作の記者会見には、テレビカメラ20台、スチールカメラ80台、記者50名、総勢200名のマスコミ陣が会場に詰めかける盛況ぶりで、会場は熱気に包まれた。
あの有名なテーマ曲と共に、記者会見のステージに登場したトム・クルーズ、クリストファー・マッカリー監督は、最新作への自信と意気込みを語った。
「ミッション:インポッシブル」シリーズは、トム・クルーズ演じるIMFの諜報員イーサン・ハントとして、トム自身がノースタントで挑むアクションシーンが常にお茶の間の話題となりスポットライトを浴びるが、最新作でも、観ている方の心拍数が上がり、手に汗握るリアルスタントへの挑戦が注目されている。本作の出来栄えについて監督は、「トムとコラボレーションした5作目の作品で、毎回が学びの現場だったし、我々が学んできたことから生まれた結果に非常に満足している、きっと観客の皆にも分かってもらえる」と自信を見せた。トムも同様に「僕も同感だ。まるで生徒のようにいつも現場で新しいことを学ぶんだ」と語り始めた途端、トムのマイクが垂れ下がり、何度か自身で直そうとするが戻らない状況に!スタッフが直しにかかると、「ほら、こうやって今も新しいこと(マイクの治し方)を学んだよ、(スタッフに向かって)アリガトウ!」とマイクを直したスタッフを気遣いつつ、超大物俳優でありながら、周りへの気配りを忘れないトム自身の人柄を表し、会場を和ませた。そんなハプニングの後、トムは続けて「マッカリー監督本当にたくさんの知識を持っていて、私が今まで知らないこと、例えば軍用機のぶら下がり方などを学んだ。でも皆には、飛行機にぶら下がるのはお勧めしないよ!(笑)」
 その本作の目玉となるアクションシーンの一つは、 "スタント無し"で地上約1500メートルを時速400キロ以上で飛ぶ軍用飛行機のドア外部に張り付き、侵入に挑むという体当たりアクションシーン。そんな不可能を可能にするトムに、「怖いものはありますか?」という質問が投げられ、注目が集まった。「怖さはあまり感じない、そう自分に言い聞かせている」とクールに答えたトムは、軍用機にぶら下がるシーンは監督のアイディアだったと明かした。そのトムのコメントに監督は「あれはジョークのつもりだったんだ」とは慌ててフォロー、逆にトムは「(そのアイディア)いいんじゃない?」と監督のアイディアを気に入ったと、名シーンが生まれた誕生秘話を語った。
その本作の目玉となるアクションシーンの一つは、 "スタント無し"で地上約1500メートルを時速400キロ以上で飛ぶ軍用飛行機のドア外部に張り付き、侵入に挑むという体当たりアクションシーン。そんな不可能を可能にするトムに、「怖いものはありますか?」という質問が投げられ、注目が集まった。「怖さはあまり感じない、そう自分に言い聞かせている」とクールに答えたトムは、軍用機にぶら下がるシーンは監督のアイディアだったと明かした。そのトムのコメントに監督は「あれはジョークのつもりだったんだ」とは慌ててフォロー、逆にトムは「(そのアイディア)いいんじゃない?」と監督のアイディアを気に入ったと、名シーンが生まれた誕生秘話を語った。
 現場でのエピソードとして監督は、「機内でモニターを見ていた後、軍用機に立つトムにコミュニケーションを図ろうとして外に出たが、非常に寒くて、あんな環境で演技をしているトムに驚いた!私は沢山着込んでいたが、それでもものすごく寒かったんだ。それでもトムはスーツ姿だからね!(笑)」と、現場でのエピソードを明かし、CGを排除した"本物のアクション撮影"を強調した。その後、トムは「スーツは着たかったんだ。スーツ姿にこだわったのは、ヒッチコックの『北北西に進路を取れ』のオマージュとしてね」と、常に観客をエンターテインさせようとするプロとしてのこだわりを明かした。
現場でのエピソードとして監督は、「機内でモニターを見ていた後、軍用機に立つトムにコミュニケーションを図ろうとして外に出たが、非常に寒くて、あんな環境で演技をしているトムに驚いた!私は沢山着込んでいたが、それでもものすごく寒かったんだ。それでもトムはスーツ姿だからね!(笑)」と、現場でのエピソードを明かし、CGを排除した"本物のアクション撮影"を強調した。その後、トムは「スーツは着たかったんだ。スーツ姿にこだわったのは、ヒッチコックの『北北西に進路を取れ』のオマージュとしてね」と、常に観客をエンターテインさせようとするプロとしてのこだわりを明かした。
あの名シーンのあまり過酷さに「1000フィート(約300メートル)上がるごとに3度気温が下がるのから極寒の寒さだった。更に、エンジンからの排気ガスが顔にかかって本当に苦しかった!僕はパイロットだからよくわかるんだ。鳥がもしぶつかったりしたら大変なことになるんだ。ぶら下がっているだけじゃなくて、そこで演技もしなくてはならなかったんだ。やっぱりやるんじゃなかったかな・・・」とジョークを飛ばして会場を笑わせた。
そこで更に監督は、「トムはそのシーンの撮影中ずっと叫んでいたんだ。僕はそれがパニックなのか素晴らしい演技なのか分からなかった。トムは『パニックじゃない、これは演技なんだ、カットしないで!と叫んでいたよ。』と明かした。
「今後、日本を舞台にするという考えはありますか?」という質問に、「いいね!道路を遮断させてもらったり、ビルから飛び降りることを許可してくれたらね。でも夏は避けて春か秋かな。」と日本のファンには嬉しいコメントも。
 最後に、「本シリーズが長年続いてきた理由や想いは?」という質問に、トムは「初めてプロデュースした作品だった。映画学校に通ってきたわけではないので映画のあらゆることを現場で学んできた。このシリーズは、いろいろな国を周り、各国の人や文化を知るチャンスを与えてくれた映画で、チャレンジもできる、観客の皆を最大限エンターテインできる作品」と、熱い思いを明かした。監督は「僕の願いが叶った映画です。本シリーズにはルールがあって、不可能なことをイーサン自身はやりたくない、でも絶対不可能なことを毎回やらなくてはいけない状況に持っていく脚本作りは非常に難しいんです。でもいいところは、作品を作る私たち自身も、物語がどこに到達するか分からない。観客と同様毎回がサプライズなんです」と締めくくった。
最後に、「本シリーズが長年続いてきた理由や想いは?」という質問に、トムは「初めてプロデュースした作品だった。映画学校に通ってきたわけではないので映画のあらゆることを現場で学んできた。このシリーズは、いろいろな国を周り、各国の人や文化を知るチャンスを与えてくれた映画で、チャレンジもできる、観客の皆を最大限エンターテインできる作品」と、熱い思いを明かした。監督は「僕の願いが叶った映画です。本シリーズにはルールがあって、不可能なことをイーサン自身はやりたくない、でも絶対不可能なことを毎回やらなくてはいけない状況に持っていく脚本作りは非常に難しいんです。でもいいところは、作品を作る私たち自身も、物語がどこに到達するか分からない。観客と同様毎回がサプライズなんです」と締めくくった。
一流の監督とキャストをチームに加え完成させた自信作「ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション」は8月7日(金)より全国ロードショー。
◆『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』ストーリー
 超敏腕スパイ:イーサン・ハント率いるIMFは無。国籍スパイ「シンジケート」の暗躍により、またしても解体の窮地に追い込まれてしまう。イーサンはこの最強の敵にどう立ち向かうのか?誰が敵か味方かわからない中、究極の諜報バトルが繰り広げられる。史上最難関のミッションをコンプリートできるのか!?イーサンの究極の「作戦」とは?
超敏腕スパイ:イーサン・ハント率いるIMFは無。国籍スパイ「シンジケート」の暗躍により、またしても解体の窮地に追い込まれてしまう。イーサンはこの最強の敵にどう立ち向かうのか?誰が敵か味方かわからない中、究極の諜報バトルが繰り広げられる。史上最難関のミッションをコンプリートできるのか!?イーサンの究極の「作戦」とは?
・公式HP:http://missionimpossiblejp.jp/
・公式Facebook:https://www.facebook.com/missionimpossibleJPN
・公式ツイッター:Twitter:https://twitter.com/MImovie_jp (#mijp)
2015年8月7日(金)より全国ロードショー!
(C)2015 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
(プレスリリースより)
 『シナモンの最初の魔法』インタビュー
『シナモンの最初の魔法』インタビュー
ゲスト:衣笠竜屯監督、白澤康宏(プロデューサー兼、黒葉役)、篠崎雅美(桂役)
・2015年 日本 1時間6分
・監督:衣笠竜屯
・出演:辻岡正人、栗田ゆうき、篠崎雅美、西出 明、松田尚子、白澤康宏、有北 雅彦
・2015年8月1日(土)から7日(金)まで元町映画館にて上映
・公式サイト⇒ http://sweetsmpr.wix.com/cinnamon-cookie
あなたの前にいきなり、可愛い、白いエプロンをつけた少女が現れ、「私はシナモン、クッキーの妖精です。あなたをしあわせにするために、洋菓子のお店からやってきました」と言われたら、あなたはどんな顔をするだろう。
 東京から神戸に出張でやってきた営業サラリーマンの川北龍成。契約は一つもとれず、上司からは、契約がとれなかったら倉庫にとばすと電話がかかる。このところ喧嘩ばかりの婚約者の桂からは、「食べたら幸せになるクッキー」を買ってきてほしいと何度も携帯に催促の電話がかかる。そんな龍成の目前に、いきなりチャーミングな少女シナモンが現れる……。
東京から神戸に出張でやってきた営業サラリーマンの川北龍成。契約は一つもとれず、上司からは、契約がとれなかったら倉庫にとばすと電話がかかる。このところ喧嘩ばかりの婚約者の桂からは、「食べたら幸せになるクッキー」を買ってきてほしいと何度も携帯に催促の電話がかかる。そんな龍成の目前に、いきなりチャーミングな少女シナモンが現れる……。
シナモンは落ちこぼれの見習い妖精。龍成を幸せにするという課題を与えられ、龍成につきまとう。シナモンの先輩の妖精メブキと謎の男、黒葉のほか、お菓子の学校のバニラ先生、妖精の仲間たちと、楽しい人物が登場する。龍成を演じるのは、総合プロデューサーでもある辻岡正人さん。今まで『クローズZERO』などアクションやホラー系の作品への出演が多かったが、本作では、自分で自分につっこむようなひとりごとの多い、人間くさい青年を演じていて、栗田ゆうきさんが演じる、ふわふわしたトリックスターのような、明るいシナモンとの組み合わせは絶妙。二人が、神戸の街を駆けめぐるドタバタ・ファンタジー・ラブコメディー。
 映画は、龍成と桂が、互いの存在のかけがえのなさに気付くことができるかという話であると同時に、シナモンの成長譚でもある。シナモンが、自分の“生きる道”を見つけられるか…。“自分の幸せ”ではなく、自分が好きな人を“本当に幸せにする”ためには、どうあったらいいのか…。シナモンが唱える「お菓子の心得」の言葉が、映画を観終えた時、思いのこもった、あたたかいメッセージとして、あなたの心に届くにちがいない。
映画は、龍成と桂が、互いの存在のかけがえのなさに気付くことができるかという話であると同時に、シナモンの成長譚でもある。シナモンが、自分の“生きる道”を見つけられるか…。“自分の幸せ”ではなく、自分が好きな人を“本当に幸せにする”ためには、どうあったらいいのか…。シナモンが唱える「お菓子の心得」の言葉が、映画を観終えた時、思いのこもった、あたたかいメッセージとして、あなたの心に届くにちがいない。
衣笠竜屯監督と、プロデューサーで黒葉を演じた白澤康宏さん、桂を演じた篠崎雅美さんにお話をうかがいましたので、ご紹介します。
◆お菓子の妖精シナモンについて
―――シナモンが本当に可愛くて、動きも楽しく、目が離せませんでした。シナモンのキャラクターはどのようにつくられたのですか?
 監督:子どもの頃、お手伝いのコメットさんが魔法を使って手伝う『コ メットさん』(1967~68年九重佑三子さん主演、1978~79年大場久美子さん主演)というテレビドラマがあり、学校でしんどいことがあっても、このドラマを観て、いやされたり、『メリー・ポピンズ』(1964年)というファンタジー映画を観て、次からはちょっと頑張ろうと思いました。映画ってそういう機能がありました。映画館に入って、ちょっと現実を忘れ、出た時には軽くなっている…、そういう映画をつくりたい。本作も、現実のつらいことを、ファンタジーとか神話、童話といった異界に助けられる話になっています。
監督:子どもの頃、お手伝いのコメットさんが魔法を使って手伝う『コ メットさん』(1967~68年九重佑三子さん主演、1978~79年大場久美子さん主演)というテレビドラマがあり、学校でしんどいことがあっても、このドラマを観て、いやされたり、『メリー・ポピンズ』(1964年)というファンタジー映画を観て、次からはちょっと頑張ろうと思いました。映画ってそういう機能がありました。映画館に入って、ちょっと現実を忘れ、出た時には軽くなっている…、そういう映画をつくりたい。本作も、現実のつらいことを、ファンタジーとか神話、童話といった異界に助けられる話になっています。
シナモンの脚本段階でのイメージは、繊細で線の弱い少女という設定で、栗田さんのイメージではなかったですが、栗田さんをとおしてキャラがみえて、立ち上がってきたところがあります。シナモンがくるくる回りながら動いていくのは、栗田さんが自分で考えついてやってくれました。大半がアフレコだったのですが、遠くから撮影していて録音できない時でも、何度もウワワ~と声を出してやってくれました。
―――この映画をつくるきっかけは?
監督:私が監督した短篇『バニーカクタスは喋らない』(2012年)では、メブキというしゃべれない女の子が主人公で、サボテンと会話し、サボテンと友達になります。その映画では、メブキは人間という設定でした。辻岡正人さんがこれを観られて、2012年暮れに、辻岡プロダクションから一本つくってほしいとリクエストがあり、2年位かけて脚本を書き、昨年GWの5日間で大半を撮影しました。
◆色彩・特撮について
―――映画の始まり方もおもしろいですね。本が開いて、挿絵がそのまま実景に変わり、カメラがひくと、龍成の姿が映る。
監督:本が開いて、そこから映画が始まると、中に実景があって…というディズニーのような映画が大好きです。本好きの少年で、小学校の図書室に行って、30年くらい前の布張りの本とか探して、引っ張り出すワクワク感が大好きでした。
―――少しぼかしたような映画の色調は?
監督:私の考え方は、今の主流と違っていて、ピントが合ってリアルな色合いでやるという映画が多い中、子どもがクレヨンで描いたような映画があってもいいんじゃないかと思っていまして、そういう雰囲気にしたかったんです。
―――そういうイメージがあるから、UFOが出てきて文字まで出てきて(笑)、あれだけ大胆だと、楽しかったです。
 白澤:あれはいろいろ意見ありましたが、衣笠監督ならではと思います。皆に何やってるのと言われながらも、絶対やらせてと引きませんでした。
白澤:あれはいろいろ意見ありましたが、衣笠監督ならではと思います。皆に何やってるのと言われながらも、絶対やらせてと引きませんでした。
監督:あれも無茶なことで、ないほうが映画としてまともと反対意見もありましたが、『コメットさん』でも、人間が風船の中に入ってしまったり、無茶なことをやっていて、最近そういうのがありません。
嘘というのが分かった上で楽しめるという特撮が、昔はあったと思います。今はCGでリアルに撮影された作品ばかりなので、レイ・ハリーハウゼン(特撮映画の監督)の映画のような、骸骨がガーツと上がってきて戦ったり、どうみても人形を動かしているのだけれど、おもしろい…そういう映画の可能性を追求したいと思いました。お菓子のお店も、小さいミニチュアをつくって映したら、若いスタッフから、監督、本気?と言われました(笑)。
―――シナモンがピョンと跳んで小さくなってミニチュアの家に入ったり、バニラ先生や妖精たちが、お菓子の学校の何かの画面で、シナモンと龍成の様子を見守っていて、賭けをしたり、助け舟を出したり、おもしろかったです。
監督:学校で画面を見ているシーンは、70年代の特撮の、皆で水晶玉に映る映像を眺めているイメージです。石森章太郎の漫画「二級天使」や、フランク・キャプラ監督の『素晴らしき哉、人生!』(1946年)のイメージで、皆で見ている感じを出したかったんです。
◆ファンタジーと現実が混ざり合うおもしろさ、神戸という街について
 ―――ファンタジーの世界に浸っている中で、いきなり黒葉が名刺を出して営業やら、現実の話になって、その対比が楽しかったです。
―――ファンタジーの世界に浸っている中で、いきなり黒葉が名刺を出して営業やら、現実の話になって、その対比が楽しかったです。
白澤:龍成がセールスマンで、持っている営業のチラシも全然ファンタジックではなく、どぎついちらしが映りこんできて、僕も現場でびっくりしました。あんな毒々しいものを売っている青年が、あんなピュアな恋をするというギャップがおもしろかったです。
監督:職業の設定をどうするかという時に、神戸のクッキーなら、東京のマムシドリンクだろう(笑)って感じになりました。
白澤:龍成のキャラと他のキャラクターのギャップがおもしろく、彼が現実のどぎつさみたいなのを引き受けて出てきてるのかなと、つまり人間側の人ということですね。ファンタジックなキャラの中に、一人、生々しい人間が混じっています。
監督: 『メリ-・ポピンズ』、『コメットさん』でも、現実とまるで違う異世界に行って、最後は、必ず現実に、家に戻ってきて、現実の中の問題も解決していて、そういうところが好きです。
ファンタジーって、神様の力というか、異界の力、異界のキャラクターの力を利用するみたいなところがあります。黒葉のクローバー薬局はきっとこれからもずっと続けるでしょうし、あのサボテンも育てるでしょう。そういうファンタジーのあり方があるのではないか。
魔法を使えるお手伝いさんが普通に街にいる世界が成り立ちそうなのが神戸で、ファンタジーと日常との境界があまりないような感覚が子どもの頃からあって、初めから神戸で撮るつもりでした。神戸は、百年位経っている古い家とか、西洋の家とか、子どもの頃から不思議な光景がありました。街を曲がると不思議なお店があって、そこに入ると魔法を売っていて、もう二度と行けないみたいな話があっても、違和感がない街並みが神戸です。
◆テーマについて
―――桂は電話のシーンでしか登場せず、はじめは、わがままで、いい印象を受けませんが、段々変わっていきますね。
監督:自分の心の中に世界を持っている人が、外とどうやってつながっていくか、そういう人同士がどうやってうまくつきあっていくのかを、『バニーカクタスは喋らない』の時からずっと考えていて、本作も、桂が心の中で、婚約者の龍成の愛情を受け取れるかどうかという葛藤の物語です。龍成のことを愛しているけれど、うまくいくか心配で、自分が愛に値するかどうか、相手を信じられるか不安。いわば、結婚する前のマリッジ・ブルーをどう乗り越えるのか。それで愛が壊れることもありますが、心の中に、お菓子の妖精や神様をつくりだして、異世界の力を借りて、不安や迷いを乗り越えて、相手とつながる、そういう物語をずっとやりたかった。
―――シナモンが成長する話でもありますね。
監督:シナモンが龍成に恋をするというのはどうだろうと言って、最初は大反対されましたが、シナモン自身が自分の使命を忘れて、恋敵になってしまうところがおもしろいと思って、スタッフを説得した覚えがあります。
脚本の時に、「お菓子の心得」みたいなのを入れようと言って、1条「人を幸せにすること」、2条、3条と考えてみて、スッタフに「本気?」と苦笑いされたりしましたが、言葉にするとシナモンの気持ちが伝わるかなと思い、やってみました。
◆観客の皆さんに向けて
 監督:今は、上を向いて歩こうとは、気恥ずかしいとか、いまいちリアルじゃないとかで、言えなくなっていて、映画を観てほっとできるような作品は、案外つくろうとされていない気がします。だからこそ、そういう映画をつくりたくなっていると思います。
監督:今は、上を向いて歩こうとは、気恥ずかしいとか、いまいちリアルじゃないとかで、言えなくなっていて、映画を観てほっとできるような作品は、案外つくろうとされていない気がします。だからこそ、そういう映画をつくりたくなっていると思います。
篠崎:何かをつかもうとするには、勇気が要って、手を伸ばさずにやめてしまうことが多いですが、この作品で、スタッフもキャストも頑張って手を伸ばしてみようとした作品です。登場人物が皆幸せになるのを観て、観客の皆さんにも幸せを感じてもらうと同時に、幸せをつかむことを恐れなくていい、そう思ってもらえる力があるかなと思います。
白澤:長い期間をかけて、全員参加で、意見を寄せ合いながらやってきたので、作品は監督のものですが、スタッフ、キャスト一人ひとりの思いがたくさん詰まった映画になりました。キャストにとっても本当に自分の作品だと思えるものになっていて、そこが伝わると嬉しいと思います。
本作は、神戸で1989年から活動している自主制作映画サークル「神戸活動写真倶楽部 港館」による自主制作映画です。撮影予定の5日間のうち、1日雨に降られて、予定どおりの撮影ができなくなり、その日のうちにメブキ役の松田尚子さんの撮影を完了させるため、急遽、屋根があるところで撮れるシーンを即興で考えたそうです。映画をたくさん観て、映画をこよなく愛する人たちが集まり、その力が結集された作品。神戸の街がとても魅力的に撮られており、ぜひシナモンに会ってみてください。
(伊藤 久美子)
