 『この世界の片隅に』片渕須直監督インタビュー
『この世界の片隅に』片渕須直監督インタビュー
■原作:こうの史代(『この世界の片隅に』双葉社刊)
■監督・脚本:片渕須直
■声の出演:のん、細谷佳正、他
■2016年11月12日(土)~テアトル梅田、 イオンシネマ近江八幡、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ茨木、109シネマズ大阪エキスポシティ、シネ・リーブル神戸、MOVIXあまがさき、ほか全国ロードショー
■公式サイト: http://konosekai.jp/
■コピーライト:©こうの史代・双葉社/「この世界の片隅に」製作委員会
★戦火の中、健気なすずの暮らし
こうの史代の原作を片渕須直監督がアニメ映画化した『この世界の片隅に』が完成、公開を前に19日、片渕監督が来阪キャンペーンを行い、作品への思いを語った。
 ――今夏はアニメが活況だった。『この世界の片隅に』も泣けるアニメだが、原作のどこに惹かれたのか?
――今夏はアニメが活況だった。『この世界の片隅に』も泣けるアニメだが、原作のどこに惹かれたのか?
片渕監督:主人公が普通に生活していて、ご飯をつくるところがおもしろく丹念に描かれる。そうした普通の生活と、裏庭から見える軍港に浮かぶ戦艦大和が隣り合わせに存在する。そんな日常生活を営む主人公のすずさんは、多少おっちょこちょいでのどかな若奥さん。やがて、そんな普通の人々の上に爆弾が落ちてくることになって、それでも生活は続いてゆく、という物語なのですが、実は、ご飯を作っているあたりでもう感じ入ってしまいました。
――その時点でこうの史代さん(原作者)に連絡を?
片渕監督:2010年夏に、こうのさんにアニメ化への思いを手紙に書きました。こうのさんのほうでも僕のそれまでの仕事を知っておられて、お互いに影響しあう関係であることが確かめられました。こうのさんは、日常生活の機微を淡々と描く僕の作品のことを、こうした作品を描きたいと思う前途に光るともし火、といってくれました。
でも、『この世界の片隅に』で今回は日常生活の対極に戦争が置かれています。それがかえって毎日の生活を営むことの素晴らしさを浮き上がらせています。アニメがテレビ放送されてから50年経ち、視聴する年齢層も高くなり、興味の内容も幅広くなっている。そうした観客を満足させられるものを作りたかったのです。自分がチャレンジするべき作品だと強く思いました。
 ――戦後71年の今年、公開される意義も大きいと思うが?
――戦後71年の今年、公開される意義も大きいと思うが?
片渕監督:今年の8月16日付け朝日新聞夕刊1面にこの映画の記事が載りました。原爆の日ではなく、終戦の日でもなく、その翌日に載ったことの意味は大きいと思います。戦争は終わっても、人々の毎日の営みは終わらない。生活は続いていきます。映画制作中に東日本大震災が起き、普通の生活が根こそぎひっくり返ってしまう、まるで昭和20年の空襲と同じようなことを経験しました。苦境にあえぐ人々がいれば、また彼らを救おうとする動きもありました。そうした人の心は空襲を受けた当時にもありました。たくさんの資料をリサーチする中で当時の人たちの気持ちがよく分かったんです。
あの時代のことはテレビや映画でいっぱい見ているつもりになっていますが、そうした時代を描く記号になっている女性のモンペだって、戦争中期まではほとんど履かれてないんですね。理由は簡単で、“カッコ悪い”からというのでした。素直に納得できて、あらためて当時の人々の気持ちが実感されてくるととても新鮮な感じがしました。『この世界の片隅に』は、そんなふうに当時の人々の気持ちを、今ここにいる自分たちと地続きなものとして捉え直す物語です。
――監督は当然、戦争体験はない。こうした戦争時代の映画を作るのはなぜ?
 片渕監督:私は昭和35年生まれなので、昭和30年くらいまでならば思い浮かべることが出来る。けれど、その10年前の戦時中の世界とのあいだには断絶があるように感じられた。でも、本来は“陸続き”なんです。ひとつひとつ”理解”の浮島を築いていって、この時代に踏み入り、やがて気持ちの上で陸続きなものとしていってみたい。そんな冒険心がありました。すずさんがその道案内です。
片渕監督:私は昭和35年生まれなので、昭和30年くらいまでならば思い浮かべることが出来る。けれど、その10年前の戦時中の世界とのあいだには断絶があるように感じられた。でも、本来は“陸続き”なんです。ひとつひとつ”理解”の浮島を築いていって、この時代に踏み入り、やがて気持ちの上で陸続きなものとしていってみたい。そんな冒険心がありました。すずさんがその道案内です。
――すずの声はアニメ映画初出演ののんちゃん。「少しボーっとした、健気でかわいい」イメージ通り!ぴったりでしたね?
片渕監督:試写を始めると同時に彼女の評価が高まりましたね。彼女は、収録に先立って“すずの心の奥底にあるものは何ですか?”と問うて来ました。彼女は表面的にも面白く演じ、でもそれだけでなく人物の根底にあるものから理解した上ですずさんを作り上げようとしたのです。
――劇場用アニメは2000年『アリーテ姫』、2009年『マイマイ新子と千年の魔法』以来、3作目だが“やり終えた”感が大きい?
片渕監督:映画とは観ていただいた方の心の中で完成するものだと思っています。本当の満足は映画が多くの方々に届くはずの“これから”ですね。
 ★アニメ映画『この世界の片隅に』
★アニメ映画『この世界の片隅に』
第13回アニメ芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞したこうの史代原作を、片渕須直監督が劇場版映画にした素朴な珠玉のアニメ。「少しボーッとした」かわいいヒロインすずを女優のん(本名 能年玲奈)がアニメ初出演で好演。
1944年(昭和19年)、すず(のん)は18歳で呉にお嫁にくる。世界最大と言われた「戦艦大和」の母港で、すずの夫・北條周作も海軍勤務の文官。夫の両親は優しく、義姉の径子は厳しいがその娘の晴美はおっとりしてかわいい。配給物資が減っていく環境の中、すずは工夫を凝らして食卓を賑わせ、服を作り直し、時には好きな絵を描く。ある日、遊郭に迷いこんだすずは遊女リンと出会い、巡洋艦「青葉」水兵になっていた小学校の同級生・水原哲とも出会う。
苦しいながらも穏やかな暮らしが3月の空襲で破られる。そして、昭和20年の夏。8月6日へのカウントダウンが始まる。広島の隣町の、呉ですずは戦火をどう潜り抜けるのか…。ほのぼのとした穏やかな絵に滲むスリリングな予感が見る者を釘付けにする。
◆片渕須直監督(かたふち・すなお) 1960年8月10日、大阪・枚方市生まれ。
アニメーション監督、脚本家。日大芸術学部映画学科でアニメーション専攻。現国立東京芸術大学大学院講師。在学中に特別講師として来た宮崎駿監督と出会い、1989年宮崎作品『魔女の宅急便』の演出補に。その後、虫プロの劇場用アニメ『うしろの正面だあれ』の画面構成を務めた。1998年『この星の上に』はザグレブ国際アニメーション映画祭入選。1999年アヌシー国際アニメーション映画祭特別上映。2002年『アリーテ姫』東京国際アニメフェア長編部門優秀作品賞。2009年『マイマイ新子と千年の魔法』オタワ国際アニメーション映画祭長編部門入選。
(安永五郎)




























 観客にとって共感できる映画より「共感できない他者」でありたい。
観客にとって共感できる映画より「共感できない他者」でありたい。 ■『歓待』と『淵に立つ』はコインの裏表。
■『歓待』と『淵に立つ』はコインの裏表。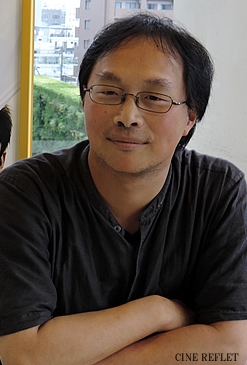 ―――コインの裏表で言えば、両作品に出演している古舘寛治さんも、正反対の役柄です。
―――コインの裏表で言えば、両作品に出演している古舘寛治さんも、正反対の役柄です。





