
若い人たちに挑戦状を叩きつけるような、エネルギッシュでキラキラした映画を作りたかった。
『星くず兄弟の新たな伝説』手塚眞監督インタビュー
1985年にロックンローラー・近田春夫が発表した架空の“ロックミュージカルのサントラ盤アルバム”を手塚眞監督が映画化、伝説の映画として若者に熱狂的な支持を得た『星くず兄弟の伝説』が30年の時を経て甦る。三浦涼介、武田航平ら若手俳優陣に加え、前作も出演した久保田しんご、高木完、ISSAY、更には夏木マリや井上順のベテラン勢も登場するロックミュージカル『星くず兄弟の新たな伝説』が1月20日(土)からテアトル新宿、1月27日(土)からシネ・リーブル梅田、2月17日(土)から元町映画館、出町座他にて全国順次公開される。
スターを夢見て月にやってきたスターダスト・ブラザーズが、ロックの魂を探す旅に出る物語では、ロックの神様に内田裕也、更にはウエスタンパートで浅野忠信も登場。主人公が2度変身を遂げる他、随所にロックなミュージカルシーンを交え、何が起こるか分からないワクワク感が味わえる。とにかくパワフルで音楽が楽しい本作の手塚眞監督に、作品に込めた思いを伺った。

■切実で辛い映画が多い今、楽しくて、豊かで、前向きで、キラキラした映画をやってみたかった。
―――『星くず兄弟の伝説』から32年ぶりとなる本作ですが、映画を作る環境や観客の変化について、感じることは?
手塚監督:30年前はバブルの真っ盛りで、日本全体が上向きであり、色々と豊かなものがあった時代。その中で『星くず兄弟の伝説』を作ったのは、そんな時代を反映する意味合いがありました。当時は若い人のエネルギーを見せることができ、それを企業が後押ししてくれる。そんな夢のような時代だったのです。ところが今は、皆が穏やかに暮らしてはいるけれど、気持ちが保守的で現状維持志向になっています。キラキラした夢など見てはいけないという雰囲気がある。映画も切実だったり、暴力的で辛いものばかり。そんな時代だからこそ逆に、『星くず兄弟の新たな伝説』は必要だと痛切に感じています。楽しくて、豊かで、前向きでキラキラした映画をやってみたかったのです。
もう一つは、今、学生が作った作品を指導する機会も多いのですが、彼らの作品からエネルギーを全く感じない。作り方は上手いのですが、内容が保守的で小さくまとまっており、悪くはないが強いインパクトもない。要は薄味なのです。そういう中で、もう一度僕たちが若い頃にやってきたエネルギーを見せたい。そんな気持ちがありました。
―――こじんまりとまとまるのではなく、もっとハチャメチャにということですね。
手塚監督:若いうちだからこそできる奔放さがあるのではないか。こちらはもう若くないけれど、まだ負けないよと。「できるものなら、これぐらいやってみたら」と、若い人たちに挑戦状を突きつけた気分ですよ。
―――前作に引き続き、今作もロックミュージカルですが、舞台が宇宙なのに驚きました。
手塚監督:30年前に近田春夫さんが「続編にするなら月に行く話」とおっしゃっていたのです。冗談ついでに、さらに次の映画は西部劇ともおっしゃっていたのです。それをずっと覚えていて、今回映画を作るにあたり、そのアイデアがすごくいいなと。本当は別々の映画のつもりだったでしょうが、二本立てのつもりで作ってしまいました。
―――地球から始まり、宇宙もの、西部劇と展開していく物語は楽しいですが、作るにはすごくエネルギーが要りますね。
手塚監督:前作は東京で自分たちが体験している面白さや、こんなことが起きればいいなと思う夢を含めて作りました。昔ご覧になった方は、「東京ってこういう場所なんだと、あの映画で知りました」と感想を寄せてくださいます。当時の若者たちにとって、最も憧れる東京の雰囲気が表現されていたのだと思います。ネット社会ではなかったので、映画で目にした東京のインパクトが大きかった。今は東京の事はリアルタイムで分かるし、地方都市でも東京とさして変わらない。その中で映画を撮るのなら、もう一度自分たちが見たことがないものをみせるしかない。それならいっそのこと、月まで行った方が潔いし、外国の西部劇の時代に戻るのも面白いのではないか。そういうものを自分も見てみたかった。
■若い頃、見たこともない、理解できないものに触れることがとても大事。
―――余談ですがパンフレットで、原案・音楽の近田春夫さんがジューシー・フルーツをプロデュースされていたことを知り、初めて聞いた時の衝撃が甦っていたんです。
手塚監督:若い頃は、見たことがないもの、理解できないものに触れることがとても大事です。僕自身も背伸びをして大人の映画を観に行っていました。例えばフェリーニの映画など、子どもが観ても全く分からない。でもどこか見たこともない世界を見せられているドキドキ感があったのです。50歳を超えて初めてフェリーニ作品が分かったぐらいですから、20代の若者が理解するのは無理でしょうが、それをその年齢で観たことが大事だと思います。普段見慣れていないものでも観てほしいという気持ちがありますね。

■シンプルな映画の対極や、映画の禁じ手をわざと取り入れる。
―――前作の主演から映画初出演の若手まで、幅広い年齢層の俳優陣がキャスティングされていますが、若い人たちにアピールする狙いもあるのでしょうか?
手塚監督:必要な役柄を揃えると必然的にそうなりました。主人公は2人でも、それぞれ3人ずつで演じているので、人数が大幅に増えています。それも皮肉で面白いですね。今は登場人物が3人だけとか、場面もあまり変わらない、とてもシンプルな映画が多いので、その対極をやってみました。
―――三浦涼介、武田航平が演じるスターダスト・ブラザーズの思わぬ変身ぶりは、予想できませんでした。
手塚監督:若くてカッコイイ俳優さんが出てくれるのだから新しい衣装をと思っていたのですが、前作主演で、今回もカン役と衣装を担当してくれた高木完さんが、「絶対前のままがいい!」。実際着てもらうと、前よりカッコよかったです(笑)。音楽もテーマ曲『星くず兄弟の伝説』だけが前のままなのは僕の考えではなく、スタッフからの意見。衣装も音楽も前作のものを継承するアイデアを出してくれて、感謝しています。変身してからが長いですが、映画でやってはいけない“禁じ手”を集めて、わざとやっています。普通ならそっちには行かないという脚本にしていますね。
―――ロックの神様として登場する内田裕也さんの存在感が凄かったですが、オファーの経緯は?
手塚監督:内田裕也さんは「ロックの神様だったら、自分が出ない訳にはいかないね」と、1日だけ空いている日に出演を快諾して下さいました。実際はその日が撮影初日で、いきなり裕也さんのシーンから撮り始めたのです。通常、映画の初日は軽いシーンから始まるのですが、一番濃いシーンから(笑)。スタッフが映ってもお構いなし、複数のカメラで撮影したので、スタッフの方も「この映画はそれでいいんだ」と理解してくれ、かえって良かったですね。
―――CGやセットを使うのではなく、夜空に月ではなく地球が浮かんでいることで宇宙にいることを表現する演出方法も斬新ですね。
手塚監督:僕のイメージの中でオマージュとしてあるのは、2つの映画です。一つはジョルジュ・メリエスの『月世界旅行』。舞台っぽい装置の前にダンサーが出てきて、皆が踊りながら見送ります。するとピストル弾のような形のロケットが月に飛んでいき突き刺さる。そんなサイレント時代のメリエスの世界を今の技術で作りたかった。特別な細工をしなくても、そこが月や未来になるというのは、ジャン=リュック・ゴダールの『アルファヴィル』のオマージュです。パリを架空の「アルファヴィル」という都市に見立てているのに、若い頃すごく衝撃を受けましたね。

■『月世界旅行』のように、百年後観てもいい映画を作りたい。
―――技術面では劣っても、往年の名作から学ぶべき点は、やはり多いのですね。
手塚監督:『月世界旅行』はモノクロで技術も大したことはないけれど、百年以上経った今でも観て楽しい。表現として古びていないのがすごいですね。今回僕が作った映画も百年経って古びていなければいいなと思っています。映画を作る時はいつも、百年後観てもいい映画を作りたいし、今の流行りでは作りたくない。見方によってはすごく古くも、新しくも見える。今回ご覧になった方が、30年後ぐらいにもう一度観ても同じぐらいの気分で観ていられる。まさに前作がそうでした。作った当時は、後々古臭く見えるのではと思いましたが、今観てもそうではないし、若い人が新たに観て、楽しんでもらっているようです。
―――作品中、手塚監督がそのまま登場するシーンが何度かあります。「細かいこと言わなくていいの、映画なんだから」という台詞も面白かったですが、最初から出演を決めていたのですか?
手塚監督:実は自主映画の頃は、しょっちゅう出演していたので、もう一度その頃に戻ってみようと思ったのです。当時は監督をしていても、絵的にはただの学生で監督に見えない。でも、今回は完璧に監督なので、ちゃんと監督として出演できるなと(笑)
学生映画の歴史に必ず名前が出てくる僕の作品『MOMENT』は、ミュージカルではないのに、主役が急に歌い始め、周りからダンサーが出てきて歌い踊るミュージカルシーンがあり、当時とてもウケました。誰もミュージカルシーンなど撮らなかったので、みんな驚くのですが、最後に僕が出ていって言うんです。「みなさん、この映画はミュージカルではないんです。やめましょう!」。ちなみに本作では僕がミュージカルシーンの後に出て行って「OKです!細かいことは気にしない」と言う。セルフパロディーなんですよ。

■70年代イギリスロックミュージカルのイメージや、発想の面白さを参考に。
―――ちなみにどんなミュージカル映画がお好きですか?
手塚監督:一つはロックを使ったミュージカルです。70年代に流行ったイギリスの映画が多いですが、近田さんが熱愛したブライアン・デ・パルマの『ファントム・オブ・パラダイス』や、『ジーザス・クライスト・スーパースター』のように舞台を映画化したものもたくさんありました。でも90年代以降にそれらがパタリとなくなってしまった。もう一つはもっと古い40~50年代のジーン・ケリーらに代表されるハリウッドミュージカル。『ザッツ・エンターテイメント』を観てから、ビデオで昔の映画を見返したのが自分の中で大きな経験になりました。ハリウッドミュージカルは芸の極み。ものすごい芸人を、ものすごい職人がきちんと計算をして撮る。ヨーロッパのロック映画はむしろニュアンスやイメージの飛躍、演出の飛躍が面白いのです。ビートルズ映画などを見ても、彼らは普通のミュージシャンで芝居も達者ではないけれど、その勢いが面白い。普通の映画と違うことをする。ケン・ラッセルの『トミー』もそうですが、少し反体制的なところも含めて、違うイメージを持っていて、その両方とも好きです。今回はロックミュージカル寄りなので、職人的世界よりもイメージや発想の面白さを重視しています。
■インディーズで、幅広い世代が楽しめる作品があってもいい。
―――各キャラクターに合わせた曲や衣装のバリエーションが豊かで楽しい作品ですが、こだわった点は?
手塚監督:長年映画をやってきて思うのは、「観客はいつも若者」。最も一般的な映画は、子どもから大人まで楽しめるという前提がないとつまらない。インディーズ映画と言えば、ことさら若者に向けた作品が増えてしまうので、むしろインディーズなのに幅広い世代が楽しめる作品があってもいいのではないかと思いました。観る人は永遠に若者のつもりですから。この作品も若い人に向けて作ったのに、むしろおじさんが喜んでいるぐらいです。
―――西部劇風シーンで登場する浅野忠信さんは『白痴』以来のタッグですが、久々に一緒に仕事をしての感想は?
手塚監督:僕の監督としての持論は「演技と芝居は違う」。演技というのは心の中から出てくる感情によりするもの。芝居は人に見せるためにするもの。見せ方が違う訳です。浅野さんは若い頃は圧倒的に演技の人で、感情を大事にし、感覚で捕まえてパッとやってしまう。人に見せるための計算はしなかった。一方、夏木マリさんや井上順さんなどのベテランは自分がどう大きく動けば一番伝わるかという芝居が分かっています。浅野さんも今はそういう大きな芝居ができるようになりました。撮影現場では男のスタッフまで見とれるぐらい。昔よりもカッコよくなり、今一番脂が乗っています。根っからのスターですね。
―――最後にこれからご覧になる皆さんに、メッセージをお願いします。
手塚監督:夢をみようというのがこの映画のテーマでもあります。それは世相など関係なく、意識の問題。どんな社会状況でも夢を見ることはできる。それを伝えたいですね。若い皆さんが見慣れない俳優もたくさん出ていますが、勇気をもって観に来てください。
(江口由美)
<作品情報>
『星くず兄弟の新たな伝説』(2016年 日本 2時間8分)
監督:手塚眞
出演:三浦涼介、武田航平、ISSAY、藤谷慶太朗、久保田しんご、高木完、谷村奈南、田野アサミ、ラサール石井、板野友美、野宮真貴、浅野忠信、夏木マリ、井上順、内田裕也
2018年1月20日(土)~テアトル新宿、1月27日(土)~シネ・リーブル梅田、2月17日(土)~元町映画館、出町座他全国順次公開
(C) 2016 星くず兄弟プロジェクト
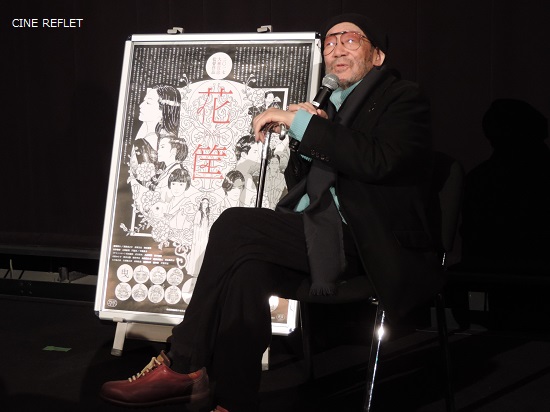













 ■監督の頭の中に全てがある。対応力や応用力が問われる現場。
■監督の頭の中に全てがある。対応力や応用力が問われる現場。
















