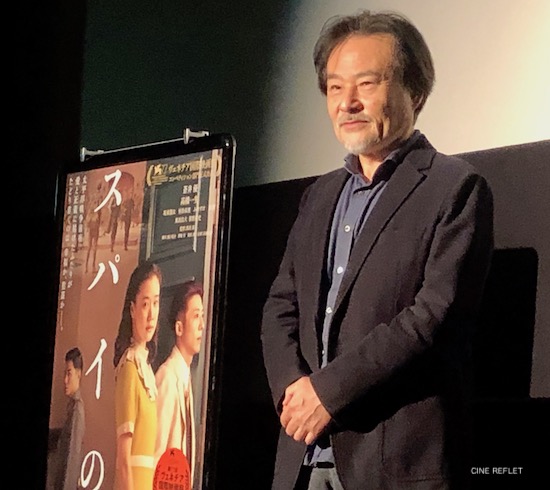稲垣吾郎と二階堂ふみが魅せる、美しくエロティックな「大人の純愛映画」
『ばるぼら』手塚眞監督インタビュー
手塚治虫の作品の中でも禁断の愛とミステリー、芸術とエロス、スキャンダル、オカルティズムなど様々なタブーに挑戦し評価が高い一方、映像化は難しいと言われてきた「ばるぼら」を、長男の手塚眞監督が映画化。昨年の東京国際映画祭コンペティション部門で世界初上映後、世界の映画祭で話題を呼んだ映画『ばるぼら』が11月20日(金)よりシネ・リーブル梅田、シネマート心斎橋、なんばパークスシネマ、京都シネマ、MOVIXあまがさき他全国ロードショーされる。
成功を手に入れたものの、それを失い、堕ちていく作家の美倉洋介を稲垣吾郎が美しく熱演。美倉の運命を狂わせる謎のフーテン女、ばるぼらを演じる二階堂ふみの表情豊かな演技にも魅せられる。撮影にはその映像美で見るものを魅了するクリストファー・ドイルを招聘し、舞台となる新宿の喧騒を印象的に捉えている。美しくエロティックな大人の幻想物語は、リモート生活に慣れつつある今、強烈な余韻を残すことだろう。
本作の手塚眞監督にお話を伺った。
■クリストファー・ドイルにキャスティング前からオファー、企画実現へ強い後押しをしてくれた。
―――手塚監督の代表作『白痴』(公開20周年記念デジタルリマスター版を10月31日よりシネ・ヌーヴォで公開)は巨大なオープンセットで自由にビジュアルを構築していましたが、『ばるぼら』はセットの部分が少ない一方、現代の新宿がまさにセットになっていました。名キャメラマン、クリストファー・ドイルさんが街を切り取ることで、作品に新しい魅力が生まれています。
手塚:この作品は非常にエロティックな映画です。通常日本でエロティックな映画といえば汗臭いとか、泥臭いものになりがちですが、僕は昔のヨーロッパ映画のような品のあるニュアンスを持つ、綺麗なものにしたいと思っていました。それには人間だけでなく街、しかも新宿の隈雑な雰囲気がする場所を綺麗に撮れる人が必要でした。そこで真っ先に思い浮かんだのがドイルさんで、出演者が決まる前にキャメラマンを彼にと決めていました。
―――キャスティング前の段階で、まずはドイルさんにオファーされていたんですね。
手塚:当時、映画会社や色々なプロデューサーに企画をプレゼンテーションしても、『ばるぼら』の実写映画化に対して、みなさん及び腰になっていたんです。「原作は面白いけれど、映画にするのはちょっと難しい」と方々から断られてしまった。さすがに僕もこれは映画化するのは無理かもしれないと気落ちしてきた時に、ドイルさんだけは「絶対俺が撮るから、絶対やろう!」と言ってくれたんです。彼一人が味方についてくれているだけで、僕もこの企画をなんとしてでも実現させようと思えました。
―――ドイルさんの参加が決まったことで、映画会社の風向きも変わったのでは?
手塚:ドイルさんご自身もそのことが分かっていて、一緒にやろうと言ってくれたのだと思います。釜山国際映画祭の映画マーケットに足を運んで、セールスエージェントを見つけは話を聞いていただいていたんです。すると通りがかりのアジアの女性監督が企画書を見て「『ばるぼら』だ!」と。なぜ知っているのかとお聞きするとドイルさんから聞いたというのです。ドイルさんは自分の仲間やアジアの映画人たちに、日本で『ばるぼら』を撮ると宣伝してくれていたようで、それぐらいドイルさんもやりたいと思ってくださっていた。周りからはこだわりが強いという部分で他のキャメラマンを推す声も少なくなかったのですが、僕はドイルさんしか思いつかなかったので、それらの声を振り切りました。

■子どもの頃から好きだった父親の大人向け漫画。現実と非現実を行き来する感覚が面白かった。
―――ちなみに手塚監督が原作漫画の「ばるぼら」を初めて読んだのはいつ頃でしたか?
手塚:父親が連載中に読んでいたので、12歳ぐらいだったと思います。父親が描いた漫画本は家の中に普通に置いてあったので、どれを手にとって読もうが自由だったんです。だから父親が描いていた大人向けの漫画は全部読んでいたし、むしろそちらの方に僕の興味が向いていました。明らかに子どもを意識した漫画は当時あまり興味がなかったのです。
―――芸術とはという問いかけや、根源に深い問題を内在する作品ですが、当時の感想は?
手塚:第一印象は「不思議な話だな」。悩む小説家の描写も出てきますが、幻覚の中に入ったり、どこまでが夢でどこまでが現実かわからないという感覚が面白いと思ったんです。僕はもともと現実と非現実の境界が曖昧であったり、もしくはそこを行き来する物語が好きで、その中で人間が振り回されながらも成長していく姿に興味がありましたから、「ばるぼら」は特に印象に残っていたんですね。
■これまでの自分の作品ともつながる「ばるぼら」、コンパクトな作品にできると思った。
―――映画化を構想したのはいつ頃ですか?
手塚:一般的に手塚治虫の作品を映画化するなら「ブラック・ジャック」や「リボンの騎士」といった有名な作品から始まるのでしょうが、5年前に純粋に次に自分がどんな作品を作りたいかと考えたとき、ふと「ばるぼら」のことを思い出しました。それまで自分が作ってきた映画たちともすんなりと繋がっていく感じがしましたし、内容的にも自分の好きな世界だと思いました。もう一つ思ったのは、『白痴』と比べて非常にコンパクトな作品にできるということ。ストーリー的にもそうだし、登場人物も小説家の美倉と少女ばるぼらに絞り込める。場所も新宿に絞り込めるので作りやすくなります。いつも僕の作品はあれもこれも盛り込み、2時間を超えるのが普通だったので、もっと短くてシンプルな映画を作るのにちょうどいい題材でもあったのです。
―――原作の魔女や黒魔術という要素を、本作ではあまり強調していませんね。
手塚:オカルティックな要素は今まで散々やりましたし、自然に出てしまうでしょうから、むしろそれを抑えめにして、インテリジェンスな表現を心がけました。オカルティックなシーンには日本で一番魔術に詳しい方に監修者として参加していただき、儀式や道具立を検証していただきました。原作では「エコエコアザラク」という正統的な魔術の呪文を使っていますが、別の作家による同名の漫画があるので、映画では実際に儀式で使われている別の呪文を用意していただきましたし、原作にあっても正確ではない要素を外すこともありました。

■稲垣さん、二階堂さんは非常に聡明、何の躊躇もなく演じてくれた。
―――やはり稲垣吾郎さん演じる美倉と二階堂ふみさん演じるばるぼらが素晴らしく、この二人に魅せられました。こだわりのキャスティングだと感じましたが。
手塚:キャスティングは一番大変で、このお二人に決まるまで時間がかかりました。最初から稲垣さん、二階堂さんは候補に上がっていたのですが、企画したのは5年近く前の話ですからそれぞれに事情があり、プレゼンテーションするのが難しかったのです。それから時間が経ち、やはりこの二人しかいないとオファーをしたところ、お二人とも一も二もなく「やります」とおっしゃってくださり、うれしかったですね。稲垣さん、二階堂さんは、脚本を読んで内容を理解したら、あとは演じるだけというスタンスで、非常に難しいシーンやデリケートなシーンも何の躊躇もなく、疑問も抱かず演じてくださいました。素晴らしかったです。
―――インテリでモテ男の美倉はまさに稲垣さんのはまり役ですね。
手塚:芸術家きどりの作家で、インテリでモテる男である美倉と、稲垣さんのパブリックイメージとは重なる部分がありますね。実際にかなりインテリな方なので、美倉役は似合うのではないかと思ったし、そんな美倉がだんだん内面をさらけ出し、ある意味堕ちていく姿を、稲垣さんなら美しく演じることができると思いました。
―――売れっ子作家と呼ばれることへの違和感や真の芸術家を追求するあたりは、稲垣さん自身が歩んできた道にも重なる気がしました。
手塚:稲垣さんの歩まれてきた芸能人性から、そのリアルさが出たのではないでしょうか。稲垣さん、二階堂さん共に非常に聡明で、正しい方向にきちんと演じ、時には僕が思った以上に演じてくださった。クライマックスの場面も二人に任せ、「あそこまでやってくれるんだ」と僕が感心するぐらいの素晴らしい演技をしてくださったので、嬉しかったですね。
■原作からピュアな要素を抜き出し、「純愛を見せつけたかった」
―――稲垣さんが演じた美倉は、原作よりも欲深さをそぎ落とし、ピュアな人物造詣になっていますね。
手塚:原作にもピュアな要素はありますが、今回はあえてそこを抜き出しました。今の時代だからこそ、肉体の触れ合いも含めて、とてもピュアなラブストーリーを作って見せたいと思いましたし、この原作がちょうどそこに当てはまりましたね。今はどうしても相手の裏を詮索したり、どちらかが騙したりという話が多いですが、むしろ純愛を見せつけたいという思いがありました。これは二重の驚きになると感じています。まずは僕が「ばるぼら」を選んだこと、そしてオカルティックな要素があるにも関わらず純愛の映画になっていること。僕の映画をご存知の方にはいい意味で驚きになるのではないでしょうか。
―――二階堂さんが演じたばるぼらも非常に魅力的ですが、どのようにキャラクターを作り上げていったのですか?
手塚:最初は原作とは全然違う現代の格好や、ゴシック要素が強いのでいわゆるゴスロリファッションもいいのではないかと考えていたのですが、衣装の柘植伊佐夫さんと二階堂さんから原作のままでいいのではと逆におっしゃっていただきました。二階堂さんは柘植さんの衣装で『翔んで埼玉』を撮っていた頃だったので、漫画をそのままにするとコスプレっぽくなってしまうのではと危惧したのですが、最初の衣装合わせで二階堂さんが原作の格好にオレンジのかつらを被って、部屋の隅に座っているのを見た時、これでいいと実感しました。撮影では、二階堂さんがご自分の私物衣装を「これもばるぼらっぽいのでは」と持参してくださったんです。映画の中でばるぼらが着用している服の半分は二階堂さんの私服です。有名ブランドの服だけど、フーテンのばるぼらの世界観に溶け込んでいる。二階堂さんの着こなしもあるでしょうし、そのチョイスもばるぼららしさが出ていたんでしょうね。

■クリストファー・ドイルが手持ちカメラで撮った「ばるぼらの表も裏も見せている」シーン。
―――生々しい現実の中を生きる美倉に対し、ばるぼらはテーマ曲にのって新宿の街を彷徨い歩くシーンが登場し、幻想的な美しさがありました。
手塚:今回の撮影はタイトなスケジュールだったのですが、あのシーンは事前にドイルさんに、「ばるぼらを1日あなたに貸すので、好きなように撮ってください。二階堂さんを自由に演出してください」とお伝えして撮っていただいたものです。実際に新宿は撮影できる場所とできない場所があり、結局限られたものしか撮れず、撮影を終了したのですが、解散した時にドイルさんが「ちょっと待って」と言い出したのです。二階堂さんに戻ってきてもらい、「この道を歩いて」と急に道を歩かせ始め、ドイルさんが手持ちカメラでそれを撮り始めた。10分間ぐらい自由に撮ったのですが、その映像が本当に素晴らしかったのです。予定にない映像でしたが、そこから随分使いました。橋本一子さんの音楽にもぴったり合いましたし、そこに稲垣さんが読むヴェルレーヌの詩を重ねると本当に好きな場面になりました。思ってもいなかった場面ですが、一番自分が撮りたかったのはこれなんだという感じです。演出していないのだけど、ばるぼらの表も裏も見せている。映画は時々このような奇跡が起きる。作っていて一番喜びを覚える瞬間ですね。
■肌と肌が触れ合うエクスタシーを純愛に取り込む感覚を忘れてほしくない。
―――『星くず兄弟の新たな伝説』の取材で「百年後観てもいい映画を作りたい」とおっしゃっていましたが、『ばるぼら』もそういうお気持ちで作られたのでしょうか?
手塚:今は男性が草食的だと言われ、肉欲的なものから離れていこうとしています。いい面もあるのですが、やはり肌の触れ合いは純愛の中でも大事な要素です。今の若者たちの純愛は手も握らないとか、精神的なニュアンスだけかもしれないけれど、もっと大人の、肌と肌が触れ合うエクスタシーを純愛に取り込むことをこの映画で感じてほしい。それを意識して作りましたし、そういう感覚を忘れてほしくない。スマホが流行った瞬間から、スマホでしかコミュニケーションを取らない風潮もありますが、僕はそれが自然ではない感じがするし、そんなコミュニケーションはセクシーでもエロティックでもない。エロティックは普段悪い意味で使われがちですが、僕はもっとポジティブに考えていくべきだと思っていますし、こういう時代に一番エロティックな『ばるぼら』を作れて良かったです。
(江口由美)
<作品情報>
『ばるぼら』(2019年 日本・ドイツ・イギリス 100分 R15+)
監督・編集:手塚眞 原作:手塚治虫 撮影監督:クリストファー・ドイル/ 蔡高比
出演:稲垣吾郎 二階堂ふみ 渋川清彦 石橋静河 美波 大谷亮介 片山萌美 ISSAY / 渡辺えり
11月20日(金)よりシネ・リーブル梅田、シネマート心斎橋、なんばパークスシネマ、京都シネマ、MOVIXあまがさき他全国ロードショー
(C)2019『ばるぼら』製作委員会
※11月3日(火・祝)第21回宝塚映画祭(シネ・ピピア)にてプレミア上映