 『楽隊のうさぎ』鈴木卓爾監督、磯田健一郎音楽監督インタビュー
『楽隊のうさぎ』鈴木卓爾監督、磯田健一郎音楽監督インタビュー
(2013年 日本 1時間37分)
監督:鈴木卓爾 プロデューサー・監督補:越川道夫
音楽監督:磯田健一郎
原作:中沢けい『楽隊のうさぎ』新潮文庫刊
出演:川崎航星、宮崎将、井浦新、鈴木砂羽、山田真歩他
2013年12月14日(土)~ユーロスペース、新宿武蔵野館、12月29日(土)~第七藝術劇場、シネ・ヌーヴォ、2014年1月11日(土)~京都みなみ会館、2月8日(土)~神戸アートビレッジセンター他全国順次公開
公式サイト⇒http://www.u-picc.com/gakutai/
(C) 2013『楽隊のうさぎ』製作委員会
~日々生徒たちと接しているところでしか台本も音楽も生まれてこない。
生徒たちとの「キャッチボール」から生まれた青春音楽映画~
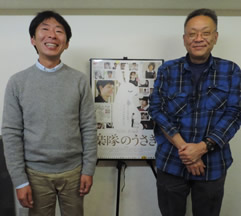 瑞々しい中学生たちが奏でる吹奏楽部の演奏は、決して完璧ではないけれど、心を打つ「音楽の力」がみなぎっている。中沢けいの人気小説『楽隊のうさぎ』を『ゲゲゲの女房』の鈴木卓爾監督が映画化。楽器の街、静岡県浜松市を舞台に、吹奏楽部員を一般の中・高校生からオーディションで募集し、映画のために一から作り上げられた花の木中吹奏楽部と、主人公克久の成長ぶりが、寄り添うような映像で綴られている。
瑞々しい中学生たちが奏でる吹奏楽部の演奏は、決して完璧ではないけれど、心を打つ「音楽の力」がみなぎっている。中沢けいの人気小説『楽隊のうさぎ』を『ゲゲゲの女房』の鈴木卓爾監督が映画化。楽器の街、静岡県浜松市を舞台に、吹奏楽部員を一般の中・高校生からオーディションで募集し、映画のために一から作り上げられた花の木中吹奏楽部と、主人公克久の成長ぶりが、寄り添うような映像で綴られている。
主人公克久を吹奏楽部へと誘ううさぎ役に山田真歩、花の木中吹奏楽部顧問の和田勉役に宮崎将が扮し、ファンタスティックに、時には在りし日のゆったりとした吹奏楽部の雰囲気を醸し出しながら生徒たちに音の楽しさを伝えていく場面も微笑ましい。また、クライマックスの定期演奏会演奏曲『Flowering TREE』(オリジナル曲)をはじめ、克久が吹奏楽部を意識するきっかけになった勧誘演奏に『星条旗よ永遠なれ』、新入部員が入ったばかりで初見演奏させられた『ファランドール』、克久がコンクールメンバー落ちしたときの演奏曲『吹奏楽のための第一組曲』など、劇中の音楽シーンはすべて実際に部員たちが演奏した生音が使用されており、音楽映画として台詞同様彼らが奏でる音にも注目したい。
鈴木卓爾監督と音楽指導やオリジナル曲作曲を担当した磯田健一郎音楽監督に、青春音楽映画を実際の学生を集めて作り上げたプロセスや、意識したこと、音楽指導でのこだわりやオリジナル曲誕生秘話について話を伺った。
■試行錯誤を重ねた生徒たちとの撮影、音楽指導
 ───今回は主役を含む中学生のキャストを全員オーディションで選び、一から花の木中学校吹奏楽部を作り上げました。今までの映画作りと違う点や、苦労した点は?
───今回は主役を含む中学生のキャストを全員オーディションで選び、一から花の木中学校吹奏楽部を作り上げました。今までの映画作りと違う点や、苦労した点は?
鈴木:今回の映画は、「浜松で映画を作りたい」という持ちかけがあったことから始まりました。吹奏楽部の物語なので、出演者はプロの俳優ではなくむしろ普段学校に通って、家で家族と暮らしている素人の学生さんたちに出演してもらえないかと考えました。プロの俳優さんは台本の流れを掴んで演技をしていきますが、10代の人たちが主人公の物語の場合、今しか映りようのない彼らという生々しいものを物語に入れたかったのです。しかし僕自身吹奏楽部の経験がなく、本作の重要な一面である音楽映画をどうやって作っていけばいいのか全くしらないままスタートしたので、彼らの生々しいものを、しかもアフレコではなく彼らが出した音を使いたいということがどれだけ大変かということを知りませんでした。生々しいものを撮るために、彼らにそこに居てもらうためにはどのように会話したり、監督として演出しなければいけないのか。その問題に突き当たりながら、スタッフみんなで作りました。
───磯田さんは、音楽監督として生徒たちの音楽指導や、オリジナルの楽曲も作られたそうですね。
磯田:オーディションで僕たちが選んだ子ども達は特に吹奏楽の経験は問わず、「『楽隊のうさぎ』に出演したい人は来てください」という条件で応募してくれた人の中から選んでいます。学年も経験もバラバラで、楽器の経験のない子もいました。最初の夏の撮影では普通の映画のアプローチを行っていました。しかし、実際に演奏をしている姿やしゃべっている顔、出ている音を使いたい。僕たちの実際目の前にいるイキイキとした子ども達を映像に撮りたいと越川プロデューサーに言われ、改めて夏の間撮影したラッシュを見ると、子どもたちが窮屈そうに見えて、僕たちが撮りたいものではないことに気づきました。そこで最初あった脚本は一度忘れて、一からやり直しました。
■原作とは違う展開を考えた理由と、映画版ならではの吹奏楽顧問「勉ちゃん」の造詣
 ───花の木中吹奏楽部を一から作るようなものだったのでしょうか?
───花の木中吹奏楽部を一から作るようなものだったのでしょうか?
磯田:どこにてもある普通の吹奏楽部を作る、もしくはそれに近付くようにやろうとしたのですが、8月の撮影ではまだ人間関係ができていませんでした。これではダメだと脚本が書きなおされる一方で、僕はオリジナル曲を書こうと思ったのです。原作では吹奏楽コンクールで全国大会に行く話になっていますが、それはやめました。震災の後に、子どもたちが他の子ども達に勝って喜び、自分たちは特別だと思うような物語を果たして紡いでいいのかという問題意識があったのです。普通の子ども達同士の有り様を撮ることは最初の撮影時点でも固まっていました。また吹奏楽部の顧問、森勉先生(以降勉ちゃん)の造詣も原作ではコンクールに一直線の猛烈型でしたが、映画ではひっくり返しています。
 ───吹奏楽部の熱血教師のイメージとは一線を画した、ふわりとした印象の勉ちゃんのキャラクターはユニークでしたね。
───吹奏楽部の熱血教師のイメージとは一線を画した、ふわりとした印象の勉ちゃんのキャラクターはユニークでしたね。
磯田:勉ちゃんは音楽が好きで、吹奏楽がずっと好きだったけど、一度やめてずっとチェロを弾いていた。学校の吹奏楽部の顧問になり、子どもたちが演奏しているのを見ている中で、また自分も子ども達の中に入りたくなるといった造詣にどんどんとしていきました。
鈴木:宮崎さんには磯田さんが子ども達と一緒に音楽室でやっているのを見てもらっていました。
磯田:宮崎さんは最初から必ず音楽室にいるんですよ。職員室でのシーンなどの出番が終わると、必ず音楽室にやってきて、ピアノの前で座っていました。誰も頼んでいないのに、ずっとその場にいたのです。
───練習をずっと宮崎さんがご覧になっていたということは、磯田さんが勉ちゃんのように指導されていたのかもしれませんね。
磯田:「僕自身が勉ちゃんだったらどうするだろうか」と思いながら、生徒たちの合奏やパート練習をやりはじめました。僕も吹奏楽の経験者として言いたいことや伝えたいことがいっぱいあったのですが、だんだんそれはどうでもよくなり、まずは音と戯れ、一緒に音楽で遊ぶということをやろうと思ったのです。学生時代指揮者だった経験を思い出しながら、「後はやってね」という風に生徒たちに投げかけました。すると、合奏の時に「チューバが音出てない!」と生徒たちが文句を言い始めたり、食事の時間になれば仲良しグループができて遊び始めるということがリアルに起こり始めました。学年や音楽キャリアを超えて本当に彼らが花の木中学校吹奏楽部になるのを感じながら、僕はオリジナル曲を脚本でいう「あて書き」していきました。
■生徒たちの生の言葉や練習の様子を台詞、オリジナル曲にフィードバック
 ───ティンパニーのドンという音から始まる曲はなかなかありません。「あて書き」とおっしゃった意味がよく分かります。
───ティンパニーのドンという音から始まる曲はなかなかありません。「あて書き」とおっしゃった意味がよく分かります。
磯田:最初に克久君の「ドン」というティンパニーの音を書くと、その後に何がくるかといえばファンファーレしかないのでトランペットや他のパーカッションを演奏する子の様子を想像しながら書いていきます。それを全部設計しながら練習するので、「こいつうまくなったな、ちょっと譜面変えて難しいことをさせてみよう」など、練習の様子を譜面にどんどんフィードバックさせていきました。同時に練習中生徒たちにさせた中から生まれた生の言葉を、シナリオにもフィードバックしていきました。こちらから投げたボールに対して、どう返すか。そういうキャッチボールを生徒たちと一緒にやるわけです。
───具体的にどういうやり方で生徒たちの生の言葉をフィードバックしていったのですか?
鈴木:コンクール出場メンバーから落ちて、廊下で落ち込む同級生に、「バーカ、がんばれ!」と同学年の女の子が声をかけていくシーンがありますが、台本の稽古ではなく、ワークショップのような形で投げかけた中から生まれました。「コンクールメンバー落ちして廊下に立っているよ。一人ずつ、声かけられるかどうかやってみようか」というシチュエーションだったのですが、越川プロデューサーから「触ることはやらないで」と言われて、悩んだ後に「バーカ、がんばれ!」という言葉が出た時はプロデューサーも涙目でした。冬のワークショップで出たその言葉を台本に入れ、翌年のゴールデンウィークの本番で使いました。
磯田: 「僕らはこういう方向で作りたいのだけどやってみて」と生徒たちに投げてみて、返ってきたことを拾い上げて、また投げ返す。それを全て撮ったのがこの映画です。僕の仕事で言えば、音楽シーンの演出だけでなく、吹奏楽部を作っていく中で、その奥にドラマがあるわけです。練習の前でふざけているときと、カメラが回り始めた時と同じテンションができなかったら、この映画はダメだということを僕たちは夏の撮影で学びました。どうやったら具体的に撮れるのか常に模索していましたね。
鈴木:自然さのある撮り方を考えたら、盗み撮りすることもできたでしょうが、それは意味ありません。僕らの前に、ちゃんと吹奏楽部があることが目標としてあり、日々接しているところでしか台本も何も生まれてこなかったのです。まさに生徒たちとのキャッチボールの応酬です。全体練習で集まれる限られた濃密な時間に、リハーサルも意識させない形で行っていました。僕が一番キャッチボールが下手だったので、他の皆さんに救ってもらって形にしていきました。
 ───主役に選ばれた川崎航星君は映画初主演ですが、役作りや撮影での様子はいかがでしたか?
───主役に選ばれた川崎航星君は映画初主演ですが、役作りや撮影での様子はいかがでしたか?
鈴木:川崎君は、最初にオーディションで会ったときに克久にすごく重なる部分があって、自己主張はしないけれど、透明感があって、人の話やしぐさを見ていたんですね。満場一致で決まったのですが、最初に花の木中吹奏楽部で集まった時に「僕はどの役をすればいいですか?」と聞かれ、克久役と告げると主役ということでショックを受けていました。プレッシャーを感じていたのでしょうが、ご飯の時間などみんなと仲良くなっていくうちに、わざとふざけて皆を笑わせるようなキャラクターで、彼の笑顔がとても良かったんです。そんないい笑顔をする子が克久のような役をしようとするには、川崎君なりに演じているわけですよね。相当自覚的に自分を追い込んで、関係性を忘れないようにしながら、休憩時間にどれだけ弾けられるか。そんな調整を自分の中でしていたんじゃないでしょうか。
磯田:川崎君は音楽経験はなかったですが、独特の集中力がありました。今回彼にはリアルな吹奏楽感を出すために、僕が教えるのではなく、先輩役の子に教えてもらうようにしました。彼は元々持っているビートは正しくて、僕は1年半一緒にやってきた中で「おまえ、リズム感いいんだぞ。自覚してないだろ?」とだけ伝えて、後は指導は彼女たちに任せていました。定期演奏会の本番でティンパニーを叩くシーンの前に、こういう持ち方をすればいいというのだけは、プロのティンパニー奏者の指導を入れましたが、それ以外は全部自分で練習していましたね。演奏会のシーンは最後の撮影でしたが、日頃は表情を崩さない川崎君が滝のようにワーンと泣いて、相当自分を追い込んでやっていたんだと思います。
■『ベルリン 天使の詩』の天使のような、どこにでも偏在している「うさぎ」の存在
───この物語で山田真歩さん演じるうさぎの存在は、ファンタジーの要素を加える一方、主人公克久を音楽室に誘う重要な役割をはたしています。このうさぎに込めた想いやうさぎで表現しようとしたことは?
鈴木:原作小説に出てくるうさぎは、克久が公園で最初に見かけ、これから行く中学校が嫌だなと思っている克久の中に住み込んでいるような内なる存在でした。映画化するにあたって、ファンタジーは僕の映画的な嗜好として好きな場面でもあるので、俳優が演じ、音楽室の空間に同時に存在してほしかったのです。しかし、ファンタジーの枠組みの一方で、生々しいやりとりをしていかなければ、生徒たちを撮れないことに気付いたとき、うさぎの意味をきちんと捉えていかないと、子どもたちがきちんと映らなくなる危機を迎えました。越川プロデューサーに「『ベルリン 天使の詩』で、天使は人が思っていることをずっと寄り添って聞いている。あちこちにいる天使の一人がうさぎと重なるのかもしれないね」と言われハッとしました。克久自身にしか見えないという本作の枠組みはあるけれど、ティンパニーを教えてくれている園子先輩もひょっとしたら1年生のときに見えたかもしれない。どこにでも偏在している、一人一人を見守っている存在ではないかと、撮影後半に入って見つけていった感じです。克久にしか見えていないようなうさぎが、定期演奏会の前、誰もいない音楽室で、一人一人の椅子を触っていき、「うさぎが皆にもきっといるのだ」と暗示しています。うさぎ役の山田真歩さんは監督からも明確な指示もない中で、自分で動きを全部考え、現場でうさぎを完成させてくれました。
───最後に、これからご覧になるみなさんに一言お願いします。
鈴木:僕たちはこの映画という日常じゃないものを、普段学校に通っている子どもたちを集めて一緒に映画に参加した時間を共有しながら撮らせてもらうという形にしました。その中で彼らが森先生とやっている音楽は、世界中にそこだけのものです。また先生と彼らの音楽や、彼らの笑顔や彼らの時間というのは、彼らだけにある特別なものだと思うのです。そこでやっているものの中から特別なものをふと感じられる映画として、みなさんと出会えたらとてもうれしいと思います。
磯田:僕たちが子どもたちと一緒に過ごした時間が定着されていて、イキイキとした何かをご覧いただけたら、それが一番うれしいです。
(江口 由美)


