
 『千年の愉楽』舞台挨拶
『千年の愉楽』舞台挨拶
(2012年 日本 1時間58分)
監督:若松孝二
出演:寺島しのぶ、佐野史郎、高良健吾、高岡蒼佑、染谷将太、山本太郎、井浦新
2013年3月9日(土)~テアトル新宿、テアトル梅田、第七藝術劇場、京都シネマ、シネ・リーブル神戸にて公開
公式サイト⇒ http://www.wakamatsukoji.org/sennennoyuraku/
(C)若松プロダクション

若松孝二監督の遺作となった中上健次原作の映画「千年の愉楽」(若松プロ)が14日、京阪神の劇場で特別に先行上映され、主演カルテットの高良健吾、高岡蒼佑、井浦新、佐野史郎が神戸、京都、大阪・梅田、十三の4劇場をPR行脚した。いずれも大入り満員の盛況で、質疑応答もある舞台挨拶はさながら若松監督の追悼集会のようだった。
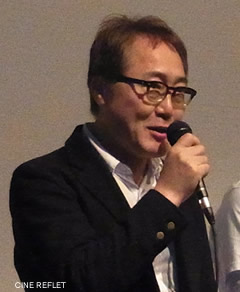 ―――若松監督の思い出は多いと思うが?
―――若松監督の思い出は多いと思うが?
佐野:監督とは舞台の状況劇場からのお付き合いで、32年ぐらい仕事させてもらった恩師。「千年の愉楽」やろう、と言ってもらってうれしかった。監督の内なるメッセージが感じられる。その中にいられるのがしあわせでした。
監督とはよく飲んで、3時ごろまで話したこともあった。(テオ・)アンゲロプロス(監督)の話になって、若松監督は反逆とか政治的な面で語られるけど、映像詩人なんだと思った。監督は亡くなったけれども、今までの作品の中にいらっしゃるし、監督が教えてくれたことを伝えていきたい。
高良:僕の役、半蔵が死ぬシーンはたまたま雨で中止になり、11月11日に撮ることになった。この日は偶然にも僕の誕生日でした。死ぬ役は役とはいってもつらくて引きずったりするけど、誕生日だから死の方から生きることを感じることが出来た。生まれては死んでいく、そういう物語の感覚になれました。
 高岡:ちょうどこのお話もらった時、世間をお騒がせしてましたが、そんな時、監督に話したら「そんなもの、人生のちょっとした1ページだよ。オレなんか公安に目付けられちゃって、入れない国もあるんだよ。まあ大丈夫だよ」と言われて、この人、すごいなあと思った。監督に安心して任せることが出来ました。どこかで生き続けてて見てくださってると思います。
高岡:ちょうどこのお話もらった時、世間をお騒がせしてましたが、そんな時、監督に話したら「そんなもの、人生のちょっとした1ページだよ。オレなんか公安に目付けられちゃって、入れない国もあるんだよ。まあ大丈夫だよ」と言われて、この人、すごいなあと思った。監督に安心して任せることが出来ました。どこかで生き続けてて見てくださってると思います。
井浦:私は冒頭で死んでしまう彦之助の役ですが、大変、ということではないけどホームレスの人が実際に生活しているところで撮りました。撮影が終わってスタッフが撤収作業に入ってる時も監督だけはじっとたたずんでいて、すべて終わった後、住人の皆さんに感謝の気持ちを伝えていた。これが若松さんだ、と惚れ込んでてしまうところですね。権力やシステムを嫌う監督だけど、人間の本質を知ってる、筋を通す人だと…。
今回も、全国の単館系の人々との付き合いを大事にするという監督の思いからこんなことが出来たと思う。
何にも分からない素人の自分に一から教えてもらい、息子のように可愛がってもらった。今は何も考えないようにしている。だけど、この映画を上映出来て、映画館がある限り、新作はこれが最後だけれど、若松監督の映画は続いて行きます。
 ―――若松監督の撮影現場で大変だったことは?
―――若松監督の撮影現場で大変だったことは?
佐野:僕たちよりも、急な階段での撮影が多く、片肺の監督が大変だったと思う。いつもテストなしで「ハイ、本番」なんだけど、ファーストカットでいきなり本番撮影だったのはさすがに初めてでびっくりした。それぐらいかな。
高良:終わってみると大変なことも全部コミコミで、あー楽しかったな、と。若松組は「段取りがない」と聞いていた。これまでにも「自由にしていい」という組もあったけど、けっこう自由じゃない組もあった。だけどこの組はホントに自由だった。デカい安心感があった。正味4日間の出番だったけど、楽しかった思い出しかない。
 高岡:ファーストシーンからラブシーンで、そこが大変だった。いきなりみんなの前でお尻を出して、から始まって、メイクさんたちにも全部見られたことで心が解放された。撮影見たことない人が見に来ていて、70歳ぐらいのおばあちゃんが日に日に化粧濃くなっていくのが凄かった。
高岡:ファーストシーンからラブシーンで、そこが大変だった。いきなりみんなの前でお尻を出して、から始まって、メイクさんたちにも全部見られたことで心が解放された。撮影見たことない人が見に来ていて、70歳ぐらいのおばあちゃんが日に日に化粧濃くなっていくのが凄かった。
井浦:「千年の愉楽」の前に佐野さんとテレビの番組やっていて、その後だったので、どういう顔して佐野さんと会うのか、後ろめたい気持ちがあった。それが一番大変だったけど、その分、佐野さんとも気持ち良く飛べた。「楽しかった」それしかないですね。
― ――監督は「愛ある罵声」で知られてますが、今回の罵声は?
――監督は「愛ある罵声」で知られてますが、今回の罵声は?
佐野:直接はなかったけど、お経詠むシーンでは、何詠んだらいいか、先に聞いていた。時間かかって、そこにエネルギー使って紀州弁の習練が足りなかった。そんなに(紀州弁が)ないから、と思っていたのに、現場行ったら井浦が思いっきり紀州弁で「こいつ裏切りやがったな」と思った。 監督から「佐野ちゃん、ナマけてたんじゃないの。お経はいいけど」とチクリと言われて、それがズシリときた。
 井浦:この作品ではあんまり“罵声”浴びなかったですね。比較的静かな現場だった。監督が怒りをぶつけた「連赤」(実録連合赤軍 あさま山荘への道程)の時はまともに怒っていて、朝起きたらけんか、怒られるたびにこちらも怒りが燃えたぎってきて、現場行くときに「監督とけんかしに行くぞ」と気合い入れて、その怒りを芝居にぶつける、それが映画のエネルギーになってたと思う。
井浦:この作品ではあんまり“罵声”浴びなかったですね。比較的静かな現場だった。監督が怒りをぶつけた「連赤」(実録連合赤軍 あさま山荘への道程)の時はまともに怒っていて、朝起きたらけんか、怒られるたびにこちらも怒りが燃えたぎってきて、現場行くときに「監督とけんかしに行くぞ」と気合い入れて、その怒りを芝居にぶつける、それが映画のエネルギーになってたと思う。
でも、現場が終わると普通に和やかに会話して、酒飲んで何にも後に残さない。お釈迦様の手のひらの上で遊ばせてもらってたんでしょうね。
監督は怒る人を決めていた。「連赤」の時は、大西信満で、ちゃんと(罵声に)耐えられるかどうか、先に調べている。僕もどなられたけど、大西は凄かった。「~三島由紀夫」の時は満島真之介が怒られ役だった。でも、怒鳴ることで全体をピリッと引き締めていたと思う。
 佐野:「連赤」などに比べると「千年」の現場は静かで監督もずっと穏やかだった。だけど、スタッフにはいつものように厳しかった。この撮影では一度、照明さんが怒られた。「漫然と(光を)当ててるんじゃねえ」と。それは役者にも同じで、監督は照明さんに「何を映したいんだ」と言いながら、役者にも「お前は何をどうやりたいんだ」と問いかけているんだ、と思った。
佐野:「連赤」などに比べると「千年」の現場は静かで監督もずっと穏やかだった。だけど、スタッフにはいつものように厳しかった。この撮影では一度、照明さんが怒られた。「漫然と(光を)当ててるんじゃねえ」と。それは役者にも同じで、監督は照明さんに「何を映したいんだ」と言いながら、役者にも「お前は何をどうやりたいんだ」と問いかけているんだ、と思った。
(安永 五郎)


