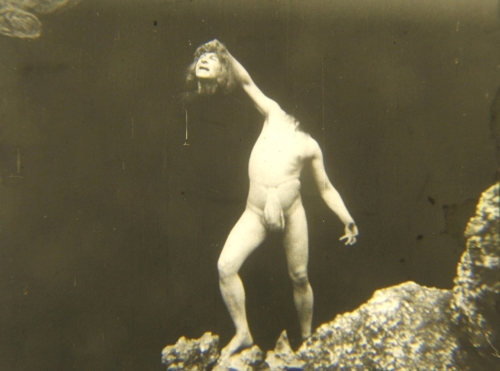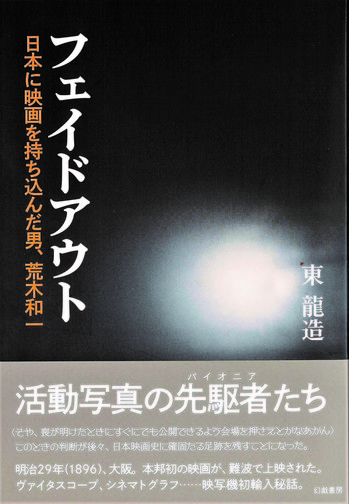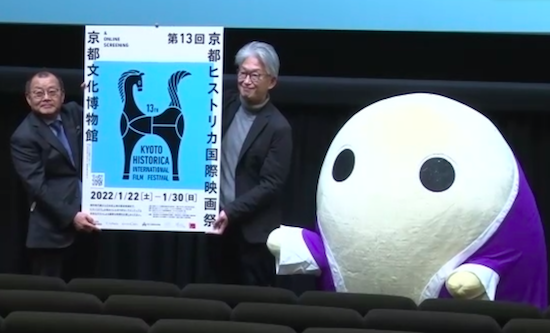『プレゼントラフター』プレスシート(マスコミ向け非売品)プレゼント!
(ブロードウェイ版の演出家、モリッツ・フォン・スチュエルプナゲル氏の貴重なインタビューが掲載されています。)
◆提供:松竹
◆プレゼント数:3 名様
◆締め切り:2022年3月11日(金)
◆公式HP: https://broadwaycinema.jp/
2022年3月11日 (金)~なんばパークスシネマ、MOVIX京都、神戸国際松竹にて全国公開
“お相手の本音、おしえますー。”
ブロードウェイが熱狂した恋愛アカデミー!?
ケヴィン・クライン、トニー賞 演劇主演男優賞受賞作品!
人間は、いくつになっても恋をする。役者魂、ここにあり。
アカデミー賞&トニー賞をW受賞したキング・オブ・アクターであるケヴィン・クラインが主演し、第71回トニー賞演劇主演男優賞を受賞した記念すべき作品であり、英国の劇作家・俳優・音楽家として大成功を収めたノエル・カワードが、“ミドルエイジの危機と悲哀”に陥った大人気喜劇俳優の姿を描いた極上のコメディがブロードウェイシネマとして登場!
大ヒット映画『アベンジャーズ』シリーズのマリア・ヒル役を演じ、本作がブロードウェイ・デビュー作となるコビー・スマルダーズにもぜひご注目ください。
【STORY】
舞台はイギリスのロンドン、1900年代前半。ギャリーはミドルエイジの大人気喜劇役者。腐れ縁の(元?)妻、自分の事を親よりも知っている秘書、恋仲の女流作家と、ギャリーに好意を持つ男性作家に若い女性―。今日も個性的な面々に囲まれながら、本心を言い出せないギャリー。
果たして、ギャリーは最後まで“プレゼント・ラフター(今の笑い)”を演じきることが出来るのか!?
【キャスト/制作】
ノエル・カワード 作『プレゼント・ラフター』
出演:ケヴィン・クライン、ケイト・バートン、クリスティン・ニールセン、コビー・スマルダーズ
装置デザイン:デビッド・ジン
衣装デザイン:スーザン・ヒルファーティ
照明デザイン:ジャスティン・タウンセンド
音響デザイン:フィッツ・パットン
ブロードウェイ版制作:ジョーダン・ロスほか
映画版制作:スチュワート・ F・レーンほか
エグゼクティブ・プロデューサー:スチュワート・ F・レーンほか
ブロードウェイ版演出:モリッツ・フォン・スチュエルプナゲル
シネマ版監督:デヴィッド・ホーン
配給:松竹 ©BroadwayHD/松竹
〈米国/2017/ビスタサイズ/136分/5.1ch〉 日本語字幕スーパー版
公式HP: https://broadwaycinema.jp/
2022年3月11日 (金)~なんばパークスシネマ、MOVIX京都、神戸国際松竹にて全国公開
(オフィシャル・リリースより)
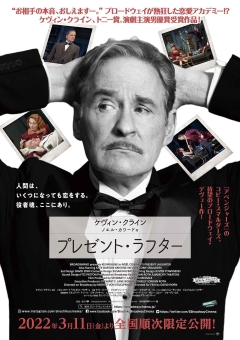










 愛する家族がある日突然、愛情の分だけでっかくなっちゃった!?
愛する家族がある日突然、愛情の分だけでっかくなっちゃった!?