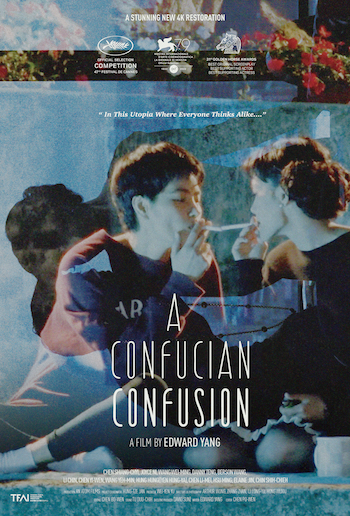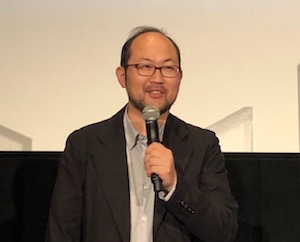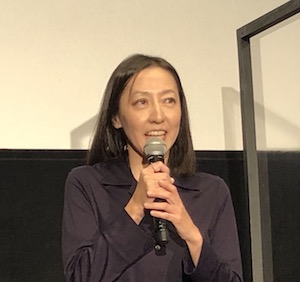10月28日(月)に日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区で開幕したアジア最大級の映画の祭典である第37回東京国際映画祭が、11月6日(水)に閉幕を迎え、TOHOシネマズ 日比谷スクリーン12にてクロージングセレモニーと東京日比谷ミッドタウンLEXUS MEETS...にて受賞者記者会見を行いました。
セレモニーでは、各部門における審査委員からの受賞作品の発表・授与。主演男優賞(長塚京三)と最優秀監督賞(吉田大八)、【東京グランプリ/東京都知事賞】に吉田大八監督の『敵』が選出され3冠を達成し、審査委員長トニー・レオンよりトロフィーを授与されました。日本映画がグランプリに輝くのは第18回の根岸吉太郎監督作『雪に願うこと』以来19年ぶりの快挙となります(当時の名称は東京サクラグランプリ)。また、長塚京三さんは東京国際映画祭主演男優賞の最高齢(79歳)となりました。その他、主演女優賞は『トラフィック』のアナマリア・ヴァルトロメイが、審査員特別賞は『アディオス・アミーゴ』が、最優秀芸術貢献賞は『わが友アンドレ』が、そして観客賞は『小さな私』がそれぞれ受賞致しました。
小池百合子東京都知事に代わり東京都副知事 松本明子より麒麟像の授与を行い、最後に安藤チェアマンによる閉会宣言により第37回東京国際映画祭は閉幕。
<第37回東京国際映画祭 クロージングセレモニー実施概要>
■開催日:2024年11月6日(水)17:00-18:30
■会場:TOHO シネマズ日比谷 スクリーン 12
■登壇者 :各賞の受賞者:(別途、下記リストにてご確認ください)
アジアの未来部門 審査委員:ニア・ディナタ、山下宏洋、横浜聡子
コンペティション部門国際審査委員長:トニー・レオン
コンペティション部門国際審査委員: エニェディ・イルディコー、橋本愛、キアラ・マストロヤンニ、ジョニー・トー
クロージング作品『マルチェロ・ミオ』:キアラ・マストロヤンニ
ゲスト:東京都副知事 松本明子
安藤裕康チェアマン
MC:仲谷亜希子 ※敬称略
<受賞者記者会見>
■開催日:2024年11月6日(水)18:45-20:10
■会場:LEXUS MEETS...
■登壇者 :コンペティション作品各賞の受賞者
(吉田大八監督、長塚京三、ヤン・リーナー監督、イン・ルー(プロデューサー)、ドン・ズージェン監督、リウ・ハオラン、テオドラ・アナ・ミハイ監督、イバン・D・ガオナ監督、エミネ・ユルドゥルム監督)
第37回東京国際映画祭 各賞受賞作品・受賞者
★コンペティション部門
東京グランプリ/東京都知事賞 『敵』(日本)
審査員特別賞 『アディオス・アミーゴ』(コロンビア)
最優秀監督賞 吉田大八監督(『敵』、日本)
最優秀女優賞 アナマリア・ヴァルトロメイ(『トラフィック』、ルーマニア/ベルギー/オランダ)
最優秀男優賞 長塚京三(『敵』、日本)
最優秀芸術貢献賞 『わが友アンドレ』(中国)
観客賞 『小さな私』(中国)
アジアの未来 作品賞 『昼のアポロン 夜のアテネ』(トルコ)
東京国際映画祭 エシカル・フィルム賞 『ダホメ』(ベナン/セネガル/フランス)
黒澤明賞 三宅唱、フー・ティエンユー
特別功労賞 タル・ベーラ
第37回東京国際映画祭 動員数 <速報値・6日は見込み動員数>
■上映動員数/上映作品本数:61,576人/208本 *10日間
(第36回:74,841人、82.3%/219本、95.0% *10日間)
■上映本作品における女性監督の比率(男女共同監督作品含む):21.9%
(208本中37本、同じ監督による作品は作品の本数に関わらず1人としてカウント)
■その他リアルイベント動員数:96,866人
■ゲスト登壇イベント本数:178件 (昨年169件、105.3%)
■海外ゲスト数:2,561人(昨年2,000人、128.1%)
■共催提携企画動員数:約 44,700人
★クロージングセレモニー
<アジアの未来>
作品賞受賞 『昼のアポロン 夜のアテネ』 エミネ・ユルドゥルム(監督) コメント
東京国際映画祭でこのような賞をいただけて、とても光栄です。審査員の皆様、観客の皆様、そしてこの作品の制作に関わったスタッフに感謝を伝えたいです。
<コンペティション>
観客賞受賞 『小さな私』 ヤン・リーナー(監督) コメント:
この映画の持つ物語が最終的に皆さんの心に刺さることがあればいいなと思います。皆さんの映画に対する愛に感謝します。この作品は障害を持つ青年の成長を描いた作品ですが、主人公は普通の人間です。映画の製作に関わったすべてのクリエイターに感謝したいです。
最優秀芸術貢献賞受賞 エニェディ・イルディゴー 講評:
現実を強烈な内なる風景へと変える、大胆なビジョンを見せてくれました。
最優秀芸術貢献賞受賞 『わが友アンドレ』 ドン・ズージェン(監督) コメント:
この場を借りてこの作品に関わったスタッフの皆さんに心から感謝を申し上げたい。この映画は私のデビュー作ですが、周りの友人たちとともに作り上げました。劇中に大雪の場面があったと思いますが、私の心の中の悩みや暗い気持ちを覆ってしまうような気がしていましたが、雪はいつか溶けて太陽があらわれる。希望に満ちているんです。これからも努力していい映画を作っていきたい。
最優秀男優賞受賞 トニー・レオン 講評:
スクリーンに登場したその瞬間から、その深みと迫真性で私たちを魅了しました。
最優秀男優賞受賞 『敵』 長塚京三(俳優) コメント:
ちょっとビックリして、まごまごしています。『敵』という映画は、年を取って一人ぼっちで助けもない。そして敵に閉じ込められるという内容で。でもこういう場に立たせてもらい、結構味方もいるんじゃないかと気を強く持ちました。ボチボチ、引退かなと思っていたので、奥さんはガッカリするでしょうけど、もう少し、この世界でやってみようかな。東京国際映画祭、ありがとう。味方でいてくれた皆さん、ありがとう。
<クロージング作品>
キアラ・マストロヤンニ コメント:
35年ぶりの日本で、東京での10日間は素晴らしい経験でした。また来ることが出来て嬉しいです。審査委員同士、全く異なる背景の私たちでしたが、色々な感情を共有することができましたし、映画祭でなければ出会えなかった作品や人々に出会えて、映画祭を通して様々な発見ができて良かったです。『マルチェロ・ミオ』について初めて聞いたときは奇妙な映画と思い一つの賭けでしたが、興味を持ち何か異なるもの新しいものを体験することは大事だと思いました。大切な人を亡くしたことがある方は共感できる映画だと思います。真面目でシリアスな作品ではなく、ハッピーな作品です。楽しんでいただければと思います。
安藤裕康チェアマン コメント:
例年に劣らず、盛況の内に終わりを迎えることができました。沢山のゲストを迎え入れることができ、去年より2割の増加となっています。東京国際映画祭での日本映画の受賞は2005年の第18回以来、19年ぶりです。この受賞が、日本映画がますます発展していくきっかけになればと思います。
名称:第 37 回東京国際映画祭
開催期間:2024 年 10 月 28 日(月)~11 月 6 日(水)
会場:日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区
(オフィシャル・レポートより)