
| 原題 | 原題:Vlny(英題:Waves) |
|---|---|
| 制作年・国 | 2024年 チェコ、スロバキア/チェコ語 |
| 上映時間 | 2時間11分 PG-12 |
| 監督 | 監督・脚本:イジー・マードル 撮影:マルティン・ジアラン |
| 出演 | ヴォイチェフ・ヴォドホツキー、スタニスラフ・マイエル、タチアナ・パウホーフォヴァー、オンドレイ・ストゥプカ |
| 公開日、上映劇場 | 2025年12月12日(金)~ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、テアトル梅田、シネ・リーブル神戸、アップリンク京都、2026年1月23日(金)~宝塚シネ・ピピア ほか全国順次公開 |
| 受賞歴 | ☆チェコ・アカデミー賞(チェコライオン賞)7冠(作品賞、監督賞、助演女優賞、助演男優賞、脚本賞、音響賞、観客賞)☆スロバキア・アカデミー賞(Sun in the Net Awards)9冠(作品賞、監督賞、主演男優賞、脚本賞、撮影賞、編集賞、音響賞、衣装賞、視覚効果賞)☆ カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭 観客賞受賞! |
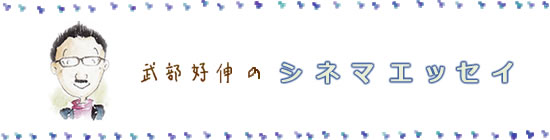
~最後まで命がけで真実を伝えたジャーナリスト魂~
今から57年前の1968年(昭和43年)、世界は大きく動いていました。ベトナム反戦運動の高まり、公民権運動を率いたキング牧師の暗殺、パリ五月革命、中国の文化大革命、日本では学生運動の激化……。ぼくはしかし、まだ中学2年生で、海外の情勢には疎かったのですが、当時チェコスロバキアの「プラハの春」は強く心に刻まれました。
 というのは、メキシコ五輪の女子体操で金メダルを取った、同国のチャスラフスカ選手がソ連への抗議の意志を示した姿がすごく印象に残ったからです。のちに、その理由がソ連主導のワルシャワ条約機構軍が武力で〈民主化〉を封じ込めたことだと知り、他国の事ながら激しい怒りを覚えました。以降、「プラハの春」という言葉がぼくの脳裏から離れなくなったのです。
というのは、メキシコ五輪の女子体操で金メダルを取った、同国のチャスラフスカ選手がソ連への抗議の意志を示した姿がすごく印象に残ったからです。のちに、その理由がソ連主導のワルシャワ条約機構軍が武力で〈民主化〉を封じ込めたことだと知り、他国の事ながら激しい怒りを覚えました。以降、「プラハの春」という言葉がぼくの脳裏から離れなくなったのです。
本作は、邦題からしてもろに「プラハの春」をラジオ報道から見据えた映画です。戦後、東側陣営に組み入れられたチェコスロバキアでは共産党の一党独裁政権下、言論や思想、報道の自由が制限され、西側の情報(ビートルズなどの音楽も!)は御法度という、ひじょうに息苦しい時代が続いていました。それはこの国だけではなく、東欧諸国のすべてがそうでした。
 ところが、チェコスロバキアでは1967年の秋、学生運動に端を発して自由化を求める機運がにわかに高まり、翌年、共産党の重鎮でありながら、リベラルなアレクサンデル・ドゥプチェクが同党の第一書記に就任後(のちに大統領も)、検閲の廃止や海外情報の受け入れなどが実現し、一気に自由な空気に包まれました。それが「人間の顔をした社会主義」と呼ばれる「プラハの春」です。
ところが、チェコスロバキアでは1967年の秋、学生運動に端を発して自由化を求める機運がにわかに高まり、翌年、共産党の重鎮でありながら、リベラルなアレクサンデル・ドゥプチェクが同党の第一書記に就任後(のちに大統領も)、検閲の廃止や海外情報の受け入れなどが実現し、一気に自由な空気に包まれました。それが「人間の顔をした社会主義」と呼ばれる「プラハの春」です。
映画の中で、そこに至るまでのプロセスが詳しく描かれていましたが、まずは冒頭の説明文に引き込まれました。「スターリンのソ連に服従し……。130万人の政治犯、5800人の処刑、そして厳しい報道規制。そんな中、最大の報道機関がラジオだった」。すでにテレビが普及していたのに、ラジオなんですね。確かに地震や紛争などの非常事態時にはテレビよりもラジオに頼るケースが大きいですが。
 主人公のトマーシュは報道記者ではなく、技術職の青年。両親を亡くしているので、親代わりに弟パーヤの世話をしています。学生運動にのめり込むこの弟が政府に睨まれており、時々、役人が自宅に素行調査にやって来ます。当時はそんなんだったんですね。ホンマにイヤな時代や。映画ではこうした閉塞感のある陰鬱な雰囲気を余すことなくあぶり出しています。
主人公のトマーシュは報道記者ではなく、技術職の青年。両親を亡くしているので、親代わりに弟パーヤの世話をしています。学生運動にのめり込むこの弟が政府に睨まれており、時々、役人が自宅に素行調査にやって来ます。当時はそんなんだったんですね。ホンマにイヤな時代や。映画ではこうした閉塞感のある陰鬱な雰囲気を余すことなくあぶり出しています。
トマーシュは弟とは真逆で、保守的というか、国の言いなりになっています。そんな彼が勤務する中央通信局の幹部の指示で、国営放送の国際報道部へ転職させられます。実はそのウラには何やら画策があるのですが、ここでは明かしません(笑)。
 国際報道部はミラン・ヴァイナーというカリスマ的な部長の下、スタッフが自由な空気を謳歌するがごとく仕事に励んでいます。アメリカのヒット曲『ビー・マイ・ベイビー』など禁止されている音楽を平然と流しており、かなりリベラル色に染まっています。しかし、「プラハの春」以前は、国際報道とは名ばかりで、モスクワと東欧の情報しか放送できなかったのです。
国際報道部はミラン・ヴァイナーというカリスマ的な部長の下、スタッフが自由な空気を謳歌するがごとく仕事に励んでいます。アメリカのヒット曲『ビー・マイ・ベイビー』など禁止されている音楽を平然と流しており、かなりリベラル色に染まっています。しかし、「プラハの春」以前は、国際報道とは名ばかりで、モスクワと東欧の情報しか放送できなかったのです。
映画はトマーシュの目を通してラジオ報道の動きをつぶさに追っていきます。しかもリアルに! もう少し取材現場を再現してほしかったのですが、あの頃の東欧のメディア環境が手に取るようにわかりました。ちなみに、トマーシュは架空の人物で、他の登場人物はすべて実在した人らしいです。
 「プラハの春」の実現にもラジオが一役買っていたんですね。ソ連の息のかかった情報がいかにフェイクだらけであるかを暴き、さらに強権的なノヴォトニー大統領を失脚に追い込んだ大スクープを放ったのですから。徹底したウラ取りと直当たりの取材は、ジャーナリズムの根幹です。
「プラハの春」の実現にもラジオが一役買っていたんですね。ソ連の息のかかった情報がいかにフェイクだらけであるかを暴き、さらに強権的なノヴォトニー大統領を失脚に追い込んだ大スクープを放ったのですから。徹底したウラ取りと直当たりの取材は、ジャーナリズムの根幹です。
自由を渇望していた国民が「プラハの春」に酔いしれていたのも束の間、1968年の8月20日、突然、ワルシャワ条約機構軍が国境を越えてきます。ソ連の声明は「チェコスロバキアからファシストを追い出すための国際的支援」。そんなアホな。今のロシアの大統領もウクライナに対して同じ事を言うてますね。どっちがファシストや、ホンマに。プンプン!!
 さぁ、ここからが映画のハイライト。国際報道部はソ連の声明を否定し、「明らかに侵略行為です。国民の皆さんは落ち着いて対処しましょう」と呼びかけます。そのうち戦車と兵士がプラハに迫り、抗う民間人への発砲が始まります。国営放送局の前では群衆が「我々に自由を!」「合法政府を支持する!」と叫び続ける中、武装した兵士が建物の中へ突入。その様子を逐次、スタッフが放送するのです。
さぁ、ここからが映画のハイライト。国際報道部はソ連の声明を否定し、「明らかに侵略行為です。国民の皆さんは落ち着いて対処しましょう」と呼びかけます。そのうち戦車と兵士がプラハに迫り、抗う民間人への発砲が始まります。国営放送局の前では群衆が「我々に自由を!」「合法政府を支持する!」と叫び続ける中、武装した兵士が建物の中へ突入。その様子を逐次、スタッフが放送するのです。
手に汗を握る展開で、緊迫感が半端ではありません。イジー・マードル監督は、俳優のベン・アフレックが演出したアメリカ映画『アルゴ』(2012年)を参考にしたそうです。1979年、イランのアメリカ大使館人質事件を題材にしたスリリングな作品です。本作も負けじとダイナミック、かつ臨場感満点に活写しています。最後の最後までマイクに向かって「実況中継」していたのだから、すごい!
 やがて機器が壊され、放送が中断されるも、想定外の方法でオンエアが続きます。ここでトマーシュがキーパーソンになりますが、これ以上は言えません(笑)。 命をかけて真実を報じる。まさに不屈のラジオ報道ですね。そこに真のジャーナリスト魂を見ました。
やがて機器が壊され、放送が中断されるも、想定外の方法でオンエアが続きます。ここでトマーシュがキーパーソンになりますが、これ以上は言えません(笑)。 命をかけて真実を報じる。まさに不屈のラジオ報道ですね。そこに真のジャーナリスト魂を見ました。
この辺りは、マッカーシズム(赤狩り)が吹き荒れる1950年代のアメリカで、その欺瞞性を暴いたラジオのキャスター、エド・マローの物語『グッドナイト&グッドラック』(2005年)からインスピレーションを得たと監督が言っています。この映画も俳優のジョージ・クルーニーがメガホンを手にしていましたね。
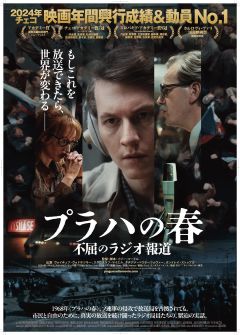 「プラハの春」はわずか半年で終焉を迎え、次に自由を獲得するのが21年後の1989年、「ビロード革命」でした。その間、国内に留まったジャーナリストは迫害を受け続けたそうです。それゆえ、この最後の言葉には目頭が熱くなりました。「勇気ある全ての記者に捧げる。我々はあなたの味方です」。
「プラハの春」はわずか半年で終焉を迎え、次に自由を獲得するのが21年後の1989年、「ビロード革命」でした。その間、国内に留まったジャーナリストは迫害を受け続けたそうです。それゆえ、この最後の言葉には目頭が熱くなりました。「勇気ある全ての記者に捧げる。我々はあなたの味方です」。
昨今、既存メディアの記者がバッシングを受けるケースが多く、元新聞記者のぼくは胸を痛めています。だからこそ、本作はひときわ輝いて見えました。SNSの情報に依存している人にこそ観てもらいたい映画です。
武部 好伸(作家・エッセイスト)
公式サイト: https://pragueradiomovie.com/
配給:アット エンタテインメント
© Dawson films, Wandal production, Český rozhlas, Česká televize, RTVS - Rozhlas a televizia Slovenska, Barrandov Studio, innogy


