
| 制作年・国 | 2025年 日本 |
|---|---|
| 上映時間 | 2時間55分 PG12 |
| 原作 | 「国宝」吉田修一著(朝日文庫/朝日新聞出版刊) |
| 監督 | 監督:李相日(『フラガール』『怒り』) 脚本:奥寺佐渡子 撮影:ソフィアン・エル・ファニ |
| 出演 | 吉沢亮 横浜流星/高畑充希 寺島しのぶ 森七菜 三浦貴大 見上愛 黒川想矢 越山敬達 永瀬正敏 嶋田久作 宮澤エマ 中村鴈治郎/田中泯 渡辺謙 |
| 公開日、上映劇場 | 2025年6月6日(金)~全国東宝系にて公開 |
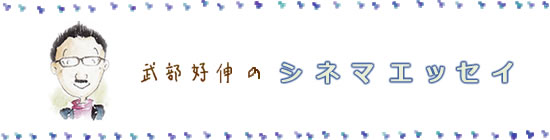
~梨園の「光と影」に翻弄された歌舞伎役者の一代記~

これ、今年の邦画ベストワンになるかも――。試写で本作を観終わったとき、正直、そう思いました。作品の質がずば抜けていたから。つまり演出、演技、脚本(ストーリー展開)、作風のすべてにおいて申し分ないということです。
正真正銘、歌舞伎を題材にした芸道映画です。このジャンルの映画なら、溝口健二監督の名作『残菊物語』(1939年)を越える作品はないとずっと思っていましたが、『国宝』があっさり抜いちゃいました。それほどまでにぼくの心に響きました。
歌舞伎界のことを梨園と言いますが、この世界は基本、血筋を何よりも重んじる世襲制がベースになっています。実際、具体例を挙げるまでもなくそうですよね。その華やかな梨園の裏側でどんなせめぎ合いが行われ、役者がどうもがいているのか、そういう実像はなかなか表に出てきません。本作はしかし、「才能か血筋」という本質をズバリ、突いています。

主人公の喜久雄は、長崎で任侠の親分を父に持つ少年です。抗争で父親が殺され、大阪を拠点にする上方歌舞伎の人気役者、花井半二郎の元に引き取られます。冒頭、宴席の余興で女形で舞う喜久雄の華麗な姿に半二郎が魅入られたからです。女形は「おやま」とも言われますが、映画の中では「おんながた」で通されていました。
 歌舞伎役者としての才能を発揮した喜久雄はめきめき上達し、半二郎の目にかなっていきます。とはいえ所詮は部屋子(見習いの幹部候補生)なので、たとえ才能があっても、「半二郎」の名跡を受け継ぐことができません。半二郎には喜久雄と同い年の俊介という息子がおり、間違いなく彼が跡を継ぎます。それが梨園のルールです。
歌舞伎役者としての才能を発揮した喜久雄はめきめき上達し、半二郎の目にかなっていきます。とはいえ所詮は部屋子(見習いの幹部候補生)なので、たとえ才能があっても、「半二郎」の名跡を受け継ぐことができません。半二郎には喜久雄と同い年の俊介という息子がおり、間違いなく彼が跡を継ぎます。それが梨園のルールです。
 映画は、この2人の友情とライバル心を軸に展開していきます。半二郎から見ても、いや彼ら自身でも、明らかに俊介よりも喜久雄の方が実力が上とわかっています。だからこそ確執、羨望、憎悪の感情が芽生え、文句なくドラマになるのでしょう。
映画は、この2人の友情とライバル心を軸に展開していきます。半二郎から見ても、いや彼ら自身でも、明らかに俊介よりも喜久雄の方が実力が上とわかっています。だからこそ確執、羨望、憎悪の感情が芽生え、文句なくドラマになるのでしょう。
「日本一の歌舞伎役者になるため、悪魔に魂を売ったんや」、「おまえ(俊介のこと)の血を飲み干したいわ」……、喜久雄が大阪弁で吐露するセリフの数々がぼくの胸に突き刺さりました。2人から聞こえてくる強烈な摩擦音。それが映画に通底しています。
 原作は吉田修一の同名小説。それを名匠・李相日(リ・サンイル)監督が極上の芸道映画に仕上げてくれました。2人のペアリングは、『悪人』(2010年)、『怒り』(2016年)に次いで3回目です。クローズアップの多用、妖艶な映像美、メリハリのある内容……と李監督の映画化への意気込みとこだわりが随所に見られました。しかもすべてホンモノ志向!
原作は吉田修一の同名小説。それを名匠・李相日(リ・サンイル)監督が極上の芸道映画に仕上げてくれました。2人のペアリングは、『悪人』(2010年)、『怒り』(2016年)に次いで3回目です。クローズアップの多用、妖艶な映像美、メリハリのある内容……と李監督の映画化への意気込みとこだわりが随所に見られました。しかもすべてホンモノ志向!
本作が何よりも素晴らしいのはキャスティングです。主演の吉沢亮が歌舞伎役者になり切り、見事な至芸を披露してくれました。美形の顔立ち。立ち居振る舞いが何ともお上品で、ホンマにきれかった! 以前から器用な俳優と思っていたけれど、ここまで完ぺきにやり遂げるとは恐れ入った。
 相方の俊介に扮した横浜流星も負けずに熱演しています。首筋にそこはかとなく艶っぽさを感じさせる女形でした。喜久雄に対する得も言われぬ複雑な感情もうまく顔で表現していました。そして半二郎役の渡辺謙。堂々たるベテラン役者ぶりで、その存在感に圧倒されました。今や三國連太郎を越えたかもしれませんね。
相方の俊介に扮した横浜流星も負けずに熱演しています。首筋にそこはかとなく艶っぽさを感じさせる女形でした。喜久雄に対する得も言われぬ複雑な感情もうまく顔で表現していました。そして半二郎役の渡辺謙。堂々たるベテラン役者ぶりで、その存在感に圧倒されました。今や三國連太郎を越えたかもしれませんね。
吉沢と横浜は四代目中村鴈治郎から直接、歌舞伎の指導を受けたそうです。おそらくビシビシ鍛えられたと推察されます。どこを取っても、歌舞伎役者そのものでしたから。そんな2人が舞台から離れると、ガラの悪い大阪弁でまくしたてるのだから何とも痛快! 大阪弁はよほど監修が行き届いていたとみえ、全く違和感がなかったです。
 舞台での芸がハイライトです。吉沢亮と横浜流星による『二人藤娘』や『二人娘道成寺』での息の合った舞踊には見とれてしまいました。2人とも歌舞伎界へシフトしたらええのにと思ったほど。『曽根崎心中』では、悲壮感あふれるお初を演じた横浜流星に喝采を送りたいです。本作は歌舞伎の映画としても存分に楽しめます。
舞台での芸がハイライトです。吉沢亮と横浜流星による『二人藤娘』や『二人娘道成寺』での息の合った舞踊には見とれてしまいました。2人とも歌舞伎界へシフトしたらええのにと思ったほど。『曽根崎心中』では、悲壮感あふれるお初を演じた横浜流星に喝采を送りたいです。本作は歌舞伎の映画としても存分に楽しめます。
喜久雄と俊介の少年時代にそれぞれ扮した黒川想矢と越山敬達のひたむきな演技も印象的でした。他に寺島しのぶ、田中泯、永瀬正敏、高畑充希、島田久作……と実力派の俳優で脇を固めており、ブレのない演技が本作をしっかり締めていました。
 フランス人カメラマンのソフィアン・エル・ファニによるカメラワークもまた素晴らしかった。とりわけ舞台での撮影が秀逸。いろんな角度から役者の内部をえぐり出すようにしつこく迫り、類まれなる様式美を構築していました。脱帽です。
フランス人カメラマンのソフィアン・エル・ファニによるカメラワークもまた素晴らしかった。とりわけ舞台での撮影が秀逸。いろんな角度から役者の内部をえぐり出すようにしつこく迫り、類まれなる様式美を構築していました。脱帽です。
今や歌舞伎界も東京一極集中で、江戸の歌舞伎が主です。だからマイナーな上方歌舞伎にスポットが当てられ、大阪人のぼくにはすごくうれしかった。当然、大阪や京都といった関西が主舞台となり、馴染みのある場所が映っていました。芝居小屋は京都の劇場や先斗町歌舞練場などが使われており、喜久雄と俊介が本音を語り合う橋は石川に架かる玉手橋(柏原市)でしたね。
 ミミズクの刺青を背中に彫った、あっちの世界の男が日本一の歌舞伎役者を夢見て、他者を蹴り落としながら駆け上っていく。梨園の光を浴び、影に潜みながら……。その50年間のドラマチックな足跡をかくも格調高く描いた本作は紛れもなく傑作でした。
ミミズクの刺青を背中に彫った、あっちの世界の男が日本一の歌舞伎役者を夢見て、他者を蹴り落としながら駆け上っていく。梨園の光を浴び、影に潜みながら……。その50年間のドラマチックな足跡をかくも格調高く描いた本作は紛れもなく傑作でした。
最後にもう一度、吉沢亮と横浜流星のお二人さん、ほんまにきれかった!!
武部 好伸(作家・エッセイスト)
配給:東宝
©吉田修一/朝日新聞出版 ©2025映画「国宝」製作委員会
公式サイト:kokuhou-movie.com
公式X:https://x.com/kokuhou_movie
公式Instagram:https://www.instagram.com/kokuhou_movie/
公式TikTok:https://www.tiktok.com/@kokuhoumovie


