
| 原題 | Talking the Pictures |
|---|---|
| 制作年・国 | 2019年 日本 |
| 上映時間 | 2時間7分 |
| 監督 | 周防正行 |
| 出演 | 成田凌 黒島結菜 永瀬正敏 高良健吾 音尾琢真 竹中直人 渡辺えり 井上真央 小日向文世 竹野内豊 |
| 公開日、上映劇場 | 2019年12月13日(金)~全国ロードショー |

~映画への愛と情熱がほとばしる活動弁士の奇天烈行状記~
「活動弁士の映画が撮られているらしいですよ」。2年前、ラジオ関西でパーソナリティーをしている知人の女性活動弁士、大森くみこさんから耳寄りな情報を教えてもらって以来、この映画のことがどうにも気になって仕方がありませんでした。なぜなら、『大阪「映画」事始め』(2016年、彩流社)を上梓したこともあり、映画創成期の諸々のことにいたく関心を持っているからです。それも周防正行監督がメガホンを取るというのです。5年ぶりの新作。期待せずにはおられませんでした。
 で、観ました! てっきりお堅い「歴史モノ」とばかり思っていたのに、見事に、かつ心地よく裏切られました(笑)。全編、お笑いで包み込んだエンタメ喜劇。といっても、きちんと史実を踏んで撮られているので、「えっ、なんで!?」と首を傾げることは一度もありませんでした。なにせ3年間、徹底的に取材して土台を固めたうえでクランクインしているからです。『それでもボクはやってない』(07)や『終の信託』(12)などしかり、周防監督はとことん調べはりますから、納得です。
で、観ました! てっきりお堅い「歴史モノ」とばかり思っていたのに、見事に、かつ心地よく裏切られました(笑)。全編、お笑いで包み込んだエンタメ喜劇。といっても、きちんと史実を踏んで撮られているので、「えっ、なんで!?」と首を傾げることは一度もありませんでした。なにせ3年間、徹底的に取材して土台を固めたうえでクランクインしているからです。『それでもボクはやってない』(07)や『終の信託』(12)などしかり、周防監督はとことん調べはりますから、納得です。
時代は大正初期。活動写真が花盛りです。「映画」の呼称が普及するのは大正中期以降です。このエッセイでは、「活動写真」と「映画」がごっちゃになりますので、悪しからず(笑)。
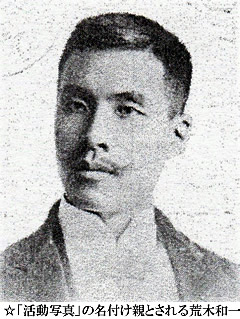
「活動写真」の名付け親がはっきりしていませんが、スクリーン投影式映画に初めてこの名称を付けたのは、渡米して発明王エジソンに直談判し、明治29(1896)年にヴァイタスコープという映写機を日本に輸入した大阪・心斎橋の舶来雑貨商、荒木和一さんだとぼくは思っています。この人が難波の鉄工所で試写を行ったのが日本での映画初上映……。これ以上、この話を進めると、まったく別の内容になってしまうので、ここで中断。
当時、映画館(これも正しくは活動写真常設館)で人気を集めていたのは、俳優ならぬ、活動弁士でした。略して「活弁(カツベン)」。モノクロの無声(サイレント)映画だったので、解説を要したわけです。活動弁士は海外では存在せず、日本だけの職業です。当初は「口上言い」「口上屋」と呼ばれており、明治32(1899)年ごろから「活動弁士」の名が定着しました。関西では「映画解説者」、関東では「映画説明者」と言われています。

その第1号が大阪・南船場で生まれた上田布袋軒。明治29(1896)年12月、難波の南地演舞場(現在、TOHOシネマなんばのあるビル)で、1人でしか観られないエジソン発明の「動く写真」キネトスコープの実演で初めて解説したからです。このあと続々と活弁が登場し、声色を遣った流暢な語り口(ルックスも!)に観客が酔いしれました。
そんな活動弁士を夢見る青年がこの映画の主人公、俊太郎(成田凌)です。映写機とフィルム持参で各地を巡業する活動写真屋の一員でしたが、実態はドロボウ一味のニセ弁士。盗んだ大金を持ち逃げし、とある田舎町の青木館という映画館に転がり込んだところから本筋がはじまります。
旧態然とした青木館は江戸時代の芝居小屋から活動写真の上映館へと衣替えしたところで、当時、そういう小屋が数多くありました。一方、ライバルのタチバナ館は、映画常設館として新たに建造されました。旧体制と新体制のぶつかり合いです。タチバナ館は、色仕掛けで活動弁士を引き抜いたり、あの手この手となりふり構わず青木館を潰そうと躍起になります。そんな混沌とする中、俊太郎がいかにしてホンマもんの活動弁士になっていくかが描かれています。
 映画が唯一の娯楽とあって、映画館の賑わいは相当なもの。三味線、鳴り物、笛で編成された「楽団」のサウンドに合わせ、弁士がおもむろに登場するや、やんやの喝采。場内はすさまじい熱気です。ぼくの大好きなイタリア映画『ニューシネマ・パラダイス』(1988年)は戦後の物語ですが、どこか共通するところがありますね。こうした活況はテレビが普及する昭和30年代後半まで続いていました。ぼくの幼かったころ、タバコの煙が充満していた映画館に行くと、いつもすし詰め状態でした。
映画が唯一の娯楽とあって、映画館の賑わいは相当なもの。三味線、鳴り物、笛で編成された「楽団」のサウンドに合わせ、弁士がおもむろに登場するや、やんやの喝采。場内はすさまじい熱気です。ぼくの大好きなイタリア映画『ニューシネマ・パラダイス』(1988年)は戦後の物語ですが、どこか共通するところがありますね。こうした活況はテレビが普及する昭和30年代後半まで続いていました。ぼくの幼かったころ、タバコの煙が充満していた映画館に行くと、いつもすし詰め状態でした。
2つの映画館の対立を軸に、女優を志望する幼なじみの栗原梅子(黒島結菜)との恋愛模様が盛り込まれ、そこにドロボウ一味を追跡するしつこい刑事が(竹野内豊)が絡んできます。ときにはスラプスティック・コメディ(ドタバタ喜劇)の様相を見せるのは、当時のサイレント喜劇映画へのオマージュなのでしょう。
 大酒呑みの弁士(永瀬正敏)、スター気取りの弁士(高良健吾)、汗をかきまくる弁士(森田甘路)、青木館の気の弱い館主(竹中直人)としっかりモンの女房(渡辺えり)、強欲なタチバナ館の社長(小日向文世)、これまた金に執着するドロボウの首領(音尾琢真)……。なんとも個性豊かな面々が映画に刺激的な彩りを添えています。
大酒呑みの弁士(永瀬正敏)、スター気取りの弁士(高良健吾)、汗をかきまくる弁士(森田甘路)、青木館の気の弱い館主(竹中直人)としっかりモンの女房(渡辺えり)、強欲なタチバナ館の社長(小日向文世)、これまた金に執着するドロボウの首領(音尾琢真)……。なんとも個性豊かな面々が映画に刺激的な彩りを添えています。
「日本映画の父」と呼ばれるマキノ省三(山本耕史)の撮影シーンは興味深かったです。見物人が大勢いる中でカメラを回し、邪魔者が入ってもそのまま続行。なんとまぁ、おおらかなこと。牧野の弟子で、のちに阪妻こと、阪東妻三郎を起用した剣戟映画の名作『雄呂血』(1925年)を撮った二川文太郎(池松壮亮)を登場させているあたり、ニクイ、ニクイ。
 映画館のなかで上映されるのは、もちろん無声映画です。トータルで11本。いずれも当時のフィルムを修正したものと思っていたのですが、実在のフィルム1本を除く10本がすべてこの作品のために製作されました。つまり新作なんです!
映画館のなかで上映されるのは、もちろん無声映画です。トータルで11本。いずれも当時のフィルムを修正したものと思っていたのですが、実在のフィルム1本を除く10本がすべてこの作品のために製作されました。つまり新作なんです!
『金色夜叉』や『ノートルダムのせむし男』など再現版が6本、オリジナル版が4本。ぼくのお気に入りの女優シャーロット・ケイト・フォックスが出演していたのがたまらなくうれしかったです。この人、無声映画向けの顔をしてはりますね。そして実在のフィルムは、なんと『雄呂血』でした! 周防監督、ちゃんとキメてはりますわ。
 1929年にアメリカで『ジャズシンガー』、日本でも1931年に『マダムと女房』というトーキー映画が公開され、状況が一変しました。当然、活動弁士にとっては死活問題になり、やがて彼らは映画館から姿を消していきます。時代の流れには逆らえないんですね。
1929年にアメリカで『ジャズシンガー』、日本でも1931年に『マダムと女房』というトーキー映画が公開され、状況が一変しました。当然、活動弁士にとっては死活問題になり、やがて彼らは映画館から姿を消していきます。時代の流れには逆らえないんですね。
現在、冒頭でお名前を出させてもらった大森くみこさん、片岡一郎さん、坂本頼光さんら全国に10人ほどの活動弁士がいます。数年前、帝国キネマの傑作『何が彼女をそうさせたか』(1927年)を活弁付きで鑑賞したときは、感動のあまり心が震えました。
それにしても、この映画の登場人物がみな若い! エネルギーがほとばしっています。夢と希望を与える活動写真への愛と情熱がビンビン伝わってきました、あの時代に生まれ、あの濃厚な映画館に浸りたかったなぁ……。心底、そう思いました。
武部 好伸(エッセイスト)
公式サイト⇒ http://www.katsuben.jp/
©2019 「カツベン!」製作委員会


