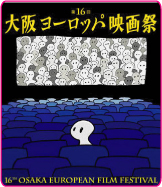| ★隣人 |
| ★ロフト. |
| 映画祭公式ホームページ |
 |
『隣 人』 Forasters
監督・脚本:ベントゥーラ・ポンス (2007年 スペイン 1時間45分) 出演:アナ・リサラン、ジュアン・ペラ ヨーロッパ映画祭の最終日に「隣人」が上映されました。監督のベントゥーラ・ポンス氏は今年の名誉会長を努めました。上映後、観客と監督のディスカッションが行われました。 |
||||||||||||||||
| Q:この映画は、60年代と現代という2つの時代を軸に描いています。特に、訴えたかったことは何ですか?
A:実は人生において、世代を超えて同じようなことが、繰り返されているということを訴えたかったのです。自分が若いころは両親の生き方を否定しがちだけれど、いつのまにか自分も両親と同じような人生を繰り返しているということ。この映画はいろいろな国で上映しましたが、家族のそうしたつながりにはどの国でも普遍的なものを感じました。 |
|||||||||||||||||
 |
Q:、一緒に住んでいても家族ではお互いに理解しにくいということはどこの国でもがあるのかもしれませんね。でも、この映画では上の階に住むイスラムの人には親しみを感じていくことも描かれています。 A:私の国では多民族の居住者がいます。現代ではアフリカからの移民が多いです。外国人ということは他者という恐れが生まれます。どう交流し、接していくかによって、その関係は変わってくると思います。結局、自分たちと違う異邦人を恐れるべきは自分たちの中にあるということです。 |
||||||||||||||||
| Q:スペインは地域によって、話されている言語が違います。映画の舞台はバルセロナですが、この映画ではどのように考えて、カタラン語(バルセロナ周辺の言語)とカスティリアーノ語(マドリッドの周辺の言語)を使われていたのでしょうか?
A:フランコ独裁政権下では他言語の使用に対しては抑圧がありました。ですから、1950年代には、カタラン語は許されていなかったのです。ですが、みんな家族の中では、自分たちの言語であるカタラン語を話していました。映画に描かれている1965年はフランコ独裁政権最後の年。人々は抑圧されていた自由に対して希求していたときです。キャラクターの行動も少し変わりますが、人々の営みは政治的な背景があっても同じことを繰り返してしまうということです。 |
|||||||||||||||||
 |
Q:初めの時代でおばあさんから子どもに本が渡されるが、あの本の意味は何かあるのでしょうか?
A:本のタイトルは「人形の部屋」です。マヨルカ出身の作家の本です。私自身が好きな本で、実は私物です。カタルーニャ語の結束のために子どもにあげるということです。言語の統一は民族を超えます。死にかかっているおばあさんがさりげなく子どもに渡すというようにしたのです。 |
||||||||||||||||
| この映画の原作はサーチ・ベルベルという人が書いた戯曲です。実はその人の戯曲を映画化するのは3回目で、「カーエイス」「生きるべきか死ぬべきか」そして、この映画です。
Q:1つのアパートの部屋を濃密に使い、演劇的に見せていますが、戯曲を映画化するのに工夫したところはどういう点ですか? A:原作通りだと、3時間半となるので、凝縮しました。物語の順番や対話の内容も変えました。また、キリスト教のシンボルを象徴していたことも変えました。2つの時代をセピア色とカラーに分けて観客にわかりやすいようにしました。いろいろたし算したり引き算したりして、原作を忠実に表現しながらも、自分なりに工夫しました。 |
|||||||||||||||||
 |
Q:なぜ、この戯曲を映画にしようと思ったのですか?
A:このストーリーに恋をしてしまったからです。私の心の琴線にふれ、心の奥に何かが突き刺さったのです。なぜかについては、うまく説明がつきませんが、取り付かれたというかんじです。大好きな話だったからこそ大きなエネルギーが生まれたのだと思います。とにかく映画にする価値のあるすばらしい作品だと感じたのです。 |
||||||||||||||||
| 監督は観客からのさまざまな質問に誠実に答えてくれ、知的でこだわりを持って映画づくりをされていることがよくわかりました。
この映画の舞台となったバルセロナは私の大好きな街です。若いころからヨーロッパにはとても憧れを持っていました。だから、病人の看護をしていた移民と思われる女性が汚れた床を拭きながら「ヨーロッパに憧れていたって、こんなもんよ」と言ったのが、妙におかしく笑ってしまいました。確かに街並みは美しく、人もおしゃれですてきなんだけれど、人の営みなんてどこの国も同じようなもの。世代が変わろうが、時代が変わろうが、愛したり憎んだり、けんかしたりしながら生きて、やがて死をむかえるのです。原作が戯曲と聞いてシンプルな構成に納得がいきました。シンプルだからこそ、それぞれの人生が際立ってこの映画に深みを持たせていたように思います。平凡な人の平凡な人生が限りなく愛しく思えるこの作品と出会い、またバルセロナが好きになりました。 |
|||||||||||||||||
(浅倉 志歩)ページトップへ |
|||||||||||||||||
 |
『ロフト.』 LOFT ゲスト:俳優のヴェールレ・バーテンスさん 〜情事部屋で起こった殺人事件の真相を探る 大人の一級サスペンス〜 (2008・ベルギー/117分) 監督 エリク・ヴァン・ローイ 出演 ケーン・デ・ボーウ フィリップ・ペーテルス ブルーノ・ファンデン・ブロッケ マティアス・スクナールツ ケーン・デ・グラーヴェ ヴェルル・バーテンス 作品紹介⇒こちら |
||||||||||||||||
| 秘密の情事を過ごす“浮気部屋”(ロフト)を、交替で共有していた妻子ある5人の男たち。だが、ある日。その部屋で血まみれの女の死体が発見される。彼女は手錠でベッドに繋がれ、側には血文字のメッセージが残されていた。一体、何が起こったのか。秘密裏に集まった5人は、お互いのアリバイを整理し、事件の真相を探り始める。
ベルギーで10人に1人が見たという大ヒット作『ロフト.』が、一般ロードショーより一足早く大阪ヨーロッパ映画祭にて公開され、出演女優のヴェールレ・バーテンスが観客とのディスカッションに参加した。(大阪の一般公開はホクテンザにて2009年12月26日〜) |
|||||||||||||||||
 |
本作においてのバーテンスの役どころは、5人の男性のひとり、精神科医のクリスを魅惑する謎多き女、アン・マライ。劇中では、ミステリアスな魅力で男を翻弄するが、実際の彼女は人懐こい笑顔がキュートな明るい女性。本人も「私はやんちゃで、アンはエレガント。まさに女性という感じ。なので、演じる時は自分の動きがオーバーにならないように、控えめに、笑うときも歯を見せないように、静やかに振舞いました。 監督も、控えめにと口すっぱく言っていた。監督は他の俳優にも同じ方向性で演技指導していて、みんなのテンションが同じレベルであることを注視していましたね。あと、監督とはよく冗談で5人の女がキャラバンで旅をして、旦那を裏切る女性バージョンも作ったら面白いかなと話していました」 | ||||||||||||||||
| 実は、本作の役はオーディションを受けて勝ち取ったという。「この映画が大ヒットしたのは、自分に自信が付いたし嬉しかった。」と話す彼女の今後の予定について聞くと「今、撮影中なのは女刑事の役。犯罪捜査課のチーフで、非常にタフ。ブロンド&ハイヒールで、いつもベルトには拳銃を携えているセクシーな女性を演じています。あと、アメリカの大ヒットドラマ『アグリー・ベティ』が、世界各国でリメイクされていますが、フランドル版の『アグリィ・ベティ』を撮影しました。」さらに、ロフトにも大富豪役で出演し、共に来日を果たしたヤン・デクレール氏については、「昔、彼の娘役をやったことがあるんです。その当時から、フランドル地方でも一番の役者といわれていました。人柄が温かくフレンドリーな方で、私たちみたいな若い役者にも対等に話してくれる素敵な方です。」 | |||||||||||||||||
 |
オープニングの挨拶では、子供の頃に日本のテレビドラマ「おしん」に夢中だったと話してくれたが、今は日本のアニメを良く見るそうだ。「日本のアニメは、美しく愛を表現していて心に染み渡ります。アニメは子供向けという感じがありますが、日本のものは大人も一緒に楽しめて素晴らしいです。あと、友人で日本のホラー映画が大好きな人がいます。日本のホラーは優れているので、『リング』とか、あまりにも怖くて私は最後まで見れません(笑) | ||||||||||||||||
| そして、最後に劇中に登場する5人の男性の中で好みのタイプを聞かれると「この質問は本当に良く聞かれます(笑)実人生だったらマニック、映画のストーリーのなかではクリスですね。クリスは、女性をいい感じで魅惑するタイプ。非常にエレガントで落ち着いた感じがあります。実は、マニックを演じたケーン・デ・グラーヴェは、次の映画で私の夫役を演じるんです。そして、また妻である私を裏切って、よその女と浮気するんです(笑)」
5人の男と複数の女性たちの秘密が入り乱れて、二転三転していくシリアスな映画と打って変わって、ガハハと大口をあけて笑う彼女が印象的なディスカッションだった。刑事を演じるというバーテンスの次回作が、いつか日本で公開されることを期待したい。 |
|||||||||||||||||
(中西 奈津子)ページトップへ |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||