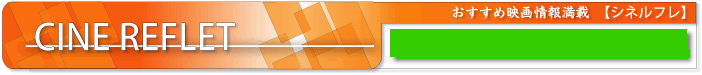| ・ 夏時間の庭 |
| ・ ベルサイユの子 |
| ・ コード(香樹) |
| ・ コード(河田充)NEW! |
| ・ 華麗なるアリバイ |
| ・ 西のエデン(浅倉) |
| ・ 西のエデン(河田充) |
| ・ 顧 客 |
| ・
サガン −悲しみよこんにちは− |
| ・ ジョニー・マッド・ドッグ |
| ・ シークレット・ディフェンス |
| ・ 美しい人 |
| ・ 未来の食卓 NEW! |
| 映画祭トップ・・・ |
| 映画祭公式ホームページ |
| ★ フランス映画祭2009 上映作品紹介 | |
| ★夏時間の庭 | |
 |
『夏時間の庭』 〜パリ郊外ヴァルモンドワに流れる時の美しさ〜 (2008年 フランス 1時間42分) 監督:オリヴィエ・アサイヤス 出演:ジュリエット・ビノシュ、シャルル・ベルリング、 ジェレミー・レニエ、エディット・スコブ、ドミニク・レイモン、 ヴァレリー・ボヌトン、カイル・イーストウッド、 イザベル・サドワイヤン 配給:クレストインターナショナル 2009年6/6〜テアトル梅田、 6/20〜京都シネマ、シネ・リーブル神戸にて公開 ★ 映画祭サイト→ |
| 最初に一軒の邸宅が映し出される。初めは全体がぼんやりしていて,何が映されているのか分からない。間もなく邸宅だと分かるが,はっきり見えたり輪郭がぼやけたりを繰り返す。まるで記憶の中の存在をじっと見詰めるような感覚だ。その邸宅の物寂しげな風情は,必要とされなくなったものの悲しみを象徴するようだ。そして,フレデリックら3人兄妹の世代を中心として,親子三代にわたる家族の情景が,時代の変化の中に捉えられていく。 | |
 |
本作は,オルセー美術館開館20周年記念作品と銘打たれており,同美術館の全面的な協力の下に製作されたという。さすがに映画に登場する絵画はレプリカだが,それ以外の美術品は本物だそうだ。例えば,母エレーヌが愛用した書斎机と椅子,飾り棚はマジョレル,家政婦エロイーズがもらった花瓶はブラックモンの作品だ。それらは,大勢の人に歴史を伝える展示品ではなく,個々人の日常生活の中で,それを支えるものとして息づいている。 |
| 一級なのは調度品だけではない。映画全体が十分に成熟して気品のある輝きを放っている。長男フレデリックは,フランスに住みながら,愛着のある邸宅や絵画を手放さざるを得ないジレンマを抱えている。二男ジェレミーは中国で働き,長女アドリエンヌは世界を飛び回っている。フレデリックの息子に言わせると,コローの絵は古臭い。彼らがエレーヌの75歳の誕生日に邸宅に集まった冒頭のシーンは,孫らの活気に満ちた姿が印象に残る。 | |
 |
これと対照的なのが,皆が帰った後のエレーヌの姿だ。彼女は,観客に背を向けて一人階段を上り,薄暗い部屋の中で椅子に座っている。彼女の存在が消えれば,邸宅が空の花瓶のような空しさに包まれてしまう。そんな痛ましさがある。だが,本作には喪失感は全くない。母と叔父との秘密の関係が隠し味になっている。子供や孫の台詞の端々から母への愛がにじみ出ている。だから,ラストで駆けていく孫の後ろ姿が清々しいものとなった。 |
| (河田 充規)ページトップへ |
|
| ★ベルサイユの子 | |
 |
『ベルサイユの子』 〜見逃せない,長編映画第1作に光る感性〜 (2008年 フランス 1時間53分) 監督・脚本:ピエール・ショレール 出演:ギョーム・ドパルデュー、 マックス・ベセト・ド・マルグレーヴ、ジュディット・シュムラ、 オーレ・アッティカ、パトリック・デカン、マッテオ・ジョヴァネッティ 配給:ザジフィルム 公開:2009年5/2〜シネスイッチ銀座他、全国順次ロードショー 大阪では、5/23〜テアトル梅田、順次京都シネマ、神戸アートビレッジセンターにて公開 ★ 映画祭サイト→ |
| ベルサイユ宮殿を囲む森の中で小屋住まいをしている人たちがいる。その一人がダミアンだ。かつて父親との間で確執があったらしく,自らの意思で社会から逸脱した生活を営んでいる。一方,ニーナは,5歳くらいの息子エンゾを連れてパリの街中をさ迷っている。両親から何をやってもダメな役立たずのクズと言われたが,社会の一員としての生活を望んでいる。二人は,社会に対する思いは異なるが,社会の外に存在する点で共通していた。 本作からは,フランスにおける貧困や福祉などの社会問題が垣間見える。福祉事務所の手続,生活保護の受給や子供の就学などに触れられている。だが,作り手が捉えようとしたものは,おそらく,社会の最小単位である家族の有り様だろう。ダミアンとエンゾという擬似的な父子を中核として,母ニーナと子エンゾ,ダミアンとその父の関係を通じ,親子の絆や家族の存在意義を問いかけているようだ。もとより,一義的な答えは存在しない。 幼いエンゾに扮したマックス・ベセット・ド・マルグレーヴが魅力的で,ダミアン役のギョーム・ドパルデューが本作に深みを与えている。沈うつになりがちな題材の中で,エンゾの存在がほんのりと輝いている。愛くるしいだけでなく,じっと大人たちを観察するような痛ましさを見せる。ダミアンは,エンゾには自分と同じ道を歩ませたくなかったようだ。森の小屋に戻りたいと言うエンゾを学校に通わせ,自らは再び父の下を去っていく。 一方,ニーナは,ダミアンの下にエンゾを置き去りにする。それは,介護の仕事に就いて生活基盤を確立するためだった。彼女に介護してもらった老女が「あなたは素晴らしいわ」という言葉がニーナの社会復帰を祝福する。だが,彼女がエンゾを訪ねていくまでには7年が経過していた。無責任だと言われても仕方がないが,それが彼女の弱さなのかも知れない。エンディングの後,エンゾがどんな選択をしたのかは観客の想像に委ねられた。 |
|
| (河田 充規)ページトップへ |
|
| ★ミーシャ/ホロコーストと白い狼 (中西奈津子バージョン) | |
 |
『ミーシャ ホロコーストと白い狼』 〜両親を捜して3000マイル。 ホロコーストから逃れたユダヤ人少女の過酷な旅路〜 (2007年 フランス・ベルギー・ドイツ 1時間59分) 原作:ミーシャ・デフォンスカ「少女ミーシャの旅」 監督:ヴェラ・ベルモン 出演:マチルド・ゴファール、ヤエル・アベカシス、 ギイ・ブドス、ミシェル・ベルニエ、ベンノ・フユルマン、 アンヌ・マリー・フィリップ、フランク・ド・ラ・ぺルソンヌ 2009年5月9日〜TOHOシネマズシャンテ 他全国順次公開 関西では、6/6〜テアトル梅田 他 配給:トルネード・フィルム ★ 映画祭サイト→ ★ 公式ホームページサイト→ ★ 監督とマチルダちゃんインタビュー→ |
| 世界17カ国で翻訳されたミーシャ・デフォンスカの原作「少女ミーシャの旅」を『女優マルキーズ』の監督ヴェラ・ベルモンが映画化。1942年、ナチス占領下のヨーロッパを舞台に、一斉検挙で両親とはぐれ一人ぼっちになってしまった少女の壮絶な旅を描く。 | |
 |
支援者の計らいで父母と共に屋根裏部屋で暮らしていた8歳の少女ミーシャ。ある日、彼女が学校へ通う間にナチスのユダヤ人狩が始まり、両親を連れ去られてしまう。一度は郊外のベルギー人宅へ保護されるミーシャだが、両親は“東”にいると知り小さなコンパスを頼りに2人を捜す旅に出る。 |
| 「旅に出る」と言ってもその道のりは平坦なものではなく想像以上の過酷さを極める。ベルギーを発ってドイツ、ポーランド、ウクライナの森を3年かけて横断していくのだが、もちろん森のなかには食料などなく、冬になれば雪が積もり、野生の生物にだって狙われかねない。普通なら飢えと寒さと孤独に耐え切れず、途中で命を落としてしまいそうだが、ミーシャは驚くべきバイタリティでこの困難を乗り越えていく。 |
|
 |
森の中に佇む古びた空き家や民家から衣類や食事を失敬し、空腹を満たすためには泥まみれのミミズだって、うさぎや猪の生肉だって、ガツガツほおばる。やさしい両親のもとで大切に育てられていた少女とは思えない、知恵と適応能力で野生を克服していく。そんなミーシャの精神力の強さには全編通して驚かされてばかりだが、その勇気全てが両親への愛を原動力にしていると再確認させられたとき、ナチスが奪ったものの大きさを実感。激しい怒りを覚えると同時に、少女のけなげさに胸を熱くさせられる。
|
| ミーシャ役のマチルド・ゴファールは、今作が女優デビューとなる。演技の上手な子役は数多くいるが、彼女の卓越した表現力と天性の存在感は唯一無二。物怖じせず何にでも挑戦し、セリフにアドリブまで加える天才ぶりに監督も感服したようだ。そして、もうひとつ。本作に欠かせない存在が、森で両親の変わりにミーシャを支えた狼たちだ。ミーシャに心を許して獲物を分け与え、時には添い寝をして、ピンチを助けるなどの大活躍でミーシャの旅路を盛り上げる。
監督のヴェラは、ロシアとポーランドの血を引くユダヤ人であり、第二次世界大戦中は隠れて生活していたそうだ。その頃の経験をふまえて、逆境に負けない強い意志と生命の神秘をフィルムに込めた。悲痛だが絶望を回避したエンディングには、監督の未来への希望が託されている。 |
|
| (中西 奈津子)ページトップへ |
|
| ★ミーシャ/ホロコーストと白い狼 (河田充規バージョン) | |
 |
『ミーシャ ホロコーストと白い狼』 〜確かに過酷だが美しくもある少女の体験〜 (2007年 フランス・ベルギー・ドイツ 1時間59分) 原作:ミーシャ・デフォンスカ「少女ミーシャの旅」 監督:ヴェラ・ベルモン 出演:マチルド・ゴファール、ヤエル・アベカシス、 ギイ・ブドス、ミシェル・ベルニエ、ベンノ・フユルマン、 アンヌ・マリー・フィリップ、フランク・ド・ラ・ぺルソンヌ 2009年5月9日〜TOHOシネマズシャンテ 他全国順次公開 関西では、6/6〜テアトル梅田 他 配給:トルネード・フィルム ★ 映画祭サイト→ ★ 公式ホームページ→ ★ 監督とマチルダちゃんインタビュー→ |
| 映画は,ナチス・ドイツの占領下にあった1942年のブリュッセルから始まる。そこでは,ロシア人の母親とユダヤ系ドイツ人の父親を持つ8歳の少女ミーシャが暮らしていた。彼女は,動物好きで,母親への愛着がとても強かった。そんな何気ないような日常の情景が丁寧に描かれ,それが彼女の過酷な冒険の伏線として生きている。一人取り残されたミーシャは,コンパスを手にして,両親が連れて行かれたという東の方向に向かって歩き出す。 | |
 |
ミーシャの旅は,1943年にドイツからポーランドを経て,翌年にはウクライナに至り,1945年3月にまたブリュッセルに戻る。その背景にはナチスによるホロコーストが確かに存在するが,暗示的に示されるだけで,それを直截に描写するシーンはない。かえって,ミーシャを包み込むような雄大な自然の描写が印象に残る。彼女は,白いオオカミと出会い,獲物の肉を分けてもらうなど,心を通わせる。そこには,神秘的な空気が流れていた。 |
| また,ドイツではミーシャが捕まらないかとハラハラさせられ,ポーランドではナチスの罠を見抜く彼女の利発さが示される。その後のウクライナのシーンが,本作の中で最も安らぎのある時間だった。ミーシャは,赤軍の青年と知り合い,フィルムに映っていたブリュッセルの街に歓喜する。それまで唐突な別れの経験しかなかったが,その青年とはきちんと別れの挨拶をする。彼女が流す涙には,戦争が家族を引き裂く悲劇が浮かんでいた。 本作は,ホロコーストにテーマを限定することなく,もっと広い視野から戦争が少女の人生に大きな影響を及ぼしたことを語っている。ブリュッセル郊外の村でミーシャの面倒を見てくれた老夫婦がいた。息子が生きていると思い続けているお婆さんの悲しみは,最後にはミーシャの思いと完全に重なる。ラストで示される「ミーシャは両親が2度と戻らないという現実を受け入れることができなかった」というフレーズがずっしりと胸に響く。 |
|
| (河田 充規)ページトップへ |
|
| ★コード (香樹えりバージョン) | |
 |
『コード』
〜夕食会から始まる悲喜こもごも でも人生ってやっぱり素晴らしい!〜 (2008年 フランス 1時間40分) 監督:ダニエル・トンプソン 出演:ダニー・ブーン、パトリック・ブリュルエル、エマニュエル・セニエ、クリストファー・トンプソン ★ 映画祭サイト→ |
| 「モンテーニュ通りのカフェ」のダニエル・トンプソン監督の長編4作目としての作品。群像劇を得意とする監督ならではの、会話から浮かび上がってくる人間模様が素晴らしい。 6月21日、音楽祭の夜。夕食会に集まってくる男女11人は、それぞれに複雑な事情を抱えている。 退屈とわかってはいるけど、この時間を笑顔で取り繕い乗り切らなければならない。それが大人の礼儀(コード)なのだから。 主催者のマリーはやり手の女性弁護士。夫は現在失業中である。改装祝いを兼ねた夕食会には、いろいろな人が招かれる。昔からの友人、家族、新しい仕事仲間、フラメンコの講師など。カップルの中には、今晩別れを切り出そうとしている人や、来る直前にけんかをしている人もいる。友人たちを集めたら、偶然に学生時代の恋人とも再会したりする。テーブルを囲んでみんなと会話をしながら、心はここになく不倫相手の所に飛んでいて、上の空の友人メラニーが印象的だ。 |
|
 |
たくさん人がいればいるほど、孤独を感じることはないだろうか? 言葉が耳の中を素通りしていき、自分だけが違う空間に浮かんで、外から中を見ているような。誰にでも悩みがあって、それでも今だけは笑っていようと必死なのだ。会話の中にある「みんな芝居している」という言葉が、心に突き刺さる。 |
|
マリーの妹が30歳も年の離れた夫とやって来る。タイミング悪く、妹と犬猿の仲である父も泊まりに来た。父はみんなに挨拶することも許されず別室に入るのだが、娘婿とは知らないまま、庭のベンチで二人仲良くたばこを一服する。婿と父の同世代どうしの絆が微笑ましい。意気投合して昔の曲でノリノリにダンスし、息もきれぎれなのがとってもチャーミング。長年の大きな溝がこの仲介人によって、埋まることを望まずにはいられない。 この日の出会いと出来事が、集った人々に大きな影響を与える。別れようと思っていた人は、本当の愛を知り、上辺を取り繕っていた人は、自分らしく生きる決断をする。犬猿の仲の親子も、何十年ぶりかで会話をもつことになった。 人はいつも誰かとつながっている。そのつながりを大事にして一歩前に進んで行くこと。たとえつながりがなくなっても、すべてを受け入れて笑顔で人生を楽しむことはできるのだと、あたたかい気持ちが残るだろう。 |
|
| (香樹 えり)ページトップへ |
|
| ★コード (河田充規バージョン) | |
 |
『コード』
〜人生は突然変わる暗証番号のようなもの〜 (2008年 フランス 1時間40分) 監督:ダニエル・トンプソン 出演:ダニー・ブーン、パトリック・ブリュルエル、エマニュエル・セニエ、クリストファー・トンプソン、 カリン・ヴィアール、 マリナ・フォイ、 マリナ・ハンズ、 パトリック・シェスネ、 ブランカ・リー ロラン・ストッケール ★ 映画祭サイト→ |
| 前作「モンテーニュ通りのカフェ」より明らかにグレードアップしている。ダニエル・トンプソン監督の新作は,11人もの登場人物の1年間の変化を通して,人生の哀歓を彩り豊かにまとめ上げていく。途切れず続いていく人生の中の1日とその1年後に焦点を当てただけだが,そこから色んな人生の縮図が見えてくる。人の言葉や出会いをきっかけに人生はどのように変わるか分からない。人生は,コード(決まり)がないからこそ,面白い。 | |
 |
6月21日の夏至にはフランス各地で音楽祭が行われる。パリでも多様な音楽が溢れ,様々な人生が交錯する。全く申し分ない舞台設定だ。この日,マリーとピョートルの夫婦が友人や知人をディナーに招く。メラニーやサラが言うように,ディナーでは人は仮面をかぶって笑って見せ,みんな芝居をしている。真実を話すことによる悲劇を避け,人を傷つけないためにウソをつく。それを可能にしてくれる愛と勇気と友情があれば,人生は輝く。 |
| 登場人物のディナー前の相関関係とその後の変化が少しずつ明らかにされていくので,適度の緊張感が持続する。頭に浮かんだ疑問が後で解消されるとき,カタルシスを味わえる。マリーには不倫歴があり,不倫中のメラニーは夫アランとの離婚を考えている。夫リュカと危機的状況にあるサラはピョートルと美術学校で恋人同士だったようだ。マリーの妹ジュリエットは,30歳年上のエルワンと結婚したが,母を捨てた父親を許せないでいる。 | |
 |
夫婦だけではなく,親子の関係にも目が向けられる。ジュリエットが帰り際に言う「父に会うのは変な気分」「ずいぶん老けた」というセリフには含蓄がある。皆が帰った後,マリーがジュリエットから渡されたDVDを父親と2人で見るシーンでは,その表情や身振りに親子の絆がほの見えてくる。その2人を戸口からそっと見詰めるジュリエットの頬には涙が伝う。夫婦や不倫に親子と色々な関係があるが,この世に不変のものはあり得ない。 |
| また,登場人物の間に認識のズレがあるため,そこから上質の喜劇が生まれる。ジュリエットの父親はエルワンに「オヤジ好きの娘を見つければいい」と助言し,ピョートルは妻の不倫相手だったジャン=ルイに「失恋の痛手は癒えたか」と尋ねる。ピョートルがサラから「あなたは父親に」と言われたときのリアクションが可笑しくも切ない。リュカは,マリーに「ピョートルが幸せなら私も幸せになれる。それが夫婦なのね。」と言われるが…。 リュカはマリーに,メラニーはピョートルに真実を話さないし,アランは助からない患者に真実を話せない。優しさ故だが,時には真実が有用なこともある。アランとフラメンコ講師マヌエラとの間に隠された事実は,人生を明るく照らす。サラは,本当の自分を見つけ出し,ピョートルには真実を告げる。テレビに映る彼女を見るリュカとピョートルの表情は見逃せない。ジュリエットも変化と無縁ではなかった。変化するからこそ,人生だ。 |
|
(河田 充規)ページトップへ |
|
| ★華麗なるアリバイ | |
 |
『華麗なるアリバイ(仮)』 〜嫉妬とアリバイの盲点を突く “アガサ”ミステリーを映画化〜 (2008年 フランス 1時間33分) 原作 アガサ・クリスティー「ホロー荘の殺人」 監督 パスカル・ボニゼール 出演 ミュウ=ミュウ、 ランベール・ウィルソン、 ヴァレリア・ブルーニ・テデスキ ピエール・アルディティ、 アンヌ・コンシニ、 マチュー・ドゥミ カテリーナ・ムリーノ、 モーリス・ベニシュー、セリーヌ・サレット、アガット・ボニゼール 2010年夏〜 Bunkamuraル・シネマ ほか全国ロードショー ★ 映画祭サイト→ |
| ギネスブックで「世界最高のベストセラー作家」に認定されているミステリーの女王、アガサ・クリスティーの名作「ホロー荘の殺人」を映画化。
フランスの小さな村・ヴェトゥイユ。上院議員のアンリと彼の妻・エリアーヌが住む邸宅に、彼らの一族や仲間たちが招かれる。しかし、集まったのは恋愛関係のもつれが予想されるいわくつきの男女7人。何とか緊迫した食事会を無事に終え、誰もがそのまま平穏に時が過ぎてゆくことを切望していた。だが、翌日の昼下がり。一発の銃声が静寂を切り裂いた。すると、プールには男の死体が倒れており…。 生前アガサは同小説に対して「ポワロの登場が失敗だった。彼を抜きにするともっとよくなる」と話していたらしく、本作はその意思を考慮して作られている。(ポワロとはアガサ作品に登場する名探偵のこと)つまりポワロは登場しないわけだが、物語の主軸が男女の愛憎劇で、トリックも実にフランス映画らしい上品な仕上がりになっているため、探偵不在でもなんら違和感なく新作ラブミステリーとして楽しめる。 登場人物は総勢9名。愛憎劇というだけあり、男女間のつながりがなかなか複雑だ。簡単に紹介すると、議員夫妻の邸宅にはこんなメンバーが集まったことになる。 作家のフィリップ〈エステルが好き〉、靴屋の店員マルト〈フィリップが好き〉、学生のクロエ、精神病医学者のピエールと彼の妻・クレール。彫刻家のエステル〈ピエールの愛人〉、女優のリア〈ピエールの元恋人〉、エリアーヌ〈ピエールと元不倫関係〉。 さすが恋愛大国フランス。これで何も起きないわけがない。しかし、なんとも節操のない男ピエール。邸宅の敷地内でも妻をほったらかして、過去の女の誘惑に負けるわ、愛した女4人が一堂に会しても平然としているわ、並々ならぬ恋愛マスターぶりを発揮。だが、そこで女同士も声を荒立てて男を取り合わないのがおフランス。嫉妬心を募らせていようとも平静を装い見えない火花で交戦する。例えば、本妻クレールと現愛人エステルの会話。クレールが射撃を楽しんだあと手についた火薬の匂いが消えないと気にしているのだが、それを嗅いだエステルが「大丈夫、せっけんの匂いよ」と切り返す。一見何の変哲もないシーンのように感じるが、合わすようで合わさない目線の動きや、微妙なほほ笑みから女の嫉妬とプライドが入り混じった異様な空気が流れ出していることに気づき背筋がヒヤッとする。 誰もが本音を隠しているように見え、2人目の犠牲者が出た頃から謎解きのテンポもスリルも増していく。そして、事件の終焉は“華麗なるアリバイ”が明かされることで終わりを告げるが、誰もが捜査を担当したグランジェ刑事のように騙されるだろう。とってもスマートで少し切ない恋のかけひき事件に酔いしれてほしい。 |
|
| (中西 奈津子)ページトップへ |
|
| ★西のエデン (浅倉志歩バージョン) | |
 |
『西のエデン』 〜密入国の孤独な旅。それは永遠に終わらない旅の始まり〜 (2008年 フランス・イタリア・ギリシャ 1時間50分) 監督:コスタ=ガヴラス 出演:リッカルド・スカマルチョ(エリアス) ジュリアンヌ・コーラー(クリスティーナ) エリック・カラヴァッカ、ウルリッヒ・トゥクール、 アニー・デュプレー ★ 映画祭サイト→ ★ 監督インタビュー→ |
| 見終わった時、「ひとつの映画が終わった」でなく、「ひとつの旅が終わった」と思った。それは観光の旅ではなく、自分探しの旅などではない。自分の国を捨てた旅。流浪の旅である。
映画は、密入国のために移民たちを大量に詰め込んだ貨物船のシーンから始まる。乗船した移民たちは、自分たちの身分証明書を破り捨て、海に流す。彼らが身分を捨て、過去を捨て、国を捨てた瞬間である。エリアス(リッカルド・スカルマッチョ)も他の密入者と同じように海に自分の身分証明書を破り捨てた。 |
|
 |
彼が漂着したのはエーゲ海の高級リゾートホテルだった。密入者の彼は国境警備隊から逃れるためにホテルの従業員に扮したり、客室に紛れ込んだりする。やがて、彼は、その島からも逃れ、パリを目指して放浪する。わずかなお金しかない彼の旅は、人の情けが頼りの旅となる。ヒッチハイクをしたり、村の人の家に泊めてもらったりする。さまざまな人と出会う。それはさまざまな人生との出会いである。子持ちのシングルマザーやトラックの運転手など、誰もがわずかな時間だけ彼の人生と交差する。その人がどんな人生を歩んできたのが一目で想像がつき、ひとりひとりの人生が感じられる細やかな描写がすばらしい。旅をすると感性が研ぎ澄まされ、人の心の動きに敏感になる。いつしかエリアスと一緒に旅をしていることに気づいた。彼と一緒に流れゆく景色や風を感じ、一緒にパリに到着した。パリに着くと空気までもが一変する。あんなに恋焦がれ一心に目指していたパリ。そこが彼にとって本当にエデンの園となるのだろうか。 |
| ひとつの旅の終わりは、もうひとつの旅の始まりでもある。国を捨てた旅は永遠に終わらない旅なのかもしれない。ドキュメンタリーを見ているように感じられるリアルな描写はコスタ=ガヴラス監督自身のギリシアからフランスへ移民したという経験に基づいているのかもしれない。2009年ベルリン国際映画祭クロージング作品に選ばれた本作品。主演のリッカルド・スカマルチョの切なく自然な演技に引き込まれる。 |
|
| (浅倉
志歩)ページトップへ |
|
| ★西のエデン (河田充規バージョン) | |
 |
『西のエデン』 〜移民に注がれる,優しさに満ちた眼差し〜 (2008年 フランス・イタリア・ギリシア 1時間50分) 監督:コスタ=ガヴラス 出演:リッカルド・スカマルチョ(エリアス) ジュリアンヌ・コーラー(クリスティーナ) エリック・カラヴァッカ、ウルリッヒ・トゥクール、 アニー・デュプレー ★ 映画祭サイト→ ★ 監督インタビュー→ |
| 青年エリアスは,フランスに不法入国するため,地中海上でボートから貨物船に乗り移る。何か様子がおかしいと不安に思っていると,警備艇が貨物船に近付いてくる。危険を察知してとっさに海に飛び込んで逃げる。そして,場面が変わり,海岸に横たわったエリアスが映し出される。そこはヌーディストビーチだった。自分も全裸になって人々の中に紛れ込み,他人の服を拝借して立ち去る。この導入部のトーンが本作の基調となっている。 | |
 |
ヨーロッパにおける移民を描いた映画には,彼らを取り巻く状況の厳しさを前面に押し出したものが多い。本作でもその一端が示される。エリアスは,一緒に密航しようとした友人が捕まるのを黙って見ているほかない。密航者の遺体が海岸に打ち上げられているシーンもあった。ヒッチハイクで運転手に金だけ取られたこともある。廃品の運搬解体の仕事に就くが,そこでは外国人労働者のためにフランス人が解雇されるという実情も示される。 |
| だが,本作では移民に関する問題が穏やかなタッチで綴られていく。新しい社会に溶け込もうとしても叶わないという移民の苦しみや悩みが沈殿するような重さは全くない。エリアスは,機転を利かせながら,ひたむきに生きていく。カメラは,その姿をコミカルな雰囲気をも交えて包み込んでいく。捜索や巡視をする警察官さえ,必ずしも忌避すべき存在ではなくなる。紛れもなく,エリアスが心の故郷を求めるオデュッセイア(長い旅)だ。 | |
 |
何よりも,エリアスに救いの手を差し伸べる人々の寛容さに心が洗われる。クリスティーナは,そっとエリアスの服の中に現金を差し入れ,彼が出て行くことに気付きながら寝たふりをしている。ソフィアは,彼を自宅に招き,鍋の煮込み料理を振る舞い,ベッドで眠るエリアスを見詰めている。パリに着いてからも,カフェで食べ残しの料理をむさぼるのをギャルソンに見逃してもらう。エリアスに何とも都合よく物事が運ぶのもまた愛嬌だ。 |
イタリアの俳優リッカルド・スカマルチョは,コミカルにもシリアスにもなりすぎず,バランスよくエリアスを好演している。彼は,マジシャンの助手を務め,パリの「リド」へ会いに来るように言われて名刺を渡され,西方にあるエデン(楽園)=パリを目指して旅を続けた。エデンは実在するのか,それとも幻想にすぎないのか。魔法のようにきらきらと点滅を始めたエッフェル塔に向かって歩いていくエリアス。その後ろ姿で映画は終わる。 |
|
| (河田 充規)ページトップへ |
|
| ★顧 客 | |
 |
『顧客』 Cliente 〜忘れかけていた“恋の喜び”〜 (2008年 フランス 1時間45分) 監督:ジョジアーヌ・バラスコ 出演:ナタリー・バイ、エリック・カラヴァカ、イザベル・カレ、ジョジアーヌ・バラスコ ★ 映画祭サイト→ |
| 幾つになっても、恋は人を輝かせる。50歳を超え、テレビ番組で通販商品を紹介・販売するキャリアウーマンのジュディット。離婚の痛手から、恋に臆病になり、以来、出張ホストのサイトで、若く美しい青年達とのゆきずりの恋を楽しんでいた。パトリックというナイーヴな青年と知り合い、逢瀬を重ね、思いが深まってゆく。しかし、彼には愛する妻ファニーがおり、ホストをしていることを知られてしまう…。映画の原題「Cliente」が女性名詞とは『顧客』が女性ということ。 ジュディットが恋したのは、お金を払えば相手をしてくれる男性。出会うきっかけが何であれ、互いに相手を思いやり、抱きしめあうことができれば、そこに生まれるのは、まぎれもなく愛。若い頃なら、自分のことだけを考えて、恋に猛進できたかもしれないが、中年ともなれば、つい相手の家族のことを考えてしまい、わがままにもなれない。そんなジュディットの優しさとためらいが愛らしく、好感が持てる。実年齢も50歳代のナタリー・バイが、プライドと恋する気持ちの間で戸惑う姿を自然体で演じ、好演。 ジュディットと同居している姉イレーヌは、ジュディットとは対照的に、“運命の出会い”を信じ、待ち続ける大らかで屈託のない明るい性格。姉妹のあけっぴろげなおしゃべりと本音でぶつかる口喧嘩が、ユーモアを添える。イレーヌを演じているのは、なんとバラスコ監督自身。 人は一人では生きていけない。恋人や夫婦、姉妹、家族と、誰かを愛し、誰かに愛されて生きていく。人に優しくなれることで、人は幸せを感じるものだということをそっと教えてくれる。 |
|
| (伊藤 久美子)ページトップへ |
|
| ★サガン−悲しみよ こんにちは− | |
 |
『サガン −悲しみよ
こんにちは−』 |
| 18歳で書いた小説『悲しみよ こんにちは』が世界中で大ベストセラーとなり、巨万の富と名声を手にした作家フランソワ−ズ・サガンの半生を追う。 | |
 |
2004年、69歳で亡くなるまで、その人生は人々の注目を集め続けた。サルトル、ゲンズブール、カポーティ、ピカソ、カトリーヌ・ドヌーヴら、文壇、芸能界にわたる華麗な交遊関係。派手なパーティ三昧、スポーツカーでの大事故、ギャンブル、アルコールと浪費の果ての多額な借金、麻薬での有罪判決……。情熱的で、波乱に富んだ人生の裏側には、寂しがりやで、いつも誰かにそばにいてほしいと望む、孤独な魂があった。 |
| サガンを取り巻く人々が次々と変っていく中で、共に老いてゆく生涯の友人達の存在が救いとなる。とりわけ、中年になってからの15年間、共同生活を続けた雑誌編集長のペギーとの、互いに勝気な者同士の、率直で親密な会話は心にしみる。 | |
 |
2回にわたる結婚の失敗に傷つき、書けなくなったらという恐れを抱きつつも、執筆の手を止めることなく数々の小説を発表し続け、登場人物と物語を分かちあってきたサガン。シルヴィ・テステューが迫真の演技でサガンを演じ、無邪気さと偏屈さを内在させた不思議な魅力で、観客をひきつける。 |
| サガンはフランスの詩人ランボーが好きだったという。ラストシーンの美しい太陽は、ランボーの詩の一節を思い出させた。 「もう一度探し出したぞ。 何を?永遠を。 それは、太陽と番(つが)った 海だ。」 (『永遠』アルチュール・ランボー、堀口大學訳) 他人からどうみられようと、自分の心に正直に、常に堂々と、信じるままに人生を歩み続けたサガン。本作を通じて、幾つになっても人生を学べないと吐露する、繊細で傷つきやすい作家の魂に気付くにちがいない。 |
|
| (伊藤 久美子)ページトップへ |
|
| ★ジョニー・マッド・ドッグ | |
 |
『ジョニー・マッド・ドッグ』 〜内戦に巻き込まれた少年少女たちの未来は?〜 (2007年 フランス,ベルギー,リベリア 1時間33分) 監督:ジャン=ステファーヌ・ソヴェール 出演:クリストファー・ミニー、デージ=ヴィクトリア・ヴァンディー、ダグベー・トゥエー ★ 映画祭サイト→ |
| 開巻後すぐ,銃を持った少年兵たちが村を襲っているシーンが目に飛び込んでくる。彼らが反政府軍に属していることや,戦争のために金や食料を調達しようとしていることが次第に明らかになってくる。その手段は,実に手荒で無慈悲なものだ。しかも,短いショットを重ねて手際よく描写されており,正に鬼気迫るシーンとなっている。強奪を終えた彼らが集団でカメラの方に向かって引き上げてくるシーンにかぶさる音楽もまた重苦しい。 コンゴの作家エマニュエル・ドンガラの小説「狂犬ジョニー」を映画化するに当たり,監督は,悲痛な暴力描写から目を背けることなく忠実に映像化したという。だが,本作は,少年兵たちの容赦のない殺りくシーンだけを描いているわけではない。ジョニーと対置する形で,少女ラオコルが紛争の中を懸命に生き延びようとする姿も描いている。もっとも,この対照的に見える2人も内戦に巻き込まれた子どもという点では,全く同じ立場にある。 舞台は,アフリカ某国というだけで特定されていない。ただ,監督は,実際の元少年兵たちをリベリアでオーディションして15人を選んだそうだ。西アフリカにあるリベリアは,1989年に政治腐敗や民族対立が主因となって内戦が勃発し,その終戦後の1997年に反乱軍を率いたチャールズ・テイラーが大統領に就任した。だが,2003年にリベリア和解民主連合(LURD)等の反政府勢力が蜂起し,同大統領は他国へ亡命し,いま再建が進められている。 国連NY本部で本作の試写会が行われた際,監督は「元兵士を使うのは私の原則だった。この恐怖を体現できるのは彼らしかいない。」と語ったそうだ。少年隊隊長ジョニーは,さしたる理由もなく,大人や子どもを見境なく殺害し,強姦する。一番恐ろしいのは,その表情に変化がないことだ。何の感情もないまま殺人マシーンと化している。だが,彼も必要がなくなれば捨てられる運命にある。ラストで少女の両目に流れる涙が全てを集約する。 (参考資料) 1.インターネット新聞JanJanのHP 世界>映画:大量破壊の少年たち(2008.8.2) 2.外務省のHP 各国・地域情勢>アフリカ>リベリア共和国 |
|
| (河田 充規)ページトップへ |
|
| ★シークレット・ディフェンス | |
 |
『シークレット・ディフェンス』 〜平和な社会の裏で繰り広げられる情報戦〜 (2007年 フランス 1時間40分) 監督:フィリップ・ハイム 出演:ジェラール・ランバン(アレックス) ヴァヒナ・ジョカンテ(ジョアンヌ) ニコラ・デュヴォシェル(ピエール) シモン・アブカリアン(アル・バラド) ラシダ・ブラクニ オレリアン・ウィイク ★ 映画祭サイト→ |
| 9・11世界同時多発テロ後の状況を題材としたスパイ映画だ。と言っても,派手なアクションではなく,心理面に重点が置かれている。フランスの情報機関である対外治安総局(DGSE)と対仏テロ攻撃を企図する組織がそれぞれ利用できると見込んだ新人をスカウトしてトレーニングする。その状況が交互に描かれた末,双方の新人同士がテロの実行と阻止というそれぞれの目的のため行動を開始する。心理サスペンスがますます増幅していく。 | |
 |
情報機関の指揮者であるアレックスは,ディアンヌが交際を始めた青年の”父親”として姿を現し,彼女をスカウトする。彼女が諜報員デルフィンヌに仕立て上げられていく過程は,まるで蜘蛛の巣に絡め取られていくようだ。一方,母親に認められたいと渇望するピエールは,真実の道を知れば迷子にならない,兄弟は君を守り,君も彼らを守るなどと勧誘され,アジズと名前を変え,自爆テロを遂行する兵士となるための訓練を受けている。 |
| フランスのために命を落とした諜報員は少なくないようだ。本作でも,諜報員が爆死するシーンが挿入される。そのような状況の下で,ディアンヌがテロ組織の指導者アル・バラドに接触して,物語はいよいよ佳境に入る。自爆テロはどこで実行されるのか,6月18日にはどんな意味があるのかなど,緊迫した展開が続いていく。だが,全てが終わった後,最大の疑問が残る。なぜアレックスが新米諜報員をアル・バラドのもとに送り込んだのか。 | |
 |
若い男女がフランスを守ろうとする機関と攻撃しようとする組織に分かれていく。進む方向が正反対のように見えるが,実は2人ともその属する集団の中で兵器として使用される点では共通している。2つの集団がいずれも平和な社会の裏側の存在であることを意識したとき,映画の冒頭で示された「魂が悪魔の手に渡るまで悪魔は獲物を放さない」という言葉が意味深長に見えてくる。人間社会の中の目に見えない大きな存在に触れた感じだ。 |
| 【おまけ】 ディアンヌが講義室のような一室に入って席に着く。間もなく,アレックスが講師として入って来て話し始める。そのとき,聴講生の一人が突然アレックスを銃撃して立ち去る。その直後,撃たれたはずのアレックスが起き上がり,他の聴講生に「攻撃者の背丈,目の色,武器,撃った弾の数を報告しろ」と指示する。このシーンは,認知心理学で現実に行われた実験とよく似ており,本作の重点が心理面にあることを端的に示しているようだ。 |
|
| (河田 充規)ページトップへ |
|
| ★美しい人 | |
 |
『美しい人』 〜目から鱗,恋愛小説の古典が現代に蘇る〜 (2008年 フランス 1時間28分) 監督:クリストフ・オノレ 出演:ルイ・ガレル レア・セイドゥ グレゴワール・ルブランス=ランゲ ★ 映画祭サイト→ |
| 本作は,「フランス恋愛小説論」(工藤庸子著,岩波新書)でも取り上げられた「クレーヴの奥方」を大胆に翻案したものだ。これは,1678年に出版されたというラファイエット夫人の恋愛心理小説で,その約1世紀前のアンリ2世の時代の宮廷が舞台となっている。クレーヴ夫人は,舞踏会でヌムール公と出会って恋に落ち,他に愛した男がいると夫に告白するが,その衝撃が原因となって夫が亡くなり,自らはヌムール公のもとを去っていく。 これまで,ジャン・ドラノワ監督,ジャン・コクトー脚本(1961仏伊)とマノエル・デ・オリヴェイラ監督・脚本(1999仏西葡)で,2度にわたって映画化された。これらと異なり,本作ではパリの現代の高校が舞台となっている。フランスでは,サルコジ大統領が2007年5月に就任したが,その選挙中に「クレーヴの奥方」のような古典を学校で読んでも意味がないという趣旨の発言をしたそうだ。これに対する反発から本作が生み出されたという。 小説のクレーヴ夫人に当たるのが,本作では転校してきた高校生ジュニーだ。彼女は,控え目なオットーと付き合うが,ほどなくしてイタリア語教師ヌムールから求愛される。その後は,大筋において小説と同様に展開していく。オットーの死にはやや唐突な感じを受けるが,全体的には古典小説の世界が現代の高校にすっぽりと収まっており,違和感がない。それはきっと,時代が変わっても揺れ動く恋模様には何ら変わりがないからだろう。 もっとも,大人の,しかも古典的な倫理観そのままでは,現代の高校生にマッチしない。本作は,10代の若者に共通する特徴ともいえる,恋愛に対する理想や不安,感受性の強さを軸に据えて成功している。オットーは理想を追い求め,ジュニーは情熱に流されまいとする。2人とも不安な面持ちを隠せない。その結果,唐突さもまた自然に受け入れられるものとなった。そして,冬の陽光が彼らの純粋さとそれ故の痛々しさを柔らかに包み込む。 ------------------------------------------------------------------------------------- 【おまけ】 クリストフ・オノレ監督フィルモグラフィー 「Dix-sept fois Cecile Cassard」(2002) 「ジョルジュ・バタイユ ママン」(2004) 「Dans Paris」(2006) 「Les Chansons d'amour」(愛のうた,パリ)(2007) 「La Belle Personne」(美しい人)(2008) |
|
(河田 充規)ページトップへ |
|
| ★未来の食卓 |
|
 |
『未来の食卓』 〜あなたの食卓は未来につながっていますか? …小さな村の大きな挑戦〜 (2008年 フランス 1時間52分) 監督:ジャン=ポール・ジョー 出演:エドゥアール・ショーレ、ペリコ・ルガッス 2009年9月19日〜第七藝術劇場、近日〜京都シネマ、神戸アートビレッジセンター 公式サイト⇒ http://www.uplink.co.jp/shokutaku/ 監督インタビュー⇒ こちら |
| 「あなたの家族や友人で、がんや糖尿病や不妊症にかかった人はいますか?」環境健康科学研究者の問いかけに挙手したのは、ユネスコ会議の出席者のほぼ全員。がんが増えていることを如実に伝える光景はインパクトがあり、今すぐにも農薬や化学肥料による食物汚染を止めるべきという、科学者の熱意のこもった発言とともに心に残る。 | |
 |
映画は農業大国フランスの姿を映し出す。農家の人たちが宇宙飛行士のような、ものものしい装備をつけて、農薬を散布している。農薬を調合する時から、毒は空気中に広がり、人間の体を蝕んでいるのではと夫の身を案じる妻。家族をがんで亡くした女性の話は、農家で小児がんや神経系の病気が広がっている事態の深刻さを伝える。 |
| そんな危機感を切実に感じた村長が、南フランスの小さな村で、学校給食と高齢者の宅配給食をすべてオーガニックにするという試みを始め、映画は約1年かけて取材していく。コストの高い有機食品をどう負担するのか。村長と村の人たちの間で熱心な議論が行われる。この取組みの影響は、子どもたちの家庭の食卓だけでなく、近郊の農家、商店にも広がり、地産地消の新しいシステムを生み出し、村全体が有機農業に変わっていく。 | |
 |
子どもたちが野菜や果物を植え、土いじりしながら、とれたてのいちごを食べたり、パセリの茎をかじったり、レタスを取って匂いをかいでみたりする姿がいい。給食の調理人が子どもたちに料理を配りながら、話しかける姿も印象的だ。 振り返って、日本の食糧自給率はわずか40%と、先進国で最下位。パン用小麦に至っては、ほとんどを輸入に頼っている。インスタント食品や缶詰など多くの加工食品に含まれている食品添加物を、我々は毎日のように口にしている。本作を観て思わず不安を感じずにはいられなかった。 |
| 「食」と「命」はつながっている。日本は個食化も進んでおり、豊かな食文化が失われようとしている。フランスの小さな村の子どもたちの生き生きした姿は、未来への限りない可能性を暗示する。原題は『子どもたちは私たちを告発するでしょう』。未来を担う子どもたちの健康について、大人たちが無関心のままでいいのか。食べることの大切さについて深く心に刻み込み、考える機会にしたい。 | |
(伊藤 久美子)ページトップへ |
|