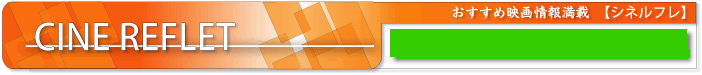| �@�E �S�[���E�V���b�s���O �m�d�v�I |
| �@�E
����т����Ӗڂ̃u�^ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �m�d�v�I |
| �@�E �G�h�E�B���Z�ҏW �m�d�v�I |
| �@�E �`�����[�g�E�t�@�C�^�[ �m�d�v�I |
| �@�E ���A���t �m�d�v�I |
�@�E �P�O�O �m�d�v�I |
| �@�@�@�@�f��Ճg�b�v�E�E�E |
| �� ���A�W�A���f��ՂQ�O�O�X�@��f��i�Љ� | |
| ���S�[���E�V���b�s���O | |
 |
�w�S�[���E�V���b�s���O�x �`�ǓƂȐS�����߂Ă����̂� �@�@�@�@�@�@ �����������i�Ɓj�ł͂Ȃ��A���������i�ƒ�j�B�` �ēF�E�B�[�E���[���� �o���F�W���E�t�@���A�A�C�����E�K�I�A�X�I�j�[���E�i�@�A�A�A�C�_�[���A���E�p�� |
| �@���Ȃ��͔������D���ł����H��������̏��i�����āA�����������C���ɂȂ������Ƃ͂���܂��H�L�x�ȐH���i�A�₩�ȃu�����h�i�A���܂��܂ȓ��p�G�݂Ȃlj��ł����낤�V���b�s���O���[���͐l�X�̗~�������A�K���ȋC���ɂ��Ă����B���̉f��u�S�[���E�V���b�s���O�v�́A�V���K�|�[���̋���V���b�s���O���[���ɂ���R�l�𒆐S�ɓW�J���Ă����B | |
 |
�@�N�����i�L���E�E���j�͗c�����납��A�V���b�s���O����D���������B�������āA�T���Ȓj���ƌ������āA���������R�Ɏg����悤�ɂȂ����B�ŐV�̃t���b�V�����ɐg����ŗD��ɕ����ޏ��́A�ƂĂ��������A�N�����A�ނقǂ��B �@����Ȕޏ����˂��܂������Ɍ��߁A�F�B�Ƙb�������ҁA�A�[�����B�����A�Ƒ��ƈꏏ�ɐH�������邪�A�ڂ����킳���A��b���Ȃ��B���߂Ă̗������܂������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B |
| �@�����āA�������̓r���ɐe�Ƃ͂���Ă��܂��A�u������ɂ��ꂽ�W�̃C���h�n�̏����A���k�B���i�̕Ћ��ɐg���B������A�H���i����������H�ׂ��肵�Đ����Ă����B
�@�N������������قȂ�ނ炾���A�ނ�ɂ͂��ꂼ��ɋ��ꏊ���Ȃ��B�N�����ɂ͍��ȃ}���V����������A�A�[�����ɂ͉Ƃ��������B�ł��A�ނ炪���߂Ă����̂́A�����������i�Ɓj�ł͂Ȃ��A���������i�ƒ�j�B�S�̂��ǂ�������߂Ă����̂ł͂Ȃ����B�����āA�u�ƂɋA�肽���v�Ƌ����Ă������k�B�Ƒ����}���ɗ��Ă����̂�҂��Ă����B��������ʼnƑ��ɌĂт�����V�[���́A����Ȕޏ��̐Ȃ��ɂ݂��`����Ă���B�f��̃��C���L�����N�^�[�̓N���������A���k��A�[�����₻�̗F�B�A�����������������Ȑl���A�x�����Ȃǂ̕`�������ƂĂ��ׂ₩�ŋ����[���B�ނ�ɂ́A�������̐l������������V���K�|�[���̍������������Ă���閣�͂�����B �@ �L���ȕ��ɂ��ӂꂽ�����́A�ǂ̍��̐l�ł�����A�ڎw���Ă����B�����A�{���̖L�����Ƃ͉��Ȃ̂��A������x�l���Ă݂����Ȃ����B |
|
�i��q
�u���j�y�[�W�g�b�v�� |
|
| ������т����Ӗڂ̃u�^ | |
 |
�w����т����Ӗڂ̃u�^�x �`�����Ƌ��b�̋��E�ŕ҂ݏグ���C���h�l�V�A�Љ�̌���` �i2008�N�@�C���h�l�V�A�@77���j �ēE�r�{�F�G�h�E�B�� �o���F���f�B�A�E�V�F�����A�W���R�E�A�����[���A�J�����E�Q���^�A�|���E�n���W���g���A�A���h�[���E�A�[���[ �ق� �E2009�N ��38�b�e���_�����ۉf��� ���۔�]�ƘA����� �E2008�N ��13�R���ۉf��� New Currents�i�V��������j���� ������f��i�i���[���h�E�v���~�A��f�j �E���A�W�A���f���2009�ɂď�f�i���{�v���~�A��f�j |
| �@�p������̂܂܁wBlind Pig Who Wants to Fly�x�B�Ȃ�Ƃ����ȃ^�C�g���ł���B�����A�����悤�ȃ^�C�g���̍�i�͂���܂łɂ��������B�w����ԂƂ��x�i1993�E�A�����J�j�Ɓw�T������ԁx�i2004�E�C���N�j���B���������Ȃ������ł���̂ɁA�g��ԁh�Ƃ��邪�A��T��`������i�ł͂Ȃ��B�ǂ�����l�Ԃ�`�����f�悾�A������g�A�C�f���e�B�e�B�h������f��ł���B��T�����g�m���}�h�g�s��p�h�Ƃ������C���[�W��l�Ԃɓ��e���Ă���̂��B�Úg�i���^�t�@�[�j�ł���B���̂��Ƃ���A�{�������̍�i���낤�Ɨ\�z�������A�ʂ����Ă��̓ǂ݂͌����ɓI�������B | |
 |
�@ �J���̓C���h�l�V�A�E�`�[���ƒ����`�[���ɂ�鏗�q�o�h�~���g���̎����V�[���B�قǂȂ��A�ϐ킵�Ă������N�����ԁB�u�ǂ������C���h�l�V�A���킩��Ȃ��I�v�ƁB���̏u�ԁA�C���h�l�V�A�E�`�[���̑I���l�����ނ����ӂ���B �ȍ~�A���˂ɐ�ւ��U�b�s���O�I�ȕҏW�ɏ悹�āA���I�Ȑl�������X�Ɠo�ꂷ��B�g�T���h�C�b�`�ɔ��|�ԉ�����ŐH�ׂ�h�Ƃ�����Ȃ��������n�̏��������_�B�T���O���X�������A�M�����Ȃ��玡�Â��s���Ӗڂ̎��Ȉ�B���Ȉ�̊��҂ł���Q�C�E�J�b�v���B�e���r�ǂœ������{�т����̏��N�ȂǂȂǁB |
| �@�ꌩ����Ɗe�L�����N�^�[�̓o�ꂪ�����̂Ȃ����̂Ɏv���邪�A�悭����ƁA�ނ炪�݂��ɘA���I�Ȑl�ԊW�Ōq�����Ă��邱�Ƃ��킩��B���ꂪ�������B�����Ă��̎��A�ϋq�͊��ɁA��v�ȓo��l���S�����C���h�l�V�A�ɂ�����}�C�m���e�B�ł��邱�Ƃɂ��C�t���Ă���͂����B���ꂪ�c���ł���B �@ ����ƁA�L���X�g���k�����̃e���r�ԑg�⓯�����҂ɑ�����A���@���ă��X�����i�C�X�������k�j�ɂȂ낤�Ƃ��Ă��鎕�Ȉ�̐^�ӂȂǁA�S�҂��ʂ�L�[���[�h���c���Ɖ������q���~�߂҂ݍ���ł����B�҂ݏオ��̂́A�C���h�l�V�A�ɂ�����}�C�m���e�B���ʂ̌��B |
|
 |
�@�r���ŁA�g�ҕ������r�ԍr�n�ŁA�Ӗڂ̓����[�v�Ɍq���ꂽ�܂ܕ��u����Ă�����i�h���ے��I�ɑ}�������B�����܂ł����A���̓͐�q�����}�C�m���e�B�̏ے����B���܂�ɂ��^�C�g���ʂ�̃C���[�W�f���ɁA�����̂����Ƃ��͊��������̂́A�؎��ŗE�C�̂������N�ɂ͌h�ӂ�\�������B |
| �@�ē̃G�h�E�B���́A�����n�C���h�l�V�A�l���؋��ł���B�o��l���͎��݂��Ȃ����A�����ɕ`���ꂽ���ʂ͎��g�����Œm����̂���B�t�@���^�W�b�N�ȃC���[�W�f���ł���̂ɁA�؎�����������̂͂��̂��߂��B���A�C���h�l�V�A�ɂ����āA�����n�l���̐�߂銄���͑S�̂�6���ł���炵���B �@ �G�h�E�B���́A�����҂ł���{��ŁA���b�e���_�����ۉf��Ղ̍��۔�]�ƘA���܂���܂����B�r���ȕ��������邪�A�m���ɍˋC�Ɉ�ꂽ��삾�B |
|
�i�쑽�@����j�y�[�W�g�b�v�� |
|
| ���G�h�E�B���Z�ҏW | |
 |
�w�G�h�E�B���Z�ҏW�x �`���݁A�ł����ڂ��ׂ���ރG�h�E�B���ē̒Z�ҏW�` �i2002�`2008�N�@�C���h�l�V�A�@43���j �ēF�G�h�E�B�� �����쏇�� 1�D�w�������Ȓ��H�x�i2003�N�^6���j 2�D�w���ƌ����������x�i2004�N�^7���j 3�D�w�̖��E�J���x�i2005�N�^7���j 4�D�w�ƂĂ��ދ��ȉ�b�x�i2006�N�^9���j 5�D�w���ɂ܂��b�x(2007�N�^6��) 6�D�w�t���t�[�v�E�T�E���f�B���O�x�i2008�N�^7���j ���A�W�A���E�~�[�e�B���O2009���V�l�E�k�[���H�ɂď�f |
| �@�@�f��Ղ́A�f��l���i�����������邽�߂ɑ��݂��Ă���̂ł͂Ȃ��B�g�m��ꂴ���i���Ƃ̔��@�E�Љ�h���A�f��Ղ̑傫�Ȗ����̈���B�Ⴆ�A90�N��ɓ��{�Ŋ����N�������C�����f��u�[����}�T���f��i�C���h��y�f��j�u�[�����A�����O�̉f��ՂŘb��ƂȂ������Ƃ����������Ő��������̂��B �@�ł́A�ډ��̂Ƃ���A�ł����ڂ��ׂ���ނ͒N���Ƃ����ƁA�C���h�l�V�A�̐V�i�ēG�h�E�B���𐄂������B�{�N1���ɊJ�Â��ꂽ��38�b�e���_�����ۉf��Ղɒ��ҏ�����w����т����Ӗڂ̃u�^�x�i2008�N�j���o�i���A�����A���۔�]�ƘA���܂ɋP�����r�p���B �@ �@���̃G�h�E�B���B�����ă|���Əo�̃��b�L�[�E�}���ł͂Ȃ��B���{�ł͂قƂ�ǖ��������A2003�N������Z�҉f��̐��E�Œ��ڂ���A���[���b�p�𒆐S�ɍ����]������Ă���B���N�̃��b�e���_���ł́A������̍ŐV��w�t���t�[�v�E�T�E���f�B���O�x��Z�ҕ���ɏo�i���Ă���A���ҁE�Z�җ�����ւ̎Q���Ƃ��������𐬂������Ă����قǂ��B����ȃG�h�E�B���ɖڂ����A���{�ɏЉ���̂�����̑��A�W�A���f��ՁB�������A��܍�݂̂Ȃ炸�A2003�`2008�N�ɂ����Ĕ��\����6�{�̒Z�ҌQ���w�G�h�E�B���Z�ҏW�x�Ƃ��ď�f���Ă��ꂽ�̂�����������B����N�x���Ɍ�Љ�悤�B �@ �@�w�������Ƃ������H�x�́A�C���h�l�V�A�Łw�R�[�q�[���V�K���b�c�x�Ƃ�������̈�ҁB�ڎ�+�p+�X���[���[�V��������g�����Ɠ��̉f������ۓI�B���y�ɍ��킹�ăe���|��ς���ҏW���܂�Ń_���X�̂悤���B���x�̍����W���W���Ƃ����C���h�l�V�A�̒��B�����ɕY���s���ȋ�C�B�E�ъ��o�C�I�����X�̉e��������߂�B���́w���ƌ����������x�́A��]���ĉf��j�ւ̓��ۂ��O�藧���m�N�����T�C�����g�d���Ă̎�����B�h�C�c�\����`��A�z������Z�b�g���G��B�G�h�E�B���͉��N�̃��[���b�p�f�������Ȃ������Ă���̂ł͂Ȃ����H�@ |
|
 |
�@�����͕M�҂̃C�`�I�V�ł���w�̖��E�J���x�B���͂��̍�i�A2005�N�ɊJ�Â��ꂽ�A���`�E�A�����J��`�Z�҉f����W�u�A�����J���E�g���E�}�v�ɂ����āA���ɓ��{���J�ρB�����̃^�C�g���́w�J���`�̎q���^�̃}�N�h�i���h�x�B�̂ǂ��ȎR�ԂɃ|�c���ƘȂވꌬ�Ƃ̒��ŁA�Ռ����}�����D�w���o�Y�ɒ���ł���B�o�Y�V�[���͒��ڕ`���ꂸ�A���̉Ƃ��_���瑨�����^���R�t�X�L�[���̃����O�V���b�g�ɔD�w�̋ꂵ���Ȑ����d�Ȃ�A�������o�߁B�����ɓ˔@���i���h�E�}�N�h�i���h�l�`���~���Ă���I�I�@�����A�n���o�[�K�[�ŗL���ȃ}�N�h�i���h�̃}�X�R�b�g�E�L�����N�^�[���B�l�`�̒��������D�w�͑����B |
| �@���b�I���Ռ��I�ȁA���܂�ɂԂ���W�J�Ƀh�̂���邱�ƊԈႢ�Ȃ��ł���B�o�Y�͖����ɍς�ł���A�Y�܂ꂽ�Ԃ�V�̓J���Ɩ��t�����邪�A����ɕ������H�B���͗���A����͌���C���h�l�V�A�̓s�s���Ɉڂ�B�����ƂȂ����J���́A�}�N�h�i���h�ɋw�G���i���h�l�`�����A����ɂނɉ��肩����c�c�@���炭�A����E�����͎̂��H�������e�Ȃ̂��낤�B���̔w�i�ɂ́A�}���ɐi�ރC���h�l�V�A�̋ߑ㉻���������鎑�{��`���ƃA�����J�̑��݂�����B�ɗ�Ȏ�`�咣�����̂܂ܒ@������̂ł͂Ȃ��A�t�@���^�W�b�N�Ȗ��t�����{���A���h�Ƃ��ĕ`����������A���ɏ�肢�I | |
 |
�@�w�ƂĂ��ދ��ȉ�b�x�́A�d�������ł��鎺����Ƃ����N�ƒ��N�����̖�����b���B��b���̂��̂͊m���ɑދ��Ȃ��̂����A�p�ɂɓ_������������肷��d���ƌ����A2007�N�̃J���k���ۉf��ՂŃp�����E�h�[����܂ɋP�����w4�����A3�T��2���x���L���Ɏc���Ă��邪�A�{��ł���������炸�̌��ʂ��グ�Ă���B�ْ��������������邾���łȂ��A�d�͋����̕s���肳��ʂ��ĎЉ�������Ă���Ƃ������@���B�䎌�⎚���ɗ���Ȃ������ɁA�f���̗͂�M����G�h�E�B���̐M�O���\��Ă���B |
 |
�@�����́A�o�X�̎ԓ��ŏo������Ⴋ�j����`�����w���ɂ܂��b�x�B�ׂ̐N�ɂӂƘb��������Ⴋ�����B��b���i�ނɂ�A�����ɐF�����Y���͂��߂�B�N�̎肪�A�����̕G�ŁA�X�J�[�g�ɐG��c�c�@�E�H���E�J�[�E�@�C��i�ɂ��ʂ���t�F�e�B�V�Y���́A�f���E�f���Ȃ��̋��ԂŔZ���ɉ�������B�������A���ɗD�ꂽ��i�Ƃ͎v���Ȃ��B |
| �@�ŐV��w�t���t�[�v�E�T�E���f�B���O�x�B�ӎv���������悤�ɐԂ��t���t�[�v�����瓮���o�����Ղɂ́A�t�����X�̉f�����l�A���x�[���E�������X���₵���匆��w�Ԃ����D�x��A�z���đ����Ƀ��N���N�������A�Ȍ�A�l�ԓ��m�̕��ꂪ�Ԃ��č��f�����B���̃V�[���͈�̉��������̂��낤���c�c�H�@�㔼�͂ǂ����R�[�G���Z�핗�ɁB���������A�R�[�G���Z����w�����͍��x�Ńt���t�[�v�������Ă��������B�t���t�[�v�����̓��������������x�b�h�V�[�������S�ȏ���U���A�ʔ����B���̑��A��ʂ̍�荞�݂ȂǁA�C���䂩��镔�������������ɁA�܂Ƃ܂�̂Ȃ��\�������Â�����܂��B �@�U��i�̑S�Ă�����Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�ǂ̍�i�ɂ��ˋC�������Ă���A���Ă��ĖO���邱�Ƃ͂Ȃ��B�G�h�E�B���̍�i�����{�̉f��قŌ��J�������������������Ƃł͂Ȃ����낤�B���̋@��ɁA���̖����o���Ă����đ��͂Ȃ��B |
|
�i�쑽�@����j�y�[�W�g�b�v�� |
|
| ���`���R���[�g�E�t�@�C�^�[ | |
 |
�w�`���R���[�g�E�t�@�C�^�[�x �`�f��j��ŋ��̃A�N�V�����E�q���C���a���I�I�` �i2008�N�@�^�C�@1����33���@�z���F���k�V�Ёj �ēE����F�v���b�`�����[�E�s���Q�[�I �A�N�V�����ēF�p���i�[�E���b�g�O���C �o���F�g�W�[�W���[�h���[�j���E�E�B�T�~�^�i���A�������A�{���p�b�g�E���`���o���W���� �ق� �y���A�W�A���f���2009 �I�[�v�j���O��i�z 3��13���i���j 18�F30�J����ABC�z�[���i���������V�Љ����j ���I�[�v�j���O�C�x���g���v���b�`�����[�E�s���Q�[�I�ē̕��䈥�A���� 5��23���i�y�j�`�@�Ȃ�p�[�N�X�V�l�} �ق��ɂđS�����[�h�V���[ (C)2008 sahamongkolfilm international all rights reserved. designed by puninternational �� �����T�C�g�� |
| �@�{�삪�f��f�r���[��ƂȂ�A�g�W�[�W���[�h���ƃ��[�j���E�E�B�T�~�^�i���͂Ƃɂ��������I�@�����I�I�@60�N��Ɂg�������̏����h�ƌĂꂽ�`�F���E�y�C�y�C���A70�N��Ɉꐢ���r�����w�����E���x�̃A���W�F���E�}�I���A�w���K�E���x�V���[�Y�̎u����x�q���A�N��l�Ƃ��Ĕޏ��ɂ͓G��Ȃ��B�~�V�F���E���[�H�@�A���W�F���[�i�E�W�����[�H�@�t���I�@���ƂƂ����₪����I�I�@ | |
 |
�@1984�N���܂�̃��[�j���E�E�B�T�~�^�i����11�Ńe�R���h�[���n�߁A���Z�݊w����1996�N�ɂ̓o���R�N�E���[�X�E�e�R���h�[���ŋ����_�����l������܂łɂȂ����B����Ȕޏ������o�����̂́A�w�}�b�n�I�x�i2003�j�A�w�g���E�����E�N���I�x�i2005�j�Ő��E���̃A�N�V�����f��t�@��������̉Q�ɒ@�������R���r�F�v���b�`�����[�E�s���Q�[�I���p���i�[�E���b�g�O���C�B2�l�́A�ޏ�����ďグ�邽�߁A4�N�Ԃɂ��y�ԉߍ��ȃg���[�j���O���ۂ����B���̊ԁA�E�B�T�~�^�i���́A�e�R���h�[�����łȂ��A�^�C�̍��Z�ł��郀�G�^�C�i�^�C���{�N�V���O�j��}�[�V�����A�[�c���̓��B�������A���̌��ƂȂ鉉�Z�ɂ��Ă��݂�����ƒb���グ���A���́E���_�̗��ʂŔ���I�Ȑ����𐋂����̂ł���B�X�ɁA�B�e��2�N�Ԃ�v���A���|��6�N�ɋy�ԃv���W�F�N�g�������B�����ɉf��j��ŋ��̃A�N�V�����E�q���C�����g�W�[�W���[�h���a�������̂ł���I |
| �@�g�W�[�W���[�h��������̂́A�^�C�E�}�t�B�A�̃{�X�g�i���o�[�W�h�i�������N�玗�j�̈��l�ł������W���Ɠ��{�l���N�U�̑啨�E�}�T�V�̊Ԃɐ��܂ꂽ�����[���i�T�j�B�}�T�V�͋A�����A�W���͈�l�Ń[�����o�Y�B���ǂ������[�������A��̈����ڈ�t�Ă��������Ɛ��������B����ȃ[���ɂ́A���̖ڂŌ����������u���̓��ɉ䂪���Ƃ��Ă��܂�����\�͂̎����傾�����B�A�N�V�����f��̃r�f�I���ς邾���ŁA�܂����������{���̃A�N�V�������J��L���邱�Ƃ��ł���̂��B����Ȃ�����A�W���������̔����a�ɖ`����Ă��邱�Ƃ����o�B�[���́A�c�Ȃ��݂̃����Ƌ��Ɏ��Ô�̂��߂ɖz�����邪�A���̍Œ��ɃW���ƃ������g�i���o�[�W�h�ɕ߂����Ă��܂��B�[���͒P�g�A�g�i���o�[�W�h�̃A�W�g�Ɍ������I | |
 |
�@�@�v���b�`�����[�E�s���Q�[�I��i�̃g���[�h�}�[�N�ł���A�gCG�Ȃ��I+���C���[�Ȃ��I+�X�^���g�Ȃ��I�h�́g�ɂ݂̓`���A�N�V�����h�͖{��ł����݁c�c����A����ǂ��납���\�{�Ƀp���[�A�b�v���Ă���I�@����Ȑ��g�̃A�N�V�����A�������ƂȂ����I�I�@�w�h���S���{��̓S���x�i1971�j�A�w�v���W�F�N�gA�x�i1984�j�A�w�L���E�r���x�i2003�j�̃p���f�B��I�}�[�W�����y�钆�A���炩�ɂ��̏���s������A�N�V�����Ɍ������A���O���ƊJ�����ςȂ��ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��������ł���B�����ȂƂ���A�O��30���̃_���_���Ƃ����h���}�W�J�͂��Ƃ炢���A���������߂���Ό�̓W�F�b�g�R�[�X�^�[��̖ʔ������B�q�W���q�U�̎g�����ȂǁA���G�^�C�����^�C�Ȃ�ł͂̂��́B�i���Z�t�@�����X��{���̃A�N�V�����������ɂ���B���ɁA�r���̊O�ǂ��g���ČJ��L������N���C�}�b�N�X�͈������I |
 |
�y�쑽����̉f�擤�m���F�w�`���R���[�g�E�t�@�C�^�[�x�z �E �[���̕��ł���}�T�V��������͉̂�炪��������ƈ������B������W���Ƃ܂����ʈ����[�����~�����߁A�C���z���āg�i���o�[�W�h�̃A�W�g�ɉ��肱�݂�������p��Ⴢ�邪�A���{������g�����A�N�V�����̑f���炵���ɂ́A�X��Ⴢ��I�@����189�p�i���ۂ�190�p���I�j�̒��g�ɓ������������Ƃ́A������NHK��̓h���}��A�w���̌��x�i2006�j�A�w�B���Ԃ̎O���l THE LAST PRINCESS�x�i2008�j�ȂǁA���㌀�o�����������Ƃł����炩�B����Ȉ��������́A1994�N������ۂɌÕ��p�ɋ���ł���Ƃ��B |
| �E �^�C�f��̗��j�͌Â��B�t�����X�̃����~�G�[���Z�킪���������V�l�}�g�O���t�̏���f��1895�N12�������A�͂�1�N�����1897�N6���Ƀ^�C�����ŏ�f����Ă���B����ȃ^�C�ŁA���߂ď�݂̉f��ق��c�Ƃ��J�n�����̂�1905�N�B�Ȃ�ƌo�c�҂͓��{�l�ł������B���̂��߁A�^�C�ł͉f��̂��Ƃ炭�g�i���E�C�[�u���i���{�̃X�N���[�����j�h�ƌĂ�ł��������B���̊��Ƀ^�C�f��́A�f��Տ�f�������āA���{�ł͂قƂ�nj��J����Ȃ������B���߂ē��{�Ń^�C�f�悪���ƌ��J���ꂽ�̂�1995�N�B�`���[�g�E�\���X�B�[�ē̎Љ�h�h���}�w���A���ƃ��b�g�x�i1994�j�ł���B�^�C�Y��y�f��̓��{���J��2000�N�̃y���G�[�O�E���b�^�i���A�[���ēw�U�h�w�s�x�m�h�m�X�@�V�b�N�X�e�B�i�C���x�i1999�j�܂ő҂��˂Ȃ�Ȃ������B | |
| �i�쑽�@����j�y�[�W�g�b�v�� |
|
| �����A���t | |
 |
�w���A���t�|���S�x �`���X�~���E�A�n�}�h�ēɂ��ā` The Convert �i2007�N�@�}���[�V�A�@�P����27���j �ēF���X�~���E�A�n�}�h �o���F�u���C�A���E���b�v�A�g�j�[�E�T�o�����g�D�A�V�����t�@�E�A�}�j�A�T�C�h�E�U�C�i���E���V�b�h |
| �@2007�N�H�̑��A�W�A���f��ՁB�u�v���l�b�g�{�P�v�Ƃ��������ȉf��قŃ��X�~���E�A�n�}�h�ē̓��W��f���s��ꂽ�B���C�Ȃ��ςɍs���āA���̐����Ɉ��|���ꂽ�B����L���Ŕ������f�����E�ɂ�������Ђ����܂�A�J��Ԃ��ςɍs���ẮA���ԒB�ƔM����荇�����B | |
 |
�@���ʂȐ������Ȃ��A�ȗ��̎d�����݂��ƂȌ����B�ḗA�����̕`���������E���ϋq�ɂ��[���`���邽�߂ɁA���l�����t��I�Ԃ悤�ɁA�e�[�}�̊j�S�ɔ���V�[����I�сA�W�X�Ɩa���ł䂭�B |
| �@��l���ɁA��̓I�ɉ����N�������̂��͂�����Ƃ͕`���ꂸ�A�B���ł����Ă��A���̕\��A���͋C����A�ǂ�Ȋ����̂��Ƃ��N�������̂��A�z�����邱�Ƃ��ł���B����ɗ]�����������قǁA�ϋq�͎����̑��ɂЂ����邱�Ƃ��ł��A�����̗��e�̂��Ƃ��v���o������A�g�߂Ȑl�ւ̈���A�v�����A�D�����ɂ��čl�����肷��B | |
 |
�@��l�������̉^�����A���Ƃ��c���Ŕ߂������̂ł����Ă��A�Ƒ�����l�炪���Y���A��܂������āA��������z���Ă����p����́A�l�Ԃ̋����Ƒ������`���A���|�����B�ē����������߂�܂Ȃ����́A�ǂ�����O�ŁA�������A���z�I���B ���X�~���E�A�n�}�h�ḗA�b�l�ƊE�Œ������A2003�N�Ɋēf�r���[�B2007�N���㎞�̃V���|�W�E���ŁA�f����ǂ�����Ă���̂��͂悭�킩��Ȃ��A���e�����C�Â��悤�Ǝv���Ă������A�Ɣ������ꂽ�B����Ȍ����ł���Ȃ���A����ȂɎ���L���ŁA�N�̐S�����_�炩���g�����n�����Ă��܂����E�ݏo���Ă��܂��̂�����A�����B �@ ����Ȋē̍ŐV�삪���̂���3��16���ɏ�f�����Ƃ����B�Ⴂ�o���ƐN���t�̏o������ɁA�@����M���߂���e�[�}�ɓ��ݍ���i�Ƃ̂��ƁB�ḗA�Ƒ��̊Ԃ̏�̋@����`�����Ƃɂ����Ă͔��Q�̘r�B���Ќ���ɋ삯���Ă��̖ڂŊm���߂Ăق����B |
�i�ɓ��@�v���q�j�y�[�W�g�b�v�� |
|
| ���P�O�O | |
 |
�w�P�O�O�x �`�l���̊�т����߁A�T�������W���C�X�̐������` �i2008�N�@�t�B���s���@�P����57���j �ēE�r�{�F�N���X�E�}���e�B�l�X �o���F�}�C���[���E�f�B�\���A���[�W���E�h�~���S�A�e�V�[�E�g�}�X ���A�W�A���f��ՂR��15���i���j�ߌ�U��40������i���{����f�j �c�����Q�X�g�F�N���X�E�}���e�B�l�X�ēA���[�W���E�h�~���S�i�e�F���r�[���j�i�\��j�c |
| �@���N�O�w���ʑO�ɂ�����10�̂��Ɓx�i2003�N���J�A�J�i�_�E�X�y�C���A�C�U�x���E�R�C�V�F�ēj�����{�ŐÂ��ȃq�b�g���ĂсA�����̏����̋������ĂB�{��́A�C���h�l�V�A�Łw���ʂ܂łɂ�����100�̂��Ɓx�Ƃ����邾�낤�B | |
 |
�@100�Ȃ�ė~����Ǝv�����ƂȂ���B��l���W���C�X�͓Ɛg�̃L�����A�E�[�}���B����ŗ]���������ƒm��B���ׂ����ƁA��肽�����Ƃ͎R�قǂ���B�܂��͐g�Ӑ����Ɏn�܂�A�H�ׂ����������́A�������������Ƃ������ɏ����o���A��l�ł��邢�͐e�F�̃��r�[�ƈꏏ�Ɏ��X�ƒ��킵�Ă����B |
| �@���ɒ��ʂ��āA�W���C�X���×~�ōs���I�Ȏp�́A�����̋C�����ɐ����ŁA�ςĂ��Ă������肵���C�����ɂȂ����B��D���ȃP�[�L��H�ו��������ɖj����V�[������ۓI�B�����邱�Ƃɂ������A�l���̊�т�T���A���ߑ������W���C�X�̐������́A�ς�҂ɁA�ʊ��Ƀ`�������W���A�l����搉̂���E�C��^���Ă����B | |
 |
�@�W���C�X�̕��o�A�����q�炪�A�߂��݂��A���肠�鎞�Ԃ��y�����ꏏ�ɉ߂������Ƃ���p���A���[���A�������ĕ`�����B�ꂪ�W���C�X�ɂ��Ăق������ƁA�����q���W���C�X�ƈꏏ�ɂ��������ƁA���ꂼ��̎v���A�����`���A�D�����ƒg���������ӂꂾ���B |
| �@������ڑO�ɂ��āA���������ΐ��̂قƂ�ɗ��������A�l�͈�̂ǂ�Ȏ����̎p�𐅖ʂɉf���o�������Ɗ肤�̂��낤�B�����̂��߁A�l�̂��߂ɁA���܂ʼn������Ă��ꂽ�̂��B�������낵�A�������ރW���C�X���݂��ސ�捂Ȑ��E�̒��ŁA�W���C�X�̉��₩�ȕ\����܂ł��S�Ɏc���Ă���B |
|
�i�ɓ��@�v���q�j�y�[�W�g�b�v�� |
|
|
|