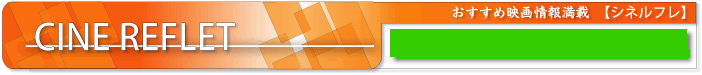|
| ★『谷中暮色』 舩橋淳監督インタビュー | |
 |
『谷中暮色』 〜人々の心に今なお息づく五重塔をめぐって〜 ((2009年 日本 2時間) 監督・脚本・編集:舩橋淳 出演:野村勇貴、佐藤麻優、加藤勝丕、小川三代子 シネーヌーヴォ上映中(6月11日まで) 公式サイト⇒ http://www.deepinthevalley.net/ |
 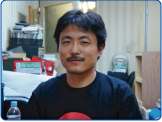 |
ドキュメンタリーとフィクションを融合し、幸田露伴の小説『五重塔』の江戸時代の世界と、谷中五重塔が焼失する昭和32年、そして現在と、3つの異なる時制を行き来しながら、谷中という土地に住む人々の過去と今とを映し出す、不思議な作品が生まれた。 ホーム・ムービーの保存・修復をするNPOで働くかおりは、谷中五重塔のフィルムを探しだそうと、地元の郷土史家や伝統工芸職人への取材を試みる。そんなときチンピラの久喜と出会う。この二人の物語を軸に、江戸時代中期、五重塔建立に身を捧げた大工、十兵衛の物語と、谷中で暮らす墓守のおばあさんやお寺の住職、地元の人々への監督自身による取材シーンとで構成される。 谷中に住む人々の姿を、生活感あふれる映像で生き生きと写しとったドキュメンタリーの部分が、なかでも魅力的だ。東京では昨年秋に公開されて話題を呼び、待つこと半年、やっと大阪での公開となった。舞台挨拶で来阪した舩橋淳監督に話をうかがうことができたので、関西大学で行われた監督の講演会の概要とともにご紹介したい。 |
| 2007年、ニューヨークから東京の下町、寺社と墓地の多い谷中に移り住んだ舩橋淳監督。生活の延長で出会ったおもしろいと思ったものをドキュメンタリーとして撮っていきたいと考えていた。ある日、墓地を歩いていた時、一人の全盲のおばあさんに出会う。あちこちの墓にぶつかりながら歩いていくので、尋ねると、「今日は○○さんの法事で、お掃除しとかなきゃいけない」と言う。後をついていくと、何百もの墓の中からきちんと目的のお墓にたどりついた。話を聞くと、30年以上、霊園の墓守をしており、500〜600もの墓石の場所と名前を正確に記憶していた。「誰も法事に来ない時は、私がお墓に花を生け、線香をあげるんです。どのお墓も分け隔てなくきれいにするのが私の役目なんです」と言って、お墓の中を歩いていくおばあさんの姿をみて、監督は、語り部のように感じ、このおばあさんのドキュメンタリーを撮りたいと思ったのが、この映画を撮る最初のきっかけだったそうだ。「谷中でドキュメンタリーを撮ろうとしていたのと機を同じくして、僕が教えていた映画専門学校の生徒たち、俳優の卵なんですが、をつかって何か映画をつくってほしいと学校側に言われ、この企画を出したんです」 | |
 |
監督は、谷中に住む老人たちに話を聞いていくうちに、誰もが、50年ほど前に焼失した五重塔のことを口にし、再建したいと言うことに気付く。なぜ建てたいのか、かつて五重塔はどんな意味を持っていたのかをインタビューしていくことで何かみえてくるのではないか、それを映画にしていこうと考えた。「映画に登場する郷土史家の加藤勝丕さんも五重塔が本当に好きで、幼少の頃からの遊び場だったのですが、五重塔が燃えてなくなる現場を見ていないんです。だから、失ったという喪失感が大きく、五重塔の不在について、いつもいろいろ考え、再建したいと思っています。そうした加藤さんの思いに押されて、この映画を撮ってみたいというところにもつながりました」 |
|
撮影スタイルについては、「前作『ビッグ・リバー』(2005年)での、スタッフが40〜50人いて、非常に重い着ぐるみを着て動く相撲取りのような気分でもどかしかったという経験を生かし、今回は、基本的に、僕と2、3人のクルーで、ドキュメンタリーのように撮っていきました。地域に溶け込むようにして撮影していくスタイルが、僕には合っているなと思いました」 谷中では寺社が多いだけあって、法事もよく見かけるそうだ。「法事という儀式も面白いなと思いました。僕も、家が仏式だからやっているだけで、自分が仏教徒という意識はありません。葬式や法事の時だけ仏教徒のふりをして、形だけになっています。法事も、たくさんの人が来ることもあれば、2人とか0人の時もあり、墓守のおばあさんの姿をとおして、谷中の家族の形態の変化もみることができたら、おもしろいのではないか。時代とともに変わったものと、変わらないものとが浮き上がればいいと思いました」 |
|
 |
幸田露伴の小説の世界を映画に交錯させたわけを尋ねると、「失われたものが一体何を象徴していたのか考えた時、五重塔をつくった時代の人たちがどんな思いを込めてつくったのかということも描いたらおもしろいのではないかと思ったんです。現代の五重塔を失った人たちが過去に思いを馳せる姿と、まだ何もない過去の人たちがどんな思いを五重塔に込めて建てたのか、双方向から描くことで、その真ん中にある五重塔が何を象徴していたのかが浮かび上がってくるのではないか。そして、映画の中で五重塔が燃えた瞬間に、五重塔が象徴していたものの大きさが、観客にも感覚的に体感できるのではないかと考えました」「五重塔は、単にきれいな建築物という以外に、かつてあったコミュニティの統一感、人々がコミュニティ同志で助け合った共同体意識を象徴していたのではないかと思います」 |
|
昭和32年に五重塔が焼失するのを記録したフィルムは、映画を撮影中に偶然、発見されたそうだ。しかし、もし見つからなければ、この五重塔が失われたという喪失感をどうやって表現すればいいと監督は考えていたのだろう。思い切って聞いてみた。「そもそも失われたものについての映画になると思ったので、皆が『あれはよかった…』、『昔はあれがあったのに…』と語る、その思いについての映画であればいいと思っていました。だから、観客の方々にも過去に思いを馳せてもらえたら、五重塔は写真だけみせて、あるいは、写真さえ使わなくてもいい、とも思っていました。見つからなくてもいいと思っていたのですが、見つかっちゃったので、使いました」
白黒とカラーの映像が混在していることについては、「過去に思いを馳せてみる時、過去が現在のように生き生きと思えたり、現在が過去とつながっているように見えたりします。そういう過去の中の現代性、現代の中の過去性が、観ている人の中でも立ち起こってくれたらという意味で、白黒とカラーの映像を混ぜてみました。だから、過去といえば白黒、現代はカラーとはっきり区分した描き方には、すごく抵抗があって、過去がすごく色付いて鮮やかであってもいいし、現代が過去と地つなぎのように白黒であってもいい、それが僕の映画のテーマに対する視点です」 地元での上映会では好評だったそうだが、監督自身は、「すごく低予算でつくった映画で、谷中で継続的に上映されたりして、末永くやってほしいですね。谷中のことを知りたいと思った人が、普通に観ることができるよう、もっと広めていきたいと思っています」と話してくれた。緊張の中、取材は終わったが、かおりや久喜がフィルムを探すために地域の人に取材していく、フィクションともドキュメンタリーともいえるシーンについて、もっと話を聞きたくなった。翌々日、関西大学で行われた監督の講演会を聞きに千里山キャンパスに赴いた。以下、その概要をご紹介したい。 文学部映像文化専修の学生達を主な対象に、授業の一環として行われた講演会では、まず、監督自身の経歴をたどることから始まった。東京大学で表象文化論を学び、蓮實重彦氏にかどわかされて年200本以上の映画を観たという監督は、映画にどっぷり浸ったこの頃の原体験が今の自分にとっても貴重だと言う。処女作の16ミリ長編『echoes
エコーズ』(2001年)では、登場人物同士の視線の合わせ方や照明の使い方など、他の映画のまねごとが多く、いろいろな監督から受けた影響を、どう整理していいかわからないまま、全部ぶちこんだそうだ。 |
|
 |
ポルトガルのペドロ・コスタ監督は『ヴァンダの部屋』(2000年)で、ドキュメンタリーとフィクションという区分を無効にする、美しい映像と物語を紡ぎだした。中国のジャ・ジャンクー監督は、『長江哀歌』(2006年)で、常連の俳優たちを2、3人現地に連れていき、ダム建設のために沈んでいく村の人々の中で、フィクション的な物語を展開させ、ドキュメンタリーと混合させた。舩橋監督もまた、このドキュメンタリーとフィクションの混合により、今、問題が起きているところにカメラを持っていって、かつて観てきた劇映画のような美しい画面で撮りたいと思ったそうだ。 |
|
監督は、ちょうど新作『何も変えてはならない』の宣伝のために来日していたペドロ・コスタ監督と対談したばかり。ポルトガルのスラムで長期間かけて個人的な関係をつくりあげ、そこの人たちとの関係を大切にし、その延長上で映画に携わりたいと考えたコスタ監督は、コミュニティに自分が溶け込む中でみえてくるものこそが真実であり、「Cinema with Justice」であると言われたそうだ。 監督がこれまで模索してきた映像話法の話を聞くことができ、とても興味深い内容だった。もう一度、『谷中暮色』を観たくなった。時間が経つにつれ、フィクション部分での俳優たちの未熟さも気にならなくなり、それ以上に、あの墓守のおばあさん、素人ながらに見事に演技もされた郷土史家の加藤さんら、映画に登場する谷中の人々の顔が、リアルによみがえってきて、とても懐かしい気持ちになった。その暖かな表情は、五重塔が燃えあがる映像とともに、心に深く焼き付けられた気がする。 |
|
(伊藤
久美子)ページトップへ |
|
| |
|